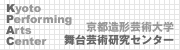May. 21 wed. 「小さな旅と、戦後サブカルチャー史」



■しかも、過去の「新宿」の話が中心になるのはいかがなものかと思いつつ、もっと「現在」と結びつくことがあるとその可能性を探っている。系譜を追うことで現在もまたあきらかになると思うが、もっと資料にあたらなければ。あと、九〇年代のこと、その時代の「渋谷」を書かなければと考えるが、まだ「新宿」だ。しつこいほど「新宿」だ。もうなんとなったら「新宿論」だ。そして「紀伊國屋書店」だ。それを設計した前川國男だ。いいのかなこれで。悩む。
■さて、個人的な事情があって、20日、茨城県の下妻に行った。関東平野はまったいらだ。まあ、丘がないわけではないが、山間部に比べれば当然だが、そうではない土地と比べても平野が広がり、クルマで走っているとよく似た風景が続きどこを走っているのかよくわからない。ときどき、異様な建造物を遠くに発見する。安っぽい城があったり、さらに不可解な建物を見つけ寄り道して近くまで行くと、まあ、たいていが宗教施設だ。なぜか巨大だ。奇妙なデザインだ。そしてこうした建物にもそれをデザインした建築家がいるはずであり、施工業者がいるはずだが、あまり語られることがないと感じるのは、僕がそれほど詳しく調べてないだけだろうか。むかしは建築雑誌を毎月読んでいたが、いまではまったく目を通していないので、建築の世界のことと言えば、ときおり開かれる建築家の展示などでその作品に触れるぐらいだし、あるいは、地方に行ったとき美術館に立ち寄りそれが誰の仕事かあとで知るぐらいか。あるいは話題になった建築がある。新しい国立競技場のこととかね。
■茨城の、なんという地区にあるのかわからないが、平野にどかんと存在した建築の設計者のことはわからない。すごいデザインで、もしかすると建築家にしたら面白い仕事なのかもしれない。新宿の紀伊國屋書店は前川國男の手になる建築だということはこのあいだも書いたが、それで時代を比較するのに、ゼロ年代以降のコミケが開催されている「東京国際展示場」のあの異様なデザインはどういうことになっているのかと思って調べたところ、株式会社佐藤総合計画という、なんというんでしょうか、企業アーキテクトデザインチームというのでしょうか、そういったところだった。日建設計とかああいった大きな会社と同じだろうか。とはいえ、こういったところにも優れた建築家がいることはよく知られている。
■だが考えてみれば、たまたま「東京国際展示場」はコミケの会場として近年、定着したのであり、それまで何度か会場を追放されている。ここで、「コミケ」と「紀伊國屋書店」を二項の対立にすることに意味はないかもしれないものの、なにか時代を考える手がかりになるのではないかと思ったのだ。というのも、サブカルチャー史を考える上で「六〇年代を象徴した新宿」という規定において大きな意味を持つ「新宿紀伊國屋書店本店」があり、いわゆる「ゼロ年代」を象徴する「東京国際展示場」だ。ここでもまた、コミケを開く条件に適した「どこでもよかった広大な建造物」がある。誰が設計したか固有名がはっきりしない。紀伊國屋書店本店の建物には前川國男というはっきりした作家の名前があった。チェルフィッチュの舞台『三月の五日間』の、「どこでもよかった渋谷」と、規模の大きさはともかく、文化的なというか、意味的に「どこでもよかった東京国際展示場」が現在なのか。
■だからあらためて、学生と演劇の授業をするのなら、『三月の五日間』の分析として、六本木の「スーパーデラックス」を出たあと、円山町のラブホではなく、ほかに行ってもよかったラブホを調査することから始めたい。二人は歩くのだ。六本木通りを歩き、渋谷の駅前に出る。それから東急本店の方向に向かい、それから円山町に行ったか、それとも、道玄坂を上がって百軒店を入っていったのか、あるいはその先まで道玄坂を上がり右に折れたのか。いろいろ考えられる。だが、ほかにも、六本木、赤坂、恵比寿など、いくつもラブホの候補はあったとすれば、「どこでもよかった渋谷」について考えることがゼロ年代のなにかを見いだすことになるだろう。1972年、『ぼくらが非情の大河をくだる時』の兄弟は、「新宿へ、そして、どこかわからない幻想の都市」へと歩き出した。この演劇性と、「どこでもよかった渋谷」がもたらす演劇性のちがいを読み解きたいのだ。それは身体論であるのと同時に、文化論だ。都市論でもある。
■だから、紀伊國屋書店が前川國男によって新しく出来たこと(もちろん紀伊國屋書店は新宿東口の現在の場所にそれ以前からあった)によって、それが象徴になり、新宿が「ユースカルチャー」「カウンターカルチャー」「サブカルチャー」の拠点となったとしたら、その1964年にもっとなにかが起こっているにちがいない。オリンピックだけではない。それまでのなにかを壊すほどの文化的衝撃が生まれたと想像する。そして、63年にまたべつの過去が終わっている。とはいっても、「新宿」が突然、出現したのではなく、なにか歴史的な系譜のなかでその時期に光があたり、特別な人間がそこに登場したと考えるべきだろう。しかも、消えてしまった「過去」は、過去として、葬られるわけではない。べつの姿でまた現れるかもしれない。いま、あたりまえのように公演されている舞台も、構造だけ取り出せば、あるいは本質をよく見れば、過去の演劇と同じであることは数多くの舞台にある。
■「アートシアター新宿文化」が『尼僧ヨアンナ』を上映し、記念すべきATG第一回公開作品になったのは、1962年だ。オリンピックの直前、ハイレッドセンターは「首都圏清掃整理促進運動」(1964)という芸術活動をしている。「1968年」は特別なものとした語られることが多い。しかし、あらためて1963年と、64年を考えることが、「新宿前史」として意味があるのではないか。もちろん「悪場所」として本来が魅力的だった新宿はずっと存在していた。「盛り場」としての新宿はあったにちがいない。だがそれとは異なる文化の萌芽があったからこそ、新宿はほかの街区とは異なって発展していった。「アートシアター新宿文化」「紀伊國屋書店」「風月堂」「黙壺子フィルム・アーカイブ 」、あるいはジャズ喫茶たち。暗がり。路地……。
■前川國男をもっと勉強しよう。あと、もっとちがうことで「六〇年代の新宿」だけではなく、「現在」を考える方法を思いついたのだが、忘れてしまった。
(9:46 May. 22 2014)
May. 18 sun. 「いわゆるゼロ年代のこと。演劇のこと、文学のこと」



■アンスティテュ・フランセ東京というのは、その名前だけ聞いて、日仏会館が名前を変えたのかと思っていたら微妙にちがった。あと、はじめにメールで出演を依頼されたときも、お茶の水にあるアテネフランセかと思っていたのだ。直前に場所を確認しなければ、あやうくお茶の水に行くところだった。家の近くから百円バスに乗って新宿へ。それから中央線で四谷。総武線に乗り換えて飯田橋で降りる。飯田橋から意外に遠い。坂道を少し登ってアンスティテュ・フランセ東京の建物があったがとても雰囲気のいい場所だった。建物もきれいだし劇場もしっかりしている。通訳を務めてくれる女性によると、青山真治監督がここでよく自作の上映とトークをしているとのことだった。
■ヴァレール・ノヴァリナさんの戯曲は翻訳を読むとかなり難解な印象を受けるが、ドキュメンタリー映画で作品が上演されるのを観ると、客席から笑いが起こり、戯曲から受けるのとはまた異なる感じだ。翻訳の戯曲はそうなるのだろうか。ずいぶん時代は変化したとはいえ、たとえばベケットの翻訳を当時の、翻訳家も演劇人も、ひどく生真面目に受け止めていたと思うのだが、それは時代だけの問題ではなく、言語を移しかえるときに起こってしまう齟齬かとも思う。あるいは、翻訳の段階で、その「笑いが起こるような要素」を言葉にするのが困難という問題もあるだろう。かといって、無理して笑いにしようとすると、そこに「笑いのセンス」というんでしょうか、それが問われ、そんなに無理しなくていいよということもあるし、あと、笑いは文化的背景が(無声喜劇映画時代の笑いはべつかもしれないが)あって、それを言語を置き換えて表現するのはかなり難しいように感じる。言葉そのもだけではなく、いわゆる「トーン」で笑うこともあるしね。
■そしてトークの内容は司会してくれたフランス人の方の質問が抽象的で難しく、自分でもなにを答えたのかよく記憶していない。
■その後、桜井圭介君(@sakuraikeisuke)からTwitterを通じて、1972年に新宿が終わったことを裏付けるように、73年にパルコ劇場が開館していることを教えてもらった。記録を調べる方法があるはずだが、うちに資料があった記憶がないので桜井君のツイートを引用させてもらうと、
ツイートを読んだ時点で、状況劇場が新宿を追い出され渋谷で公演をはじめた場所(渋谷金王八幡宮)はたまたま知っていたが、では唐十郎が新宿を去ったことをもって(69年)、「新宿が終わった」にならないのは、それでもなお新宿は文化的に機能していたからだし(「新宿プレイマップ」という伝説的なリトルマガジンが刊行されたのは69年7月)、それに変わる文化的拠点がほかの街区に存在しなかったからだ。あるいは文化がまだ沸き立つ空気が(「新宿プレイマップ」の例を持ち出すべくもなく)あったからだ。日記拝読。「別冊新評 唐十郎の世界」年譜によると、69年(西口公園で警察と衝突後)『少女都市』から「紅テントは新宿から渋谷へ移った」とあり(「寺山修司から黒い花輪が送られ渋谷街頭で天井桟敷と乱闘」ともw)翌70年までは渋谷(どの辺でしょう?)で活動
71年『吸血姫』湯島天神、吉祥寺、渋谷。72年『二都物語』から上野の水上音楽堂、74年『風の又三郎』で上野と夢の島。僕はその『風の又三郎』を上野で見たのが最初でした。プロペラ機が不忍池の中からザバーって出てきて空に飛び立つ!という終幕にヤラれたクチです。
いずれにせよ「1972年に新宿は終わった」はその通りだと思います。渋谷の「西武劇場」が開館したのが1973年で、土方巽(72年に新宿アートシアター『四季のための27晩』の後の)『静かな家』、安部公房『愛のメガネは色ガラス』等が上演されているわけですから。
『別冊新評 唐十郎の世界』に上演目録が!69年『少女都市』渋谷金王八幡宮。70年『愛の乞食』吉祥寺名店会館裏、渋谷北谷稲荷神社。71年『吸血姫』湯島天神、吉祥寺(同前)、渋谷西武百貨店駐車場。西武の駐車場というはどこかな?『田園に死す』の最後の屋台崩しのあそこなんだよな。
■と、そこまで書いてわかったけど、「新宿プレイマップ」は僕が書いている「新宿は1972年に終わった説」を見事に証明、というか体言している。なにしろ、その刊行時期は、1969年7月から1972年6月までだからだ。そのあたりの事情は『60年代新宿アナザー・ストーリー―タウン誌「新宿プレイマップ」極私的フィールド・ノート』(本間健彦/社会評論社)に詳しい。
■そして、桜井君が呟いていたように、1973年には渋谷には早くも八〇年代を代表する文化潮流となる西武セゾン系に属する、「西武劇場」が開館し、そこで、「アートシアター新宿文化」で72年に公演したばかりの土方巽が公演しているのは象徴的だ。72年に新宿が終わったことが示しているのは、つまり六〇年代的なものがここで終わったということだろう。サブカルチャー(ポップカルチャーとは厳密に区別したときの文化的潮流としてのそれ)は、明治通りを渋谷方向に進む。72年に新宿が終り、七〇年代が始まると、1983年に原宿に「ピテカントロプス・エレクトス」という日本で初めてのクラブがオープンしたことで八〇年代が始まる。ぴったり十年後だ。
■さて、話を一気に、いわゆる「ゼロ年代」に進めます。八〇年代の話はもうかなりしてしまったのでとりあえず置いておき(その後の発見もあったものの)、あと九〇年代については、「テクノと青山正明」「ある種の九〇年代的な毒」、そして「九〇年代サブカル」については興味深く感じる。そして、これまで震災とオウムの事件があった1995年を手がかりにしていたが、ここまで書いたように、93年になにか変化があったのではないか(3のつく年に)。もっというなら、92年になにかが終わったと想像できる。そのことで八〇年代が完全に終わったと考えるべきではないか。まだそれを立証できないものの。ただ少なくとも、1993年に僕が岸田戯曲賞を受賞しているけど、ま、いいか、それは、なんかあれだし。さて「一気にゼロ年代に時代を進める」と書いたものの、それを話す前に、あらためて時間をさかのぼり、1972年に話を戻す。1972年、すでに書いたように櫻社は『ぼくらが非情の大河をくだる時』(作・清水邦夫/演出・蜷川幸雄)を上演した。そのラストの有名な台詞を引用しよう。
さて、それから32年後の2004年、まったく種類の異なる劇言語が登場し、私たちを驚かせた。岡田利規君の『三月の五日間』だ。そのラスト近くの台詞を引用。兄 誰だ泣いているのは……風か……いや水の音だ……河だ、河が流れてる……くさい、ひでえ臭いだ……きっとくさった動物の死骸が流れてるんだ、猫やら豚やら人間やら……ああ、なんて汚辱に充ちて、華やかな混乱なんだ……とにかく河岸までいこう。構うもんか、おれはのどがカラカラだ、さ、おれにしっかりつかまるんだ、ふり落とされるな、もし無事に河岸へつけられたらおれたちは舟を出すぞ、たとえ十月の蝶にも似たか弱い舟でも、おれたちは漕ぎ出すんだ……(清水邦夫『ぼくらが非情の大河をくだる時』より)
いったいこの変化はなんなのかと。男優4(観客に)ユッキーって女の人は、「あ、俺、山手線だけど」「あ、私、東横線」ってことで、それじゃ、ってことで、さようなら、ってことで、終わったって話があるんですけど、そのあとで、でもその人はすぐ電車乗らないで、なんかもう少し余韻浸っていたいの渋谷、みたいなことで、今来た道玄坂のほう戻る感じで散歩みたいなことしたんですけど、──(中略)──「それは野糞が信じられないってことじゃなくて、その人、その人、だっていちおー人間なのに動物だと思って自分が見てたんだっていうその数秒があったってことがすごい、人間のことを本気で犬かなんか動物だと思って見てたんだっていうことがあったんだっていうことが信じられなくて、ほんと信じられなくて、信じられないって思って(ズボンのポケットから女性用のリップクリームを出して、唇に塗り、仕舞う)、そう、それで吐いちゃって、トイレ、どこか、お店の入ろうと思ったんだげど間に合わなくて、道で吐いちゃってっていう、それで少しだけ落ち着いて、超急いで駅に向かって、そのときはもう全然、渋谷、普通に戻ってて、でもそれどころじゃなかったっていう、話があって」、
男優4 っていう、そういうことにこれからなるそのコとその相手の男が、三月の5日間の最後の朝に銀行で男が金おろして、っていう、女のコがそれを待っているっていうのを今からやって、それで『三月の5日間』を終わります。(岡田利規『三月の五日間』より)
そして、街区の差異ということで考えると興味深いのは、すでに書いたように、『ぼくらが非情の大河をくだる時』が劇場の外に出て行くとき、そこにあったのは、「新宿」という六〇年代性をまとった街だった。では『三月の五日間』はどうか。地図を見てもらうといいが(新宿もそうですけどね)、『三月の五日間』は「六本木」にある「スーパーデラックス」というクラブで出会った男女が六本木通りを歩き、「渋谷」へ行き、円山町のラブホテルに入る。かなり歩く。そして具体的だ。では、『ぼくらが非情の大河をくだる時』はどうか。死んだ弟を背負った兄は、上記の台詞を叫んで劇場の外へ、新宿の街へ出て行ったあと、やはりかなり歩くはずだと思うが、ではどこに向かったのかよくわからない。このどこに向かったかわかならいという幻想性、抽象性をかつては(ある特別な演劇の時代)、「劇的なるもの」と呼んでいたのではないか。あるいは「詩」と。では『三月の五日間』に「劇的なるもの」や「詩」がないかというとそうは思えない。そこには、質が変化した「劇」や「詩」があると考えられるし、それを背後で支えているのが「土地」だ。六〇年代性をまとった「新宿」であり、どこでもよかった「渋谷」である。というのも、スーパーデラックス(略してスーデラ)を出たあとの二人がホテルに行くのなら、べつに渋谷でなくてもよかったのだし、六本木や赤坂、恵比寿にもラブホはあったはずである。「どこでもよかった渋谷」がその時代性を感じさせる。このふたつの劇言語から、身体性の話をこれまで演劇の授業でしてきたが、いまは文化の問題、その背後にある「街」「土地」のこととして考えたとき、「どこでもよかった渋谷」は意味が大きい。九〇年代の「渋谷系」と言われた時代の「渋谷」ともまた異なる空気が街区に漂っている。そのことをまたあらためて次の機会に考える。というか、なんか、むつかしくなってきた。
■補足。桜井圭介君のツイートにあった、1973年の西武劇場の開館によって、文化的な位相は渋谷に移ったかというと、そうはならず、もっぱら「新宿→原宿」という図式で六〇年代から、七〇年代、八〇年代の変遷があったとするのはなぜなのかということになるが、「西武劇場」は建物の上階にあり、土地との繋がりが薄かったからだ。むしろ、公園通りから階段を降りればすぐ劇場に入ることのできた「ジァンジァン」のほうがずっと、渋谷の土地に根差していた。ほんとかよ。
■あと、文学について書こうと思っていたが時間がなくなった。またの機会に。というか、僕が書こうと思っている小説の話なのですが。
(8:18 May. 19 2014)
5←「2014年5月前半」はこちら