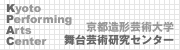Sep. 16 tue. 「今週から働こうと思う」

■突然だが、先週の土曜日にiPhoneを買ってしまった。
■二ヶ月、なにもできなかった鬱憤や、胸骨の痛みに耐える日々の、鬱々とした気分を晴らすためにあとさき考えずに買った。ひところの行列騒ぎはすでに過去になり、いまではどこでも簡単に手にはいる。入院中、いろいろなサイトを調べたり雑誌を読んで情報は仕入れていたのだった。日本語入力が遅いとか、コピーができないとか、従来日本で普及してきた携帯電話の考え方で使おうとすると勝手がちがって戸惑うなどネガティブな情報が流布される一方、支持する者らの評価は高い。どっちを信じていいかわからない。で、実際に使ってみたが、こんなに面白いものもあまりない。
■とはいうものの、iPhoneの端末は高い。HDDが16Gの機種の場合、「八万円」以上になる。これ携帯の値段じゃないだろう。若い人、なかでも学生、高校生は、よほどじゃなければ買うのはむつかしかろう。なぜ高いか使っていればすぐにわかるが、これはつまり、ちょっとしたコンピュータだからだ。掌に載るコンピュータ。ネットに接続できるし、POPサーバーのメールもチェックできる(っていうか、PCメールしか受け取れないか)。し、僕は興味がないがゲームがいろいろできるらしい。で、コンピュータだから、ソフトを入れてゆけばさまざまな用途に使うことができるとはいうものの、それほど、すごいソフトがあるわけではない(ゲームが好きだったらいろいろ楽しめるのではないか)。ただ、現在位置が確認できる地図がいい。日本語入力に関しては、ファームウェアっていうのか、iPhone ソフトウェア 2.1
にすると劇的に改善されるらしいが、買った前日に、「2.1」が公開されており、すぐにアップデートしたので「2.1」以前の日本語入力がどうだったのかわからない。改善されたかどうかもわからない。いまのところ入力は快調である。というか、これまでの携帯電話の入力はあの小さなキーを押さなくちゃならないのに苦労したが、それに比べたらずっと快適に感じる。まあ、先週の土曜日(13日)に使いはじめ、数日しか経っていないのでまだわからないところもある。おいおいわかってゆくだろう。あとソフトバンクの電波状態を心配する声もネットにはあったが、都心ではデパートの地下でも受信でき、このあたりは土地によってちがうと思われる。
■ほかには、本ばかり読んでいた週末だが、いろいろ収穫は多かった。さあ、仕事だ。毎日でも少しずつ歩くようにしており、だいぶ調子も元に戻ってきた。で、きょうは(火曜日)は五反田の病院で診察してもらった。順調に快復している。まだ胸の骨は少し痛いとはいえ、もう大丈夫だ。仕事をしよう。やるべきことは山積。大学の予習など、いろいろあって、「サブカルチャー論」の講義をするようになってからすっかり勉強の傾向が変わってしまい、この五十年くらいの「サブカルチャー的なるもの」について意識的に読むようになった。するとジャズのことも書いたけれど、文化はどこかであらゆるものが通底しており、こういった傾向が出現したからそれがべつのジャンルに影響を与え、といったふうに動いていると思えるし、その背景に経済も関係するが、それが政治へと反響し、それがまた文化に戻ってくると、ぐるっとひとまわりして経済に影響がおよび、ぐるぐる循環していると感じる。サブカルチャーの動向は、時代の空気になってメインカルチャーにも反響する。そこに「時代の空気」が生成される。
■僕はむかしから、マイナーなもの、消えてしまったもの、あるいは、志半ばで死んだ者らに興味を持つことがよくあるが、何人かの人のことがこのところ心に引っかかって仕方がない。だが、マイナーだっただけに資料も乏しく、自分の力で調べないと先へは進めない。とはいうものの、それをすることがいったいなんになるのかと思えることもあるし、人から見たら、ばかに思えるかもしれない。歴史のなかで埋没してしまった者たち。だが、その活動がその後の時代を準備した者。たとえば、ジャズの世界に守安祥太郎という天才ピアニストがいた(多くの人の証言がある)。三十代の前半で自死している。あるいは、トロツキーの著作を精力的に翻訳、紹介していた対馬忠行がいる。やはり自死している。そうした人について調べたところでなんになるかと思えるが、僕にはそうした人や現象に興味を持つもともとの性格があるように思えてならない。敗者へのシンパシー。それは単なるロマンティシズムだろうか。「都市空間論」に関連しては、相馬から教えてもらった『〈都市的なるもの〉の現在』(東京大学出版局)を購入。読む。面白い。ほかには、若林幹夫さんの『都市への/からの視線』(青弓社)。
■そんな読書が続いている。深夜、散歩に出たらものすごく歩いた。手術前、少し坂道をのぼると、肩から、胸のあたりに激痛が走ったがそれがまったくなくなったし、息切れもあまりしなくなった。単なる肩こりだと思っていたのは心臓だったのだな。いま心臓がぐんぐん動いている。どんどんよくなっている。これからばりばり働く。
(11:27 Sep. 17 2008)
Sep. 11 thurs. 「少しずつの回復」
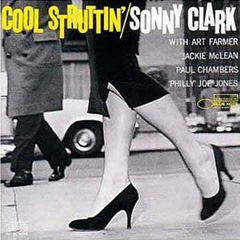
■その後も、退院を祝ってくれるメールをたくさんいただいた。ありがとうございました。リハビリは順調に進んでおり、日ごとに歩く距離を伸ばしているけれど、ときおり胸の骨が、かくっとか音をたてるような気がしひどく不気味だ。咳をすると胸骨を中心に胸部が痛むのは、入院中、痰を切らなくてはいけなかったので何度か経験していたが、怖れていたことが現実になったのは、うっかり、くしゃみをしてしまったからだ。これが痛い。ものすごく痛い。「くしゃみ」には、ただごとならないエネルギーがあって、激痛が胸を襲う。それはそれはすごい。
■下高井戸にある歯科医の予約があるとばかり思いこみ、きょうは出かけたが、予約カードをよく見たら診察は金曜日だった。今週の火曜日、五反田の病院に外来でかかったとき、行くときは心配だったのでタクシーに乗ったが、帰りはゆっくり歩いて山手線で家に戻った。だから大丈夫だろうと思い、下高井戸からも歩いて帰ってきた(行くときはやはり心配でタクシーを使ってしまったが)。ずいぶん楽に歩けるようになった。京王線の下高井戸駅のあるちょっとした駅ビルには、啓文堂書店が入っていて、棚を物色したら、「文藝」の別冊号が「赤塚不二夫」追悼特集だったので手にする。いろいろな人が文章を寄せていたり、かつてのアシスタントの方たちがインタビューに応じているが、ここに、「長谷邦夫」という名前がないことが少し残念だ。
■そして私は、このところ、一九五〇年代の、自分が生まれたころのことを考えることが多い。すると、五〇年代の一側面として、モダンジャズはどうしても切り離せないし、映画のムーブメント、政治的なムーブメント、文学、演劇、美術と、時間軸で時代を把握しようとするとき、モダンジャズはその背後に通底音として流れていた気がするのだった。だからジャズばかり聴いている。あるいは、その時代のジャズについて記された本ばかり読んでいる。それはつまり、時代の気分、というか、それはもちろん(モダンジャズは)都市的な現象だったのだろうし、日本が全般的にそうした気分に支配されていたとは思わないが、先端的なアーティストら(ときとして、思想家たち)によって形成され、牽引された「時代」はきっとあったはずだ(それはどんな時代も変わらないのだし)。そこに興味をもつ。演劇はどうしていたのかと思って調べると、福田善之さんの『長い墓標の列』が五八年、『真田風雲録』が六三年か。だが、歴史に残されなかった「演劇的行為」がきっとあったと想像するのだ。時代のなかで埋もれてしまったが、微かな光源となって、のちの時代を準備したものたち。八〇年代に、ラジカル・ガジベリビンバ・システムは「演劇」としてまったく評価されなかったが(やっていた当事者も、そこで評価されようなんて、考えてもいなかったし)、しかし少なからずその後を準備した一要素だった。ともあれ、五〇年代のモダンジャズが準備した「身体」があったからこそ生まれた潮流は五〇年代のなかでひっそりと育てられ次の時代へ飛翔したと思える。それが、いまの興味。
■からだが少しずつ恢復してきたので、なにかと意欲が湧いているのである。そろそろ仕事を再開しなければと思うし、御恩になった方々、迷惑をかけた人たちに、お礼をしてもしても、したりない。そして気がつけば、9・11。あれから七年。世界はなにが変化しているのだろう。総裁選、まったく興味なし。石破さんが総理になれば、ちょっとは興味もわくのに。だって、面白いからさ、石破さん。歳も同じだし。
(3:27 Sep. 12 2008)
Sep. 7 sun. 「少しずつの回復」
■退院して、少し落ちついたものの、まだ胸の骨のあたりが痛い。リハビリのために家の近くをゆっくり歩くが、痛みですぐに立ち止まる。また歩く。また休む。この繰り返しで少しずつ体調を回復させてゆかなくてはならないのだな。
■以前、『ニュータウン入口』芸術劇場版の感想を送ってくれた奈良のGさんから、Gさんがフィールドワークした「太田省吾の稽古場」に関する記録をファイルにして送ってもらったのは入院をした当初のころだ。そして、京都造形芸術大学の舞台芸術センターが刊行している『舞台芸術』の今年の春に出た号では、太田さんの特集が組まれており、どちらも刺激的なエクリチュール群で、太田さんの肉声を感じさせてくれるGさんから送っていただいた資料(でも、どう読むと、この資料はもっとも生きてくるのか考えていたが)だし、また新しい演劇人によって見つめられる太田省吾という人の姿は、またべつのことを考えさせてくれる。そういった刺激を受けつつ、焦燥感がないといったらうそになる。なにもしていない自分に焦るのだ。舞台は遠い。次になにをしたらいいのか考えあぐねている。
■九月になっても、まだ外は暑い。そして奇妙な豪雨が突然やってくるのは、熱帯雨林のスコールのようだ。この国は亜熱帯になってしまったのかもしれない。それから、その後、たくさんの方から、退院を祝ってくれるメールをいただきました。ありがとう。少しずつ復活してゆきます。驚くほどの、人から迷惑だと言われるほどの、復活をしたいと思っています。
(9:43 Sep. 8 2008)
Sep. 5 fri. 「五反田から遠く離れて」



■写真は、私が入院していた「NTT東日本関東病院」である。五反田にある。かつては「逓信病院」という名前だった。以前も書いたと思うけれど、頼めば各病室に「Bフレッツ」をひいてくれるというネット環境の充実は、NTTならではだ。何週間か前、遊園地再生事業団メンバーの上村と、僕の舞台にもいくつか出てくれた鈴木将一郎、鈴木謙一、笠木らが見舞いに来てくれたとき、上村は、関東病院のマークを見て、「NTTに似ている」と言っていたそうだ。鈴木らは冗談で言っているのだと思って話を合わせていたが、上村は本気だった。よく見れば「NTT東日本」と書いてあったと思うんだよ。
■ここの「心臓血管外科」の手術には定評があり、有能な医師がいてこれまでも数多くの実積を残しているから、まったく不安なく手術を任せられた。医師たちはほとんど休むことなく働き続けている。すごかった。朝八時過ぎに回診してから、そのあと手術し、手術を終えるとまた夜の回診に来る。退院したあと、外来でまた、ここに来るが、外来の日程と時間を指定するとき、「小さな手術がちょこちょこ入っているから、そのあいまに外来で診るから」と言っていた。忙しいな。すごいな。
■退院をひかえ、四日はなにもすることがないまま、ぼーっとしていた。検査もないし、医師の検診が一日に二度あるけれど、それほどたいしたことではなく、足の傷を見て消毒するだけだ。治りかけの傷がまだ開いている。なぜ、こんなことで三日も退院が延びたか疑問だが、それでもいよいよ退院になった。すると、その前日は遠足にでもゆくような気分になって、なかなか寝つかれない。寝るのがもったいないような気になっていた。五日に退院。天気がよかった。晴れ晴れとした気分になった。家に戻ると、アマゾンに注文してあった荷物が大量に届いていた。本とDVDと、そのほか。午後、少し散歩。胸の骨は痛いが、歩くのはそれほど苦痛ではないので、予定より多めに歩く。ときどき休んでは、心臓がよく動いているのを感じながら。からだ中に血液がしっかり流れているのを感じながら。
■その後、さらに「釣り」のことを考えていた。希望としては川がいい。船に乗って釣りをするのはなにかいやなのだ。「川」についてさらに調べていると、「釣り」というより、「川」そのものに魅了される。それで記憶を遡ると、一九七五年に東京に出てきたあと、二年ほど東京での生活があり、そのあいだいろいろあって、病気にもなったし、精神的にも疲弊し、大学を休学し七七年にいったん掛川に帰った。そのころ、東京に戻らず掛川でなにかできないか考えていたのをいまごろになって思い出した。政治的な運動に疲弊し、掛川でゆっくり考えていると、この土地でなにかできるんじゃないかと思わせてくれたものが、ソローの『森の生活』だったり、『ホール・アース・カタログ』の背後に流れている思想だったように思える。
■だから、なぜいま自分が、こんだけどっぷり東京の生活に溶けこんでいるのかよくわからない。まあ、思想に影響されたといっても、中学から高校、それから大学に入ってという、ほんの五年ほど、信じている思想があっても、その五年間なんていまになってみれば短い。たった五年でなにがわかっていただろう。だが、若い時の時間は濃密だ。基本的に、現状に存在する社会のシステムを否定するのにかわりはなかったが、しかしその思想の表現の仕方が、大学を休学して掛川に戻ってから大きく変わった。掛川でなにかできると思っていた。小さなところから社会は変革できると考えていた。まだそのころの掛川の街は小さかった。どこに行くにもクルマじゃなきゃだめになったのは、地方の生活圏が大きくなったからだ。なにものかが街を大きくしたからだ。かつては歩いてすぐの場所に商店があって、小さな土地で人は生活していたし、そうした生活に大きな支障があったとは思えない。資本はそれだけでは動かないから、地方の空間を変容させ、資本を活性化させようとするから、いまでは誰もが、地方ではクルマがないと生活できない、という言葉をあたりまえに感じている。けれど、「地方ではクルマがないと生活できない」はクルマを必需品にさせようとする資本の企みが生んだ言葉だ。というか、資本主義は、無自覚のうちにそう発展する。そのようにしか生きてゆくことができない。
■問題なのは、いまある経済システムを越えるような、またべつのシステムが生み出されないことだ。資本主義はよくできている。よくできたシステムに乗っかって人は、安易に、自分たちにとってもっとも大事なものを手放すことになったから、自然は果てしなく収奪されてゆく。自然のなかには「人」そのものもあり、人間と、人間の労働が疎外されるのは、『経哲草稿』で若き日のマルクスが語ったのとあまり変わっていない。二ヶ月にわたる入院の、短くはない時間のなかで、それはまったくなにもできないような時間だったから、忘れていたことをいくつも思い出した。これからのことをゆっくり考えた。もちろん手術は苦しかったし、傷はいまでも痛いが、こうした時間がなければ、ふと立ち止まるように考えることもなかったにちがいない。夏が入院生活で終わってしまったけれど、もしかしたら、そんな時間を持てたことに意味があったのかもしれない。
(10:57 Sep. 6 2008)
Sep. 3 wed. 「血圧が低い」

■退院は五日になった。ようやくこんどこそきまりだ。長かった。丸二ヶ月だ。疲れた。毎日、なんど血圧を測ったことか。朝、六時過ぎにまず最初の検温と血圧測定があり、いくら眠くたっておかまいなしに看護師さんたちはやってくる。眠いけれどからだを起し体重も計りに行く。きびしかった。その規則正しい生活、ある意味、その不自由さにストレスがたまりそうだった。何度も退院がのびのびになり、そのたび意気消沈していたのだ。精神的にかなり疲弊した。手術より、そのときのダメージのほうがきつかった気さえする。
■これもひとつの経験か。病院の奇妙な時間のなかで、さまざまなことを考えていた。ゆったりとしたその時間がもたらすものはなんだろう。とはいっても、血圧を計るのは忙しかったのだ。しかも、なぜか血圧がずっと低かったし。上が、八〇台しかなかったんだよ。高いよりはいいんだろうけどさ、動脈硬化にくわえて、これで高血圧だったら、脳がね、危ないってことだろうし、あと糖尿も怖いが、そういったいちいちが「老化」ってことであって、いやになる。
■久しぶりに漫画を読んだのは、その帯にあった次のコピーにひかれたからだ。いましろたかし『盆堀さん』より。
およそ漫画の主人公たりえない人間たちが、ほぼまったく活躍せずに終わる世界。
これ、相当いいな。しかも、『盆堀さん』は、まさにその通りの作品になっているからきわめて面白い。たしかに「ほぼまったく活躍しない」のだ。病院はけっこうドラマティックである。なかでも、心臓血管外科、脳外科となると、突然の発症で緊急手術が多いし、患者だけではなく、家族が集まって劇的に事態が展開することはある。するとそこに、ちょっとしたことでも「劇(=ドラマ)」は発生するだろう。上のコピーを、「およそドラマの主人公たりえない人間たちが、ほぼまったく活躍せずに終わる世界」と書き換えれば演劇の話になる。では、「病院」という「場」は、必然的に劇を発生させてしまうかといえば、そうでもなく、それは場に向ける視線によって決まるので、同じ「場」のどこを見ているかによって、表現される「場」の色合いも変わる。
ただ、こうした「劇性」の低さ、あるいは、「劇的なものからいかに遠ざかるか」について、コミックも、演劇も、あるいは小説も、これまで繰り返し試みをしてきたのではないか。たとえば、「演劇」は「劇的なもの」を疑い、劇言語そのものを、いかに過去の「演劇のことば」から遠ざかるか、九〇年代の半ばから盛んに試行されてきた(ほかの分野も同様かもしれない)。
いましろたかしが描く世界が、またべつの姿をしているのは、その描画の奇妙なリアリティだ。けっして細密ではないし、うまいと思えない描画が、それゆえに醸し出す人物の実在感は、理想とされるべき「漫画の主人公像」とはかけはなれ、しかも、どうでもいいような内面を抱えて思考し、行為する。その思考と行為が構成するのは、「ほぼまったく活躍せずに終わる世界」だ。だとしたらかなり「実験作」のようでありながら、出現する作品の感触は確実に「ドラマ」である。人の愚かさが客観的に描かれた「喜劇」である。
あるいは、きのうのノートに「釣り」について書いたあとから、この『盆堀さん』を読んだんだけど、偶然にも釣り好きの登場人物が出てくるばかりか、作者のいましろさんが、そもそも釣り好きだった。これもなにかの縁か。「釣り」のほうへとなにかが動いている。
■とはいっても、からだの調子もあるし、たとえ、実際に「釣り」に出かけるとしても、まだ先になるだろう。九月は、胸骨をしっかり治すことが肝心だ。まだ痛いんだよ。リハビリをかねて軽い運動もしよう。そして十月までにやっておかなくちゃならないこと、ほんとだったら夏休みにすべきだった大学の準備、なかでも「都市空間論」のまとめをしなくては。読むべき本が山のようにある。
(9:11 Sep. 4 2008)
Sep. 2 tue. 「病院の時間」

■写真は、入院している病院の吹き抜けである。でかい。
■「新潮」のM君とKさんが見舞いに来てくれた。直接的にこの手術や闘病について書くというわけではなく、これをきっかけに、また新たな創作の手がかりになればと励ましてくれた。そう言われてみると、いま時間について、「感じ方」が日常とは異なるものになっており、まるで子どものころ、川へ遊びに出かけ、水の音をいつまでも耳にしていたときのような、そうしているだけで、ほかになにもしないでも困らなかったときのような奇妙な感覚になっている。子どものころに遊んだ川は信じられないほどきれいだったし、ほかに物音もせず、水の音は心地よくあたりの森に響いたものだった。
■そんなことを考えていたら、中学生のころに読んだソローの『森の生活』のことを思い出した。中学生の僕にはまだむつかしく感じるところもあったが、書物の全体から湧き上がるような匂いは、あとになって知ったが、その時代のある傾向を持った「空気」だ。『森の生活』は六〇年代から七〇年代にかけて、自然志向派というべきか、もっと端的にヒッピーと表現すべきか、その世代の人たちの参照先のひとつだった。病院のなかにコンビニがあって、「BRUTUS」の最新号があったので手にすると「釣り」が特集されていた。べつに、「釣り」をやろうとは思わないが、ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』を持ちだすべくもなく、「フィッシング」の思想の一面に、やはり、自然志向というか、「森の生活」的ななにかがある。それで『フライフィッシング教書──初心者から上級者までの戦略と詐術のために』という本をネットで発見し、すぐに注文した。繰り返すようだが、べつに釣りをするつもりはないのだ。子どものころから、釣りにはいい記憶がちっともない。ただ、フィッシングの本が読みたかった。釣りを含めた「森の生活」的な本が読みたいから、今泉吉晴さんという人が新たに翻訳して評判もいい、『森の生活』(小学館・二〇〇四年)をアマゾンで注文したのである。これらはみな、「サブカルチャー論」に属する事柄である。べつに趣味的ななにかというわけではなく。
■で、「新潮」のM君とKさんが見舞いに来てくれたから思い出したわけではないが、小説『返却』に書いた、ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』のあの独特な、章立てというか、エピソードが重ねられてゆく手法は、まあ、よく理解できないリズムで刻まれているが、「釣り」をする行為を考えればその不可解さが解けるかもしれないと思った。ブローティガンの文体、と僕が認識している日本語は、どうしたって翻訳に決定づけられている。構造や構成を考えると、そこに「釣り」があるように思えてならない。だから僕には、『アメリカの鱒釣り』がうまく理解できなかったのではいだろうか。なにしろ僕には、子どものころから「釣り」にいい記憶がまったくないのだ。
■そんなことを考え、つらつら書いているうちに、だんだん「釣り」をしに出かけたい気分になってくるから人間、わからないものである。繰り返すが、「釣り」にはいい記憶がないし、先述した「BRUTUS」には開高健の釣りについての記事があって、読むといよいよ「釣り」にいい印象を持てないが、けれどなにかが魅了する。
■夕方、映画を作っている岸と、『ニュータウン入口』にも出た杉浦さんが見舞いに来てくれた。聞けば、杉浦さんもからだの調子が悪いという。心臓じゃないかと心配していた。岸はぜんぜん、健康そうだ。そして、病院生活はまだまだつづき、奇妙な時間の流れのなかで、「釣り」のことを考え、「森の生活」について考え、まずなにからはじめたらいいか迷っている。
(13:16 Sep. 3 2008)
Sep. 1 mon. 「夏は終わったけれど」

■もう九月だ。夏は完全に終わってしまった。なんだったんだよ、夏。
■入院してから二ヶ月になろうとしている。こんなことになるとは思いもよらなかった。数日、チェルフィッチュの山縣太一君をはじめ、いろいろな人が病院を見舞ってくれた。それから、元筑摩書房の打越さんからはハガキとお見舞いが送られてきたが、ハガキに「私はこの夏、マジックとチアリーディングに明け暮れました」とあって、どう理解していいかわからなかった。
■大阪のM君からはメール。最近、「素人の乱」の松本哉君と友だちになったという。それで、松本君、それからかつて京都にいていまは静岡で働いているK君と三人で会いに来たいという旨のメールをもらった。うまくいって四日に退院するとしても、まだ胸骨が痛いので外で人に会うのが不安である。松本君とは、ほんとは阿佐ヶ谷のロフトでイヴェントをやる予定でもあったし、ぜひとも会いたい。M君、K君は、遠くにいるのでなかなか会う機会もないから、やはり会っておきたい。ただ骨なんだよ、問題は。だいたい、そのイヴェントにこんなからだの状態になってしまって参加できないのが悔しい。面白そうなことがあったらどこにでも行きたいが、からだがだめだと、動けないんだから腹立たしいよ。ロフトの人にも迷惑をかけたし。きちんと治さなくちゃな。楽しいことがなにもできない。
■夜、主治医のN先生から手術の経過と、今後の治療について話をうかがった。胸骨のレントゲンを見せてもらったが細いワイヤで縛りつけてある。元のようにきっちり接合するには二ヶ月ぐらいかかるらしい。クルマの運転は控えたほうがいいとか、いくつか注意されたが、胸はしっかりカヴァーしつつも軽めの運動は続けなくちゃいけない。軽めの運動だから、チアリーディングは無理だと思う。で、根本的に考えると動脈硬化だから、食事を制限したり、煙草をやめたり、ストレスをためないなど、日常を全面的に更新しなくちゃならない。なにしろ、医師によれば、「もう心臓はこれ以上、よくなりません」だ。だからよくない心臓を保守するための生活である。煙草はやめ、塩分の少ない食事をするのはいいとして、ストレスをためた記憶がこれまでないものの、なんかあったんだろうし、それを解消するとき僕の場合、煙草が大きな意味を持っていた。だとしたら今後はどうしたものか。そうはいっても、やっぱりチアリーディングじゃないと思うんだよ。
■それにしても、心臓血管外科の医師たちはものすごく働いている。僕が入院してから、部長のT先生や、主治医のN先生とは毎日会っているし、朝の八時過ぎ、夕方、必ず回診に来る。そのあいだ、外来があり、手術があったり僕がICUにいるあいだはN先生がしょっちゅう様子を見に来てくれたし、いつ休んでいるのかぜんぜんわからない。不思議だ。あと、よく働いたというなら、自分の心臓だ。虚血性の心臓病というのは、心臓の筋肉の一部が死んでいることだと説明を受けた。ある部分が死んでいたらそこを切り取って縫い合わせる手術も今回はする予定だった。そこまで死んでいないのでそれはしなかったが、まばらに死んでいる部分が存在するという。だから、「心臓はこれ以上、よくなりません」になる。心臓にいろいろ負担をかけてきた長い時間の結果だ。よく働いていたのだ。それでもうこれ以上は無理だというので、瀕死の心臓が悲鳴をあげ、肺に水がたまった。よくがんばった。これからは大事にしながら生きてゆこうと思う。
■さて、退院まで、あとわずかだ。ようやく仕事の続きができる。やらなくちゃいけないこと、あるいは、読んでおきたいもの、あらためて資料にあたって調べたいこと、考えることがいくらでもある。いま、また、新しい興味が生まれた。どんなに愚鈍であろうと、反時代的であろうと、興味のあることしかしない。そのほうがストレスもたまらないし、心臓にもいいからな。そしてそうした興味への情熱が、創作や、大学の授業に反映すればいい。
(10:15 Sep. 2 2008)
8←「二〇〇八年八月」はこちら