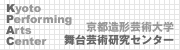Jun. 26 fri. 「金曜日の夜、幸福な気分になって」


■またあわただしい一週間だった。だけど、金曜日の六限の授業を終えて研究室で学生たちと夜11時過ぎまで話をしていたらとても幸福な気分になった。そのとき学生にも話したが、こうして学生と話ができたり、授業をしたりと、大学の生活はいろいろためにもなるし、楽しい。一方、自分は作家だ。創作しなければという思いをより強くしつつも、けれど大学の授業を準備すること、進行することの愉楽があり、そのあいだで葛藤しているのだ。そんなふうには見えないかもしれないが葛藤してるんだよこのやろう。どっちも好きなんだから困る。
■しかも私は最近、アフタートーカーになってきた。木曜日(25日)は、ミクニヤナイハラプロジェクト『五人姉妹』のアフタートークに参加。矢内原美邦、白水社のW君と話す。その日は夕方、大学の授業(「戯曲を読む」)があったのでアフタートークの時間までに吉祥寺シアターに向かい舞台は前日のゲネを観た。空間を構成する色や装置、高橋君の映像、中原昌也君の音楽によるダンスが生み出す造形はかっこいいとしかいいようがないが、一方で、われわれは、この舞台作品を「演劇」という文脈で見なければいけないと何者か(=演劇の制度?)に強いられる。というのも、矢内原美邦が創作するとき「ダンス」として発表されるもの以外、「演劇」だと思いこまされるからだし、矢内原の固有性だけではなく、パフォーミングアーツのシステムはたいていそういうことになっている。そうではない見方について考えていた。まあ、「せりふ」と「ドラマ」は戯曲を読めばいい。だから、せりふが聞き取れないとか(言葉はここで、いい意味、音楽における楽器の音のようにあった)、話がどうなっているのかほとんど理解できない(わたしはほとんどの舞台においてそうなんだけど)、といったことは気にならなかったものの、しかし、それでもパフォーマーの一部の身体はそれを「言葉ではないなにものか」によって伝える。むしろそれが強く印象に残った。その「からだ」とはなんであるのか。まあ、具体的にいうと三坂なんだけど、いままで見た三坂のなかでいちばんよかった、というのは、空間が生み出す造形の抽象性のなか、わけのわからないものを強く発しているのを感じ抽象性からたくまずしてはみだしてしまう「過剰」があったからだ。それが矢内原の演出とよく合っていたとしか言いようがない。繰り返すがたくまずして。もう一度やってみろといっても再現できない気がする。だからなおさら、「そうではない見方」を考えざるをえない。演劇を観るのとはまた異なる態度。それはつまり創ることにつながる。ジョン・ケージは自分たちの音楽について次のように書いた。
現代音楽に用心深く異議を唱える人たちは、もちろん反革命というやり方であらゆることを試みるだろう。演奏家たちは、われわれが音楽をつくっていることを認めようとはしないだろうし、われわれが表面的な効果に関心を持っているか、あるいはせいぜい東洋的な音楽や未開の音楽を模倣しているにすぎないと言うだろう。新しく独創的な音は「ノイズ」というレッテルを貼られるだろう。しかし、どんな批判にたいしても、われわれは一致して、音楽の禁則というわずらわしい頭でっかちの構造にはとらわれずに、仕事を進め、聴き、音とリズムという素材で音楽をつくり続けることによって、答えていかなくてはならない。(ジョン・ケージ、柿沼敏江訳『サイレンス』より)
だからこれを演劇に置き換えると、「演劇の禁則というわずらわしい頭でっかちの構造にはとらわれずに、仕事を進め、観、身体と言葉という素材で演劇をつくり続ける」ことによって、演劇を取り巻くさまざまな「もの」や「こと」に応答していかなくてはということになる。正直『五人姉妹』を全面的に肯定するわけにはいかないものの、いろいろ考えるきっかけになった。とても刺激された。で、俺はどうしようかなと、次の舞台について思いをめぐらしていた。
■いま、これを書いているのは、土曜日(6月27日)の午前中ですが久しぶりにこの週末は外での仕事がない。きのう学生とゆっくり話ができたこと、この気持ちのいい夏のはじめの朝の空気を感じることといい、きわめて幸福な気分になっている。でもまたすぐに仕事だ。文庫本(『資本論も読む』)と、河出書房から刊行される予定の、横光利一『機械』を12年近くにわたって読み続けたあのどうかと思うような連載をまとめる単行本のための原稿だ。本が出るのは楽しみだ。この12年近くにわたって書き続けたという、この理解できない冗談を、どうかまとめて読んで味わっていただければと思う。
■夏だなあ。一年でいちばん好きな七月はすぐそこだ。去年はずっと病院で過ごした七月。汗をだらだら流そう。夏は修行の季節である。
(9:11 Jun. 27 2009)
Jun. 22 mon. 「ほんとうに更新が一週間ごとになってきた」


■最初に宣伝である。ニブロールの新作公演『五人姉妹』のアフタートークに出ます。6月25日(木)。詳しくはこちらへ。
■あるいは、ベケット・カフェで上演された『あたしじゃないし、』(サミュエル・ベケット作/岡室美奈子訳)について僕が発言したことに対し、演出の川口さんが、ベケット・カフェのブログで回答してくれた。それに対しても応じなくてはならないと思いつつ、なかなか言葉にするのはむつかしい。
■この日曜日は渋谷のO-nestというスペースで批評家の佐々木敦さんが主宰する雑誌「エクス・ポ」復刊のイヴェントに出演した。佐々木さんと、大谷能生君と話をする。なにより印象に残ったのは、大谷君は人が話しているとき最後まで話を聞かない人だったことだ。おい、少し落ちつけと、最後まで人の話を聞けと……話しづらいなあ……まあ、それにしても大谷君のものすごい博覧強記ぶりには驚かされる。
■O-nestは、いまのユーロスペースの少し先、かつては渋谷のラブホ街でしかなかった土地(円山町)にある。もう20年以上前、その先の松濤に住んでいたわけですけれど、円山町界隈にもラブホだけではなく住宅もあって、秋になるとお祭りをしていた。子ども神輿が町内を練り歩いていたけれどまだ人があまり行き来しなかった時代の円山町はただのラブホ街だったから、どうなんだろうと、子ども神輿がそんなところを練り歩いていいのか心配になったというか、でも面白かった。しかしあたりの様相はすっかり変わってしまった。わけのわからない若者でにぎわっていた。ライブハウスがあり、クラブがあり、そして相変わらずラブホ。すげえなそれにしても。動物化する都市。欲望だけがぎらぎら輝いている都市。静かな場所に行きたい気分にもなるけれどこれもまた面白いといえば面白い。
■イヴェントには早稲田の学生たちが何人も来てくれた。あるいは「新潮」編集部のKさん。ありがたかった。そうだ、相対性理論のヴォーカルの人に挨拶されたのだった。笠木がPVに出ているという話を前から聞いていたが「サブカルチャー論」の授業でそのPVを流さなくてはと、いまこれを流さずにどうするという感じで。
■もう、あまり書くことがない。あとは大学の授業のことばかりだ。
■本日は、朝の10時40分から「社会演劇学」の授業の担当の日だった。「エクス・ポ」のイヴェントが終わって家に戻ってから授業の準備。眠らずに大学へ。平田オリザの「現代口語演劇」の評価をめぐってこの授業のコーディネイトをする岡室さんと議論。ところが学生の多くはなんの話をしているか、なにを問題にしているか、うまく理解できていなかったとおぼしい。
■あとで学生に手を挙げてもらったが、青年団を観たことのある者が数人、チェルフィッチュを観たことのある者も数人、では、「劇団四季は?」と質問すると半数以上が手を挙げた。「現代口語演劇」なんてまったく関係ないところで「彼/彼女」らは芝居を観ている。ま、そうだよな、世の趨勢はそのほうが圧倒的に大きいに決まっており、じゃなければあんなに劇団四季の観客動員が多いはずがない。ただ、知らないという者らに対し、そうではない演劇の文脈もあると話すことも必要だ。知らなかった者が刺激を受けまた新しい観客になるかもしれない。そのための教育。だからなおさら、説得力を持った話ができないといけなかったんだ。
■で、最初、少しワークショップ的に、学生を数人前に呼んで、簡単に演技すること、演技といえば大げさだが、簡単になにかからだを動かすことをさせようと計画していたことを実行すればよかったかな。すると、一気に、演技というものの「嘘くささ」とか、「からだはなぜ固いか」とか、「固くてなにが悪い」とか、僕がこれまでやってきたことがわかったはずだ。
■このところ授業が終わると、去年がそうだったように数人の学生が研究室に来るようになって、いろいろ話をするのが楽しいし、心がなごむ。だんだんメンバーが固定されてきたけれど、なかにあきらかにもぐりの商学部の学生がいる。僕が担当するほとんどの授業にもぐっている。とても頼もしいけれど、まあ、僕の授業に興味を持ち熱心に話を聞いてくれるのは、どこかほかの学生とは異なるだろうから、劇団四季は観ないだろう。とはいってもわたしはけっして、劇団四季を否定しているわけではないのだ。否定したってしょうがないじゃないか。
■このところ、ノートの更新が一週間間隔になってしまった。なぜだろう。去年はそんなこともなかったはずだが今年はやけにせわしない。落ちついて本も読めない危機的状況。本が読めないってそれほんとうに危機だ。
(7:13 Jun. 23 2009)
Jun. 15 mon. 「原稿の催促もされる月曜日だ」


■このところ、ウイークデイは大学とその準備、週末はなにかと用事があって埋まる、というわけで休むひまがない。
■土曜日(13日)は、放送作家の高橋洋二が本を出し、その刊行記念のトークライブが新宿のジュンク堂書店であった。僕はゲストとして呼ばれた。同じく放送作家の鮫肌文殊君も客席に来ており、久しぶりに笑いのプロたちと話をした気分になった。その「笑いのプロ」は、「プロの演者」ではなく「笑いが好きな素人」でもなく、ある特別な人たちだ。二人とも適確に現在の笑いを分析してゆくが、しかし、笑いが好きな批評家ではないので、ただ分析するだけではなく、その話で笑える点が重要なポイントだ。久しぶりだったなこういうのも。
■いみじくもトークライブの最中に高橋が僕に質問する。いま高橋たちが仕事をしている「現場」から離れて、また異なる場所で仕事を僕ははじめたが、かつてのような、たとえば、僕が「1」を提案すると「2」を畳み込んで「1」の笑いを膨らませるような、そうした人間が、僕の周囲にいなくなったのではないかと高橋は言う。高橋にしろ、いまは映画監督になっている三木聡にしろ、突出した才能だったから、こちらが何か出せばすぐに跳ね返ってきた。しかもそれがほんとうにばかばかしいし笑えた。ほかにもそうした才能が多くいた。いまは高橋が言うように、たしかにいないけれど、それは僕の変化でもある。あのころと変わったのは周囲の環境の変化というより、僕が変わったということの、その反映ではないか。
■それにしても驚いたのは、高橋の本の担当者である国書刊行会のT君だ。14歳のとき大阪で「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」の最後の作品を観たという。トークライブを終えて、新宿の飲み屋に移動。白水社のW君や、高橋の奥さん、鮫肌君らと、かなり長話。面白かった。そういえば、鮫肌君は、あのころ僕が書いた手書きの原稿をスタジオで拾って家に持ち帰りいまでも保管しているという。けっこうそういうやつがいるという噂を聞く。迷惑な話である。
■日曜日(14日)は、中野にある「中野テルプシコール」という劇場で、「ベケット・カフェ vol.2」を観に行った。ベケットの作品を新たに翻訳し直し上演する試みの劇場。上演されたのは、先にも書いたけれど、『幽霊三重奏 テレビのための劇』と、『あたしじゃないし、』。いろいろ考えた。まだ言葉が整理されていないのに、上演後のアフタートークでまとまらぬ発言をして、あとで後悔した。まだうまくまとまらないので、おいおい書いてゆくことにしよう。ともあれ、早稲田の岡室さんによる『あたしじゃないし、』の新しい訳は、そのタイトルが示すように(原題は「Not I.」これまでは『わたしじゃない』と訳されていた)きわめて現在性の漂う言葉によって構成されている。言葉とからだにある齟齬を、僕は疑問に思った。しかし、だからといって、ごくあたりまえに、いわゆる「リアル」に発話するということではないはずだ。だとしたらどんな方法があるかについて、もっと考える余地はあったというより、じつは、ここにチャンスがあったと思えてならなかった。とはいっても、困難な課題だ。なにしろ、「Not I.」にはこういった制約がベケットによって指定されている。
■アフタートークは、演出家、俳優、翻訳家ら(僕の授業の手伝いをしてくれる二人のK君もいる)が劇場の床に腰を下ろして、観客と一緒に、車座になって話すような形態だったのがすごくよかった。なにしろ、距離が近いし、話をするというその姿勢が(なかには壁により掛かってだらしない格好をしている者もいたりと)、よくあるアフタートークとは感触の異なるものにしていた。
■「ベケット・カフェ」という試みもいいな。そこに僕は、「小さなメディアとしての劇場」を再認識させられた思いがしたのです。「なにかを試みること」「考えること」「対話する場」としての劇場であり、空間だ。アゴラ劇場で、僕の『14歳の国』を上演してもらい、終演後、その場で急遽アフタートークがはじまったときに感じた「いいもの」とはきっとそのことだったのだ。来年の十月、遊園地再生事業団は久しぶりの公演を「座・高円寺」でやる。あの空間を、「小さなメディアとしての劇場」にするために、なにかできることはないだろうか。ちょっと、考えたんだけど、上演時間より、アフタートーク、ポストトークのほうが長い舞台があり、観客と対話する場がたっぷりあるっていうのもいいじゃないか。でも、それ、いつものプレ公演かな。リーディングは戯曲の途中まで(約25分)、あとは、お客さんにビールでも飲んでもらって、トークと対話があるっていうのはどうだ。俺はしゃべるよ。とことんしゃべるね。二時間はしゃべる。
■さて、「笑い」「演劇」と話が続き、するとどうしたって、ここで「90年代サブカル」について話を進めてゆこうと思うし、先に引用した「ある有名な団体に所属するKさんのメール」の続きを紹介し、さらにそれへコメントしたいが、あまり時間がない。
なかなか自分が青春を生きた時代を客観的に振り返るというのは難しく、宮沢さんが90年代をどうおとらえになるか、とても楽しみです。/電グルの卓球がかつてやっていた人生(引用者註:「人生」は「電気グルーブ」の前身)は、イギリスのスロッビング・グリッスルの影響を感じました。電子音楽ということ、カットアップやコラージュの使用、そしてパロディ的な俯瞰する意地悪な笑いと社会への悪意。電グルは表面を快楽でおおいましたが、底にはいまもそうしたものがありますよね。/セカンド・サマー・オブ・ラブは一回り先輩たちの歴史でした。僕らには、60年代を反復しようというような使命感はなかったです。ゴアやプーリーでもオリジナル・ヒッピーたちとは一線を画していました。僕はといえば、やがてインドの仲間たちと別れて、一人で紛争地へ通うようになりました。パレスチナ、ボスニア、アルバニア、チベット、アフガニスタン等々へ、政治状況をリサーチし、言葉を習得し、ツテをたどって入り込むのです。もちろん政治的興味がありましたが、いまかんがみるに青山さんにとっての修行と同じような、身体的なものをギリギリまで突き詰めていく動機があったようにも思います。2004年に香田さんがイラクで殺され、それへの"自己責任"バッシングが起き、何かが終わったように感じました。/青山さんや卓球、ねこぢるが体現した快楽と悪趣味、社会と身体のコントラスト。そこで取り戻すべき遺産はなんなのか。気になります!
ただ、このKさんの言葉を読むと、「九〇年代」の一側面として、「快楽志向」と同時に、青山正明がしばしば冗談のあいまに書いた「修行」における「身体への意志」が「時代の心性」としてあったように思える。その態度はきわめてストイックな印象だ。「オウム」と結びつく思想性は時代の気分として漂っていたのではないか。精神世界への接近、身体から発した根源的な意識の変容への能動、そうしたものらを動かしている強い契機はどうしたって思想的だが、Kさんが「60年代を反復しようというような使命感はなかった」と書くとき、そこには世代として、あたりまえのこととして、そうした思想に接近していった──いや、もちろんある限定された層だったかもしれないが──それがごく普通の心性として自分を取り巻いていたと考えたほうが自然ではないか。思想は分岐する。「快楽志向」と「身体への意志」へ。だが、それはごく近い位置にあったからこそ(表裏一体となって)青山正明という人物がそれを表象した。
拙著「ノイズ文化論」でしきりに書いた「九五年の切断」のことを考えたとき、どうしたってオウムについて、オウムという教団や、その宗教的な理念というより、現象したもの(テレビでの報道、サリン事件の波紋をはじめ、あらゆること)すべてを、あらためて考えることは必要だろう。なぜ「オウム」は生まれてしまったのかだ。なぜ、あのときだったのか。あの年だったのか。
九〇年代はいつからはじまったのだろう。それがはっきりしないと「90年代サブカル」も曖昧なままだ。一説によれば一九九三年だという。だとしたら、なんとなく腑に落ちることは多い。「90年代サブカル」を考えるにあたり、まずは資料にあたってそのことをはっきりさせることからはじようと思うが、僕の個人的なことを書かせてもらえれば、先に書いた高橋たちのいる現場から離れて、演劇のフィールドに僕がほとんど移行したのが、まさに九三年のことだった。
(5:14 Jun. 16 2009)
Jun. 7 sun. 「また更新が一週間できなかった」 ver.2


■「90年代サブカル」について少し書き直しました。
■あれはいつのことになるか、以前、「ベケット・カフェ」のアフタートークに呼ばれた。その第二回目の公演が今週末にある。
■「サブカルチャー論」のTAをしてくれる早稲田の院生のK君も翻訳に関わっているのが、『幽霊三重奏 テレビのための劇』だけど(当然ながら、作・ベケット)、その演出をするのは、僕の舞台の手伝いもしてくれたことがある鈴木君ではないか。さらに、早稲田の岡室さんが翻訳した『あたしじゃないし』の上演もある。二本立て。僕は14日に観に行く予定。
■また、佐伯隆幸さんはいらっしゃるのだろうか。また佐伯さんにつかまってしまうのだろうか。佐伯さん、なにか質問しても、答えてくれているのかと思うと、結局、自分の言いたいことをえんえん話されてしまうのだ。それはそれで面白いといえば、面白いが、佐藤信さんといい、佐伯さんといい、みんな話しだしたら止まらない。この人たちのエネルギーはどうなっているのだ。
■ところで、その名を聞けば誰でも知っているにちがいない、ある有名な「団体」に勤めているKさんからメールをもらった。以前、Kさんとは仕事をしたことがある。僕がこのところ、「90年代サブカル」について書いていることについて。彼が体験したことなど、いろいろ教えてくれたが、その話が面白いし、とてもためになる。
■当然ながら、僕もまた、九〇年代は生きていたわけだし、しかも子どものころだった六〇年代が、記憶が薄かったり、遠い出来事としてわからないのとは異なり、九〇年代はついこのあいだ、大人だった自分はかなりリアルに実感していたはずだ。それでも、目に入らなかった文化はあきらかにあった。「言葉」は知っていた。「存在」は知っていた。「状況」もわかっていたつもりだが、もっとからだに近いところにある実感のようなもの。Kさんはメールに書いている。
ブログですこし前に青山正明について書いておられましたね。/かつてレイブ会場だかで何度かすれちがったことがあります。/僕はインドでニューヒッピー&レイブ勃興を体験したり、ドラッグカルチャーに一時漬かったりしたこともあり、彼についてはいろいろと思うことがあります。
ということはつまり、ドラッグを身をもって体験したということなのだろうか。なんて、ジャンキーだ。そんなふうには見えなかったが、まあ、人ってのはわからない。そんなことはともかくさらに話は続く。
書いておられたことを補足させていただきますと、彼の文化的バックグラウンドとして80年代の自販機系雑誌『JAM』や『HEAVEN』があったように思います。/彼の文章で思い出深いのは『危ない薬』の後半の修行系への言及、そして『危ない一号』だったかのトランスパーソナル心理学への批判。/ポイントは、ポスト・オウム、ポスト・オカルトにおいて"超越"といかに向き合うかということだったように思います。/宗教的な”超越”でなしにいかにそこにたどりつくか。それがドラッグへのザハリッヒなまなざしであり、また悪趣味という回路ではなかったか。/そこにレイブ、テクノ、サイケデリック・トランスが輸入されます。/1999年、代々木公園で行われたサバイバル・リサーチ・ラボ(SRL)のライブ客席にハニカー系(ヨージ・ビオメハニカのファン)の蛍光色ドレッドのレイバーが混ざっていた光景を忘れられません。悪趣味とトランスの交差点・・・
ここで取り上げられている、「80年代の自販機系雑誌『JAM』や『HEAVEN』」は、僕などの世代が受け手だった時代の雑誌で、おそらくパンクやニューウェーブの文化的な影響下にあった、伝説の雑誌だ。『HEAVEN』は何冊か持っていたはずだが捨ててしまってもう家にはないので、しばらく前、ヤフーオークションに八冊揃い「五万円」で出品されていたときは入札するかどうかで、そうとう悩んだ。
つまり、青山正明(1960年生)と僕(1956年生)は、四歳年齢がちがい少し世代が異なるとはいえ、多くの部分で同時代を共有していることになる。
異なることがあるとすれば、八〇年代をどこで生きていたかになるだろう。僕は、青山正明がいたエロ本業界には縁がなかったし、出版業界と多少、関係していたが、種類の異なる場所に僕はいた。すると、前史として、「80年代の自販機系雑誌『JAM』や『HEAVEN』」の受容があったのち(しかし、正しく書くなら「七〇年代末から八〇年代前期の雑誌」になるか)、次の時代(八〇年代ど真ん中)にどこでどうしていたかによって、九〇年代の迎え方が異なった(八〇年代にルサンチマンを抱いた層が「八〇年代はスカだった」と言葉にしたように)。そしてKさんが書く、「ポスト・オウム、ポスト・オカルトにおいて"超越"といかに向き合うか」という青山正明の態度の根底にあるのは、オウムの幹部と自分が同世代だったこと、「感性」に近しいものがあるのを知り、共感と同時に出現するのは深い「問い」だったことだ。青山正明にあって、ドラッグはオウム以後ではなく、オウム以前であり、ドラッグへの接近についてしばしば彼は「ひまつぶし」といった意味の発言をしているが、オウムとよく似た「感性」(誤解されるのを覚悟で書けば、九〇年代における「ドラッグカルチャー」とは、その「感性」にあると私は考えるが、うーん、言葉が足りないか)が根底にあったからこそ、生きることの深い部分にドラッグと共振する思想があったと想像できる。「快楽主義」と彼自身は口にしていたかもしれないが、「ドラッグ」にしろ、「バッドテイストな笑い」にしろ、あるいは「ロリータ趣味」にしろ、単なる受動ではなく「発信する側」に回ったとき、「発信する行為」はきわめて強い思想性を帯びることになるにちがいないのだ。
■というわけで、この項、つづく。Kさんのメールはさらに続き、とても刺激されるのである。
■先週は、メディア論があって5コマの授業をやったわけだが、やけに疲れた。で、週の終わりの金曜日、「都市空間論演習」は、まったくだめな授業になったのだ。なんか、頭がぼーっとして用意してきた考えがまったく出てこないわけですよ。だめだった。というか、この日は朝から、「考える人」(新潮社)の原稿を書いていたが結局、書けず、あまり眠らなかったのがいけない。失敗したなあ。なんだかへとへとに疲れたよ。
(17:48 Jun. 8 2009)
5←「二〇〇九年五月後半」はこちら