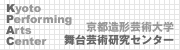Oct. 16 fri. 「一週間が終った」
■たしか今週の月曜日は休日のはずだが、必要なものがあって、大学に行ったら授業があるらしく門が開放されていた。おそらく休日が月曜日に集中するので、何日かは休まずに授業をやるのだろう。このあいだ台風で休講になったしな。研究室まで行き、佐藤信さんの戯曲集『あたしのビートルズ』を探す。そこに『イスメネ』という短い戯曲が収録されているからだ。「座・高円寺」の「テキスト読解」で『アンティゴネ』をとりあげるにあたって、あらためて読んでおこうと思ったからだ。もうかれこれ、30年近く読んでいなかった。人間、歳をとるのもいいことだ。かつて理解できなかった戯曲を読めるようになっていた。
■ところで、今週、特に変化があったのは、いとうせいこう君に促されて以来、「Twitter」でしばしばつぶやくようになったことだろう。以下、NHKによる「Twitter」のニュース。
ははあ、そういうことになっていたのか。ただ、まだよく理解できないことがあって、このサービスを利用して情報を得るというのはどうすればいいのか。「フォローする」とか「フォローされる」といった感じがうまくわからない。「フォローする」の場合、いったいどうやって知人を探せばいいのか、まあ、すごくわかりやすい名前で登録している人、あるいは、おそらくこれはあいつだろうと確信を持てる人はいいが、無闇にフォローするのもいかがなものかと思ってしまうが、そういうものでもないのだろうか。
■で、少しずつつぶやいている。ただ、外に出たとき、iPhoneでつぶやくべきなんだろうけど、忘れるんだよな。家に戻ってから、あ、つぶやかなければと、そう思って慌てるがこんな使い方はおそらくまちがっているのだろう。iPhoneでつぶやくことを心がけよう。心がける、って、なぜそんなに義務感を抱かなければいけないのだ。まだ、「Twitter」をちゃんと理解していないってことだな。
■「座・高円寺」の「テキスト読解」の講義を引き受けて以来、火曜日から金曜日まで仕事をしに出かけるという立派な人間になってしまった。「テキスト読解」は今週から、『アンティゴネー』を読みはじめる。スタッフのSさんの提案もあって、受講生が能動的に関わるようにと、「ギリシア悲劇」や『オイディプス王』『アンティゴネー』についてあらかじめ基礎データを発表してもらった。よくできた発表になっていた。
■僕もかなり講義ノートを用意してきたが時間がなくなったので続きはやはり次週へ。でも今週末は、次のテーマのブレヒトについて調べる。で、いま気がついたが、ブレヒトに関する資料を研究室にぜんぶ忘れた。
■大学は、水曜日からいつもの授業をしっかりやったぞ。今期も休講なしでがんばる。ところで、11月6日に慶應大学の藤沢にあるキャンパスで僕は特別な講義をやる。福田和也さんのゼミ生が企画したものである。水曜日はその打合せをした。あとで藤沢キャンパスがどこにあるのか地図で探したがものすごく遠い。これはちょっとした旅ではないか。よく通ってるなあ。驚かされる。
■といったことで、きょうは四限と、六限のあいまに、岡室さんと、このところ議論をしている「つっこみ」というテーマで少し話をする。学生を研究室に呼んでしまったので、岡室さんとじっくりその議論を煮詰められなかったが、根本にあるのは、「つっこみ(=批評)」によって、ある種の「ドラマ」は成立しなくなったのではないか、演劇でも、テレビドラマでもそれはあり、たとえば「韓国のドラマ」を例にとればわかりやすいかもしれないが、あれ「批評しよう」と思えば、というか、つまり「つっこもう」と思えば、いくらでもできるほどドラマとしての虚構性がどうにも「嘘」くさい。
■こうした「物語」「ドラマ」が成立しなくなった背景の、「批評する方法の一般性」、あるいは「ごく普通に人がつっこむようになった」という状況から、いかにドラマを成立させようと脚本家や劇作家が努力したかについて、たとえば岡室さんは宮藤君のドラマ脚本を例示するし、また、平田オリザをはじめ、九〇年代に出現したある種の演劇作品もまた、「物語」や「ドラマ」が成立しない状況を背景に生まれてきたと言える。九〇年代のはじめ、平田オリザの『ソウル市民』を観た僕は、そのことを演劇誌『しんげき』の劇評で書いた。もうそのときからそうだったのだ。
■しかし、「ものを見る方法」、あるいは、「批評する方法(=つっこみ)」という視点は誰かが発見しそれが一般化した。つまりポピュラリティーを持つということですね。「方法」を教えてくれたのは、たとえば、ビートたけしさんであり、タモリさんであり、あるいは蓮實重彦さんだったとわたしは考えるのだ。七〇年代から八〇年代にかけ、その視点が一般化し、いまでは凡庸なほど、誰もが「つっこみどころまんさい」という言葉を使うようになった。しかし、「巧拙」はある。誰でも鋭いつっこみができるわけではないものの、先にあげた先達の方法を使えばそれなりの批評はできる。それをかいくぐって創作する側は、またべつの方法で「物語」や「ドラマ」を書かなければいけない。しかもそれは、「つっこまれないようにしよう」として、「逃げる」ことではない。正面から向かってゆきつつ相手をねじふせるほどの力業が必要になるにちがいない。
■ふー、一週間が終った。疲れた。でも、ブレヒトの勉強をしなくては。ブレヒト、面白いよな。まだやることは無数にある。「新潮」のKさんに連絡しなくちゃいけないのに予定がたたない。いよいよ窮地に立っている。
(7:53 Oct. 17 2009)
Oct. 11 sun. 「あわただしい」

■この数日忙しかった。いろいろな人に会った。きょうは舞台も観た。「座・高円寺」で上演されていた、『旅とあいつとお姫さま』だ。子ども向けの良質な舞台。面白かった。客席の子どもがいろいろ口に出す。首が出てきたのを見て、「にせものだよ、にせものだよ、ほんものだったら警察に捕まっちゃうよ」と言っていた。笑ったなあ。
■先週のことを書こう。
■めまぐるしかった金曜日の話。「都市空間論演習」の授業のあと、というか、その授業もやることがいろいろあって(学生たちをフィールドワークに向かわせるための準備など)大慌てだったものの、そこからがさらにいろいろだった。長い一日。すでに書いた、日本建築学会の雑誌を編集しているSさんが学校を訪ねてくれ、白水社のW君や、TAをしてくれる近藤、イシハラやアベらと次の授業までずっと話をしていた。建築の話。やっぱり建築は面白く、それというのも、建築の潮流は社会を色濃く反映するからだろう。いま、こういうことになっているのかと、建築を通して世界を見せてくれるような感じというか。
■そんなことを話していたところへ、3年生のOが現れ、バイト先でもらったという食パンを大量に置いていった。Oが来てくれたのはうれしかったものの、しかし、この食パンの量はどうなんだ。36枚ある。次の演習の授業を受講しているのが、ちょうどそれくらいの人数なので、一人に一枚ずつ配るのはどうかと近藤が言う。しかしなあ、食パンを食べながらの授業ってどうなんだ。結局、もっとも腹を空かせているにちがいないという理由で31枚はイシハラが持って帰った。あと五枚は、いとうせいこう君の手に渡った。なぜなのか。で、次の授業「サブカルチャー論演習」の履修者がこれまでに比べてやけに多い。教室にぎっしり学生。
■五枚のパンがいとう君に渡った成り行きを書くと、まず、いとうせいこう君と、奥泉光さんによる「文芸漫談」が早稲田で開かれたことから語り出さなければいけない。いとう君に会いたくてそれを聞きに行き、結局、その流れで打ち上げまで出ることになったのだ。イシハラとアベも一緒に来たが、食パンを抱えているイシハラを見て、いとう君が「五枚くれ」と言ったのである。枚数指定である。「パン粉にするから」といとう君。
■38号館のAV教室という、戸山キャンパスではいちばん大きな教室で、文芸漫談は開かれた。面白いな。奥泉さんが話をはじめると、それにいとう君が素早く反応してつっこむという、その構造がかなり完成されている。何度も笑いを誘うが、あいまに語られるのはかなり知的な文学についての対話だ。終って、白水社のW君と少し話をしていたところ、遠くから、僕を見つけたいとう君が、「宮沢さん」と声をかけてくれた。20年以上経っても、その声の響きと、そこから出てくるいとう君の人柄の感じが変わっていないと思ってうれしかった。それで僕は一日、かなり慌しかったこともあり、すっかり疲れて早めに帰ろうと思っていたが、誘われて、打ち上げの席に呼ばれたというわけだ。
■たくさんの人に会ってしまった。僕のエッセイをよく読んでいると川上未映子さんは言った。ありがたい。映画の話をする。映画で「演じる」ことが、どういったものかわからなかったと川上さんは言った。なにしろ、いま会ったばかりの窪塚洋介さんと手をつないで走らなければいけないが、どうしたって、そうした気分になれないと。ああ、それはそうか。つまり、川上さんは、かなり「ライブ」の人だということだ。映画俳優と呼ばれるような人たちはそれをどう解決しているのか。映画はシナリオの順番通りに撮られるとは限らないし、編集されてどうつながれるかわからないまま俳優は、カメラのフレームのなかで演じなければいけない。舞台では、時間は一定の方向に流れるので、俳優は、その時間の感覚で生きる。まったく異なる感覚なのだろう。俳優をやったことがないので僕にはその生理がわからない。で、逆から考えてみるとわかることもあるのではないか。つまり、映画の俳優が、舞台に出たときに感じるだろう、さまざまな「舞台」の不思議についてだ。おそらく、人はそうして、異なるカテゴリーのあいだにあることから、そのものを学ぶのではないだろうか。ちがいによって気づかされるということ。いま会ったばかりの窪塚さんと手をつなぐような気分ではないのに、では、舞台でそれができるとしたら、逆に考えれば、できてしまうこともまた不思議である。
■それにしても川上さんは気取りがなくてとても感じのいい人だった。あと、いとう君と久しぶりにゆっくり話ができた。で、いとう君にうながされ、Twitterで、もっと頻繁につぶやかなければならくなった。忙しいな。
■そんな日々だけど、なんだったんだ金曜日。一日がすごく長かった。土曜日と日曜日は、ずっとソフォクレスの『アンティゴネー』をあらためて読んでいた。ジュディス・バトラーの『アンティゴネの主張』や、小川真人さんの『ヘーゲルの悲劇思想』などを横に置いて。「新潮」のKさんに連絡しなくてはいけないのだが、なにかを書く時間がない。うーん、来年は、高円寺の講座のことをあらためて考えないと、創作ができない、というか、だいたいその「座・高円寺」で舞台をやるのもままならないではないか。困った。
(12:42 Oct. 12 2009)
Oct. 8 thurs. 「ホール・アース・カタログのこと、ゴダールのこと」

■七月にあった「ゴダールシンポ」の前、毎日のようにゴダール作品を再見したことはすでに書いたが、そのころ、なんとか観ることができないかと探したのが、六〇年代末から七〇年代にかけて、ジガベルトフ集団名義で制作されたゴダール作品たちだ。国内版はほとんどない(『東風』はビデオがある)。ネットで探したところ海外からDVDボックスを買うことができると判明したものの、字幕はポルトガル語(ブラジルで作られたかららしい)だ。でもまあ、なんとかなるだろうと思って注文したが、いっこうに届かなかった。そうこうしているうちに「ゴダールシンポ」は終わり、夏も過ぎ、ゴダールのことも忘れかかっていた、そんなきょうのこと、ようやくDVD『Jean-Luc Godard And Groupe Dziga Vertov Collection (1968-1974)』が手元に届いたのだ。うれしかった。外国になにか注文したとき、それが届くよろこびはなんだろう。
■さて、大学は台風の影響で休講になった。「戯曲を読む」の授業がなくなってしまった。授業の用意をしていたので、急になくなったのはなにか肩すかしをくった感じである。とはいうものの、今週もいろいろで忙しかった。で、今月と来月のスケジュールが意外にタイトである。昼間、「新潮」のKさんから電話をもらい、このままずるずる書かないのは、少し書いたこともあるしもったいないというか、書かねばならないということでアドヴァイスを受け、ついては、どこか一区切りつける日を決めて会い、その日までに少し進めようという話になった。うーん、死ぬ気になればなんとかなるだろうか。
■火曜日は毎週、「座・高円寺」で「テキスト読解」の授業だが、この準備も忙しいものの、まあ、自分が勉強するための時間だと思えば、なんということはない。しかも講師をしていると、「座・高円寺」の二階にある「アンリ・ファーブル・カフェ」での飲食が二割引である。とても雰囲気がいい空間だ。近くにお寄りのさいはぜひ足を運んではいかがか。とてもいいです。
■大学は「サブカルチャー論」があって、ここんところ、シマという神戸出身の学生が授業後、研究室に来るようになった。この男がまた、音楽について、やけにマニアックに詳しい。なかでもなるほどと思わされたのは、先頃、マリファナで捕まった鈴木茂の報道のあり方についての彼の憤りである。鈴木茂さんは、数多くのミュージシャン、アイドルらの歌のアレンジをしており、むしろシマにとってはそうした音楽活動において存在していた人だった。ところが、報道では、「元はっぴいえんどの鈴木茂」としか紹介されなかったといい、それがおかしいと怒る。言われてみると、誰も、松本隆のことを「元はっぴいえんどの松本隆」とは言わない。「作詞家の松本隆」だ。細野さんもそうだし、むしろ細野さんにいたっては、「元YMOの」とも形容されないだろう。
■はっぴいえんど後の、鈴木茂を評価するシマにとって、この報道は許せないものだった。それにしてもこと音楽に関して、彼の該博な知識に驚かされた。しかも、かなりマニアックで、なんでそれ知ってんだって話がぽんぽん口から出る。そして、当然、イシハラとアベはいた。アベはこのあいだの「アゴラ劇場弟子のくせになんだよ問題」について、僕がここに書いたことについて怒っていた。イシハラは、「弟子に彼氏がいるというのは、弟子の概念からしておかしい」といった意味のことを言う。たしかにそうかもしれないが、なんだか理不尽な論理だ。
■あと、「都市空間論」のTAをやっている近藤は、このノートを読んでいて、アベのことをずっと男だと思っていたというので、まんまと作戦が敵中したと、うれしい気分になったのだ。どこでアベが女だということをばらすか、ずっと考えていたのである。そんなふうに学生たちとの会話はえんえん続く。面白くてしょうがない。
■「サブカルチャー論」では、とうとう「六〇年代」が終った。最後は、僕がどこで、どんなふうにして、「六〇年代が終わった」のを実感したかについての話。以前も書いたように(2008年12月9日付)、一九八〇年の十二月のことだ。まだ僕がなにもしていなかったころ。なんでもなかったころ。ジョン・レノンが死んだとき、子どもの自分が強く影響を受けた「六〇年代的なもの」がすべて終ったと、僕には感じられた。
■そして、それまでなにもできず鬱々としていたからこそ、八〇年代になにかを期待していたのではないだろうか。そんなふうにして八〇年代がはじまったけれど、楽しかった反面、それでもなにかもの足りなさを感じていたからこそ、九〇年代に入って僕は、またべつのことをしはじめたのだと思う。ただ、ぜんぶはなりゆきだなあ。たまたま八〇年代になってから仕事をはじめ、それもごく偶然で、やっぱりなりゆきだった。なにかに導かれていると書けば、ひどく感傷的だが、ジョン・レノンが死んだ八〇年の十二月のその日のことを語るのもまた感傷的になってしまう。
■さて、「サブカルチャー論」は来週から、いよいよ七〇年代の話。はじまりはおそらく七〇年の三島の事件かもしれない。だが、その前に、ヒッピーカルチャーから出発した新しい生き方の模索としての、「ホール・アース・カタログ」の話になるんだけど、そのことについては、このところメールを頂いている、日本建築学会のSさんから興味深い話を教えてもらった。日本建築学会の会員に毎月配布される会誌「建築雑誌」(Sさんが連絡してくれたのは、この雑誌の取材の件があったからだが)の編集長が、「ホール・アース・カタログ」を編集していたスチュアート・ブランドにスカイプによるインタビューの交渉をしているという話だった。それはすごい。面白そうだ。と、まあ、そんなこともあり、いよいよ「七〇年代論」がはじまるが、学生たちは興味を持ってくれるだろうか。
(5:28 Oct. 9 2009)
Oct. 4 sun. 「オリンピック、その他」

■先週の木曜日(10月1日)はメディア論の授業で午後から大学に行ったが、第一回目は担当する四人の教員による挨拶だ。大人数を収容する戸山キャンパスではいちばん大きな教室だったが、そこのAV機器が新しくなっていた。プロジェクターが明るいので映像がかなり鮮明だ。
■あと、手元でペン入力した文字や絵が画面に映し出される。よく授業でやる「記号」についての話をそれを使ってやってみた。学生に「富士山」を描いてもらうのがいつもの手だ。誰かが発明した「富士山の記号」は、日本人の大半が描けるとされている。ところがだ、最初に、ちょっと描いてみてと声をかけた学生が留学生だった。「描けない」という。しょうがない。それでべつの学生に声をかけたら、前に出てきたくせにペンを手に逡巡している。どうした? と聞くと、また留学生だった。そんなことってあるかよ。だいたい、書けないのになぜ出てきたのか、っていうことと、留学生には描けないことが興味深く、それというのも、ではなぜ日本人だったら富士山を描けるか、それが謎だ。
■自分が担当する回のさわりを話したが、地図に関する内容にからめてNHKで去年の秋、単発で放送されていたブラタモリという番組をほんの少し流したのだ。で、話は飛んでその夜のことになるが、たまたまテレビを観たら、レギュラー化されて新番組として「ブラタモリ」をやっていた。なんて偶然なんだろうと思ったら、しかも、第一回目のテーマが「早稲田」である。大学を中心に早稲田界隈が、古地図などをもとにその歴史がひもとかれる。縄文時代の地形にまで話はさかのぼる。偶然の不思議にめまいがする想いをしつつ、それにしてもこれ、地図好きにはたまらない。今回が「早稲田」で、次回が「上野」だというが、「上野」はおそらく、もっとなにかが潜んでいるにちがいない。
■その夜は「戯曲を読む」の授業。二文の学生はどんどん減っているがもぐりの学生も含め、10数人はいるのでたのもしい。商学部のイシハラがまたもぐっている。まして弟子のアベももぐっている。アベといえば、日曜日、アゴラ劇場にマレビトの会を観に行ったら、弟子のくせに彼氏と一緒に来ていやがった。修行の身でデートをするとはなにごとだ。しかも、場所はアゴラ劇場かよ。もっとデートらしい場所ってものがあるじゃないか。だいたい、横浜国大に通っているはずなのに、最近、西武新宿線沿線に引っ越したって、それ、あきらかに早稲田に通いやすい場所じゃないか。どこまでももぐるつもりか。
■それはともあれ、そうだ、松田正隆が主宰する「マレビトの会」の話も書こうと思うが、どうしても書いておきたいのは「オリンピック」のことである。
■残念だった。落選してほんとうに残念だった。いやあ、残念だ。残念でしょうがない。いやはや残念。笑えるほど残念。残念すぎて、落選が決まったニュースを見た瞬間、バンザイをしてしまった。祝杯をあげた。人間、気が動転すると、なにをするかわからないものである。
■松岡修三やオリンピック招致の委員たちが言った。「子供たちに見せたかった」と。うそつけこのやろう。おまえらに利権が発生するだけじゃないか。東京の子どもだってむつかしいが、まして全国の子供たち、北は北海道から、南は沖縄まで、すべての子どもに生でオリンピックを見せることができるだろううか。不可能だ。見せられるわけがない。東京に出てこられない子どもが数多くいる。経済的に無理だったり、さまざまな理由で誰もが見られるとは限らない、というか、ある限られた子どもだけが見られる。松岡には想像もできないだろう。一九六四年に子どもだった私は東京オリンピックを見られなかったぞ。「子供たちに見せたかった」と、口あたりのいい、もっともらしい言葉を簡単に使うなこのやろう。もっと端的に、みんながみんな、「これでしばらく仕事に困らなかったんですけどねえ」と言えばよかったのだ。正直がなにより。
■「マレビトの会」の公演『cryptograph(クリプトグラフ)』の感想を、印象だけで書くのは気が引ける。もっと考えて書きたいと思うが、この何年か、松田正隆の作風が過去とはすっかり変わったことについて、舞台を観ながら考えていたのは、僕もまた変化したことがあり、作品そのものと同じくらい、この「変化」についてそれがなにから生まれたかがとても興味深い。いま、なぜ、こうした方法が求められるのか。松田正隆は、かつてきわめて正統な劇作の方法にたけた作家だったし、おそらくその書き方をしていれば、ある種類の劇の世界で一定の地位を獲得していたはずだ。だが、作家が、あるいは演出家として「変化」するとき、時代との切り結び方が、時代に対して、いまある演劇に対して、「誠実だった」としか言いようがない。
■演劇についてより強く考えれば、彼の内部にあった過去とは異なる資質によって、新しい表現へと踏み出すのは当然の帰結だったにちがいなく、一方に、時代を反映する「数多くの人気の舞台」がありながら、むしろ反時代的な方法に向かうことが、逆に、「現在の正しさ」であると確信したのだろう。あるいは繰り返すが、それこそが「誠実さ」である。その「こと」に共感する。ただ、ひとつ気になるとすれば、表現がある方向に向けて抽象性を帯びるとき、では、俳優の身体の変化をどこに求めるのかについて。身体はどう変化したか。一部の俳優たちは数多く舞台を踏み経験を通じて確実に成長しているのが印象的だが(たまたまわたしが、彼らを学生時代からよく見ていたという事情がある)、この「成長」は、作品の中心にある表現から生まれているのか、それがうまく感じ取れない。しかし、かつて感じたような、政治的な「劇言語」と、彼らの「生の身体」のあいだにある距離はずいぶん変わった。「カラダ」はときとして作り出すことができる。劇の言葉にあわせて作り出し、作り出す技術が「うまい」とされる劇の世界もあるだろうが、松田正隆がいま作ろうとしているのは、もっとべつのことではないか。
■さまざまな試みをする舞台に触れることの刺激がある。飴屋法水の舞台にあったのは、これとはまた異なる刺激だったし、またべつの舞台を観に行けば、新しい刺激をもたらしてくれるだろう。来年の十月、僕も新しい舞台を上演する。それが刺激になれたらいいと思う。いや、刺激するぞ、世の中を、といった気分に自分を高めなきゃ、芝居なんてやってられないけれど。
■少しずつ涼しくなってきました。大学の授業は順調にリスタートしました。なんとなく前期より、学生のモチベーションが高いような気がする。そちらがそこまで食いついてくると、こちらもやる気が出てくるというか、負けるものかと、学生のエネルギーに負けてたまるかという、わけのわからない気分になっているのだ。
(14:55 Oct. 5 2009)
9←「二〇〇九年九月後半」はこちら