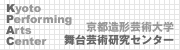Feb. 26 wed. 「あけましておめでとうと言うひまもなく」



■とてつもない2月だった。人生でこれほどせっぱつまった2月はなかった。だってたいてい2月ってのは、寒い寒いと口にしているうちに終わってしまうのものではないか。
■それが今年に限ってなんだったのだろう。まず、大学の成績をつける作業があり、そのためには大量のレポートを読む仕事が待っていたのだ。さらに修士論文も読んださ。卒業研究の学生たち(どこのゼミにも所属していなかった学生)の卒論も読んだ。
■そうこうしているうち、文芸誌「新潮」に『ボブ・ディラン・グレーテスト・ヒット・第三集』を発表することになり、まあ、去年の暮れあたりから書きはじめ、年が明けてようやく脱稿。そして、その直し、ゲラチェックでてんてこまいだった。でも、納得ゆくまで直しができたこと、直しの作業を通じて小説の書き方、魅力を再発見できた。「新潮」4月号に掲載されます。たくさんの人に読んでもらうのが楽しみだ。それから「フェスティバル/トーキョー」から依頼された相模友士郎君の『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』の劇評を12枚と頼まれていたのに、30枚くらい書いたっていう、どんだけ書けば気が済むんだってくらい書いた。それを短縮する作業。そして、岸田戯曲賞の候補作を読む。今回は九作。読んだ。ものすごく読んだ。丁寧に読んだ。死にものぐるいで読んだ。そして早稲田エクステンションセンターで「90年代サブカル論」の講義。その準備も。
■そんな忙しいなか、以前から決まっていたスケジュール、観劇の予定も無事にすますことができ、いくつもの舞台に刺激を受けた。ただ、パレスチナのなあ、演劇を観ることができなかったのが心残りだ。
■本日は水戸までチェルフィッチュの『ゾウガメのソニックライフ』を観に行った。いい観劇体験だった。そのあいだ(というのはつまり観ているあいだということだが)ずっと考えていたのは、「静かな祝祭」という言葉だった。というのも、去年の飴屋法水さんの作品『わたしのすがた』を観てからずっと、「祝祭から内省へ」という時代の潮流について、それをどう論拠づけようか考えていたが、「内省」が文字通り「静謐さ」だけで語られることもないのだと、『ゾウガメのソニックライフ』を逆の方向から観ていた。そこにあったのは「祝祭」である。そして「祝祭」はわーわーとにぎやかでなければいけないかのようだが、その内部にふつふつ沸き立つものが、しかし外部に溢れることもなく、内的でなにかを生み出しているのなら、それこそまたべつの意味での「祝祭」だと、『ゾウガメのソニックライフ』における岡田君の表現に感じた。
■正直、前作、というのは横浜で上演された『私たちは無傷な他人であるのか』の、新しい岡田君の表現と、言葉がとても新鮮で、そのタイトな舞台のスタイルに強い刺激を受けたが、またちがうものが「ゾウガメ」にあったとすれば、それが「静かな祝祭」だったと思わずにいられない。
■では、その意味はなにか。それが演劇に与える影響とはなにか。「祝祭」に含まれる「性的なエネルギー」はしばしば、文字通りの「お祭り」においてハレの場が象徴するように「過剰さ」「豊穣さ」「にぎやかさ」が特色として語られはするが、では、その瞬間、ある特別な祝祭のさなか、人はふと「内省」することがあってもいいはずであり、飴屋さんの作品に感じた「祝祭から内省へ」という現在を感じさせる表現とはまたべつに、「静かな祝祭」ということで演劇の可能性が広がり、豊かになると思ったのだ。
■演劇は、「歴史的にも」「経験則においても」、祝祭から誕生したといった語られ方をするが、そうではない側面もきっとあるのであり、それはつまり、教会で祈りを捧げる体験によく似た、「もの」や「こと」との対峙のありようだ。だから「内省」は「教会で祈りを捧げること」のアナロジーではないかと、私は少し前に劇評に書いた。
■では、「静かなる祝祭」とはなにか。演劇の二つの誕生の径路の統合として、そこに出現する表象である。お祭りとして人が踊り騒ぐことによって演劇の原初性が生まれたのと同様、祈りが原初的に存在したとしたら、それらは長い歴史のなかでクロスし、重なり合い、ともに成長し、現在に至ったのであれば、そこに特別な演劇が生まれてもおかしくはない。それがたとえば、『ゾウガメのソニックライフ』になるのではないか。だからまた、飴屋さんの『わたしのすがた』は、「にぎやかな内省」とも言えるかもしれない。
■わかりやすく、「祝祭」と「内省」が、もっというなら、「生の演劇」と「死の演劇」がわかれる時代ではないのかもしれないが、ではそれはなんの反映なのか。なにがそれをもたらしたか。ここで「経済」を持ち出すのはおかどちがいな気もするが、〈私〉はこの「ゼロ成長」を無意識のなかで強く影響を受けており、ある時代(たとえば八〇年代)とはまったく異なり未来が見えてないことへの、不安は誰もが抱えているし、人口もまた減少してゆくように、経済的成長は多少の変動はあっても、かつてのようにはけっしてならないとするならば、この漠然とした不安とゆらぎは、人の意識にどうしたって反映する。浮かれている場合でもないのだ。だから、まっすぐ「内省」へと人の意識が変化すると結論づけてもよかったが、それだけで人は生きていけないからこそ、「静かな祝祭」は確実にある。
■『ゾウガメのソニックライフ』がつむぐのはこの現代的な貧しさが表出する昏い眼差しによる〈いま〉を語るテーマだと思わずにいられない。それでも、演劇のある部分に遡る「静かな祝祭」によって観る者を救う。フェスティバル/トーキョーで観た、相模友士郎の『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』と同様、ここに、こちらが想像力を働かせなければならない「救い」があると思えてならない。それはやはり「教会での祈り」に似ているが、しかし、あくまでも祝祭である。そこが、『DRAMATHOLOGY/ドラマソロジー』とのちがい、「生」と「死」についての意識のちがいではなかったか。岡田利規はこんな時代の暗澹たる「生」の現場から語り出そうとしているのを感じる。それがゾウガメのソニックライフだ。
■まもなく、3月です。これが今年、最初の「富士日記2.1」の更新になりました。演劇についてもっとゆっくり考えてゆこうと思います。というか、いまこういったことを考えること、小説について考えること、ゆっくりものを考えることが楽しく、それというのも、こんな時代ですから。もうゼロ成長ですから。先はないですから。とはいえ、静かな祝祭を、僕も目指します。
(9:33 Feb. 27 2010)
12←「二〇一〇年十二月後半」はこちら