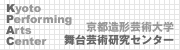Jun. 15 sun. 「先週のことなど、そして、なぜ秋葉原だったのか」

■更新がまた滞ってしまったので少しずつ書いてゆこう。
■たまたま、写真部のM君が主宰する勉強会のようなものがあって土曜日は早稲田に行くことになっていたのと、クルマが不調ということもあって(動かなくなったのだ!)、地下鉄に乗ったのだった。14日開通の「副都心線」である。「新宿三丁目」の駅から、「西早稲田」まで。「西早稲田」の駅は、明治通りと早稲田通りの交差点に駅があるかと思いこんでいたが、そうではなく、一本新宿よりの諏訪通りとの交差点にあった。そこから早稲田の戸山キャンパスまで歩いた。だらだら坂を下った。けっこうな距離がある。はじめて早稲田構内の学生会館というところに入ったが、「学生会館」という言葉でぱっとイメージするのは汚い場所だがすごくきれいだったし、高層の建物なのでエレベーターに乗る。これが学生会館か。驚いた。僕が学生だったころには想像もできないような状況である。
■それで写真部の学生たち十人ほどの前で話をする。与えられたテーマは「写真とサブカルチャー」だ。そもそも、「写真」が専門でもなければ、「サブカルチャー」が専門でもないので、なにをどう話したらいいか困ったが、「なにも考えずに撮った写真をサブカルチャー論的に考察する」という内容にした。iPhotoに貯めてあった画像を90枚ぐらいランダムに見せて、それがいかに、なにも考えずに撮ったかを話した。それというのも、なにかを「意図する」と、いい写真が撮りたくなるからで、だけど、使っているのは簡単なデジカメだ。コンパクトなデジタルカメラは、やっぱり「カメラ」ではないのだと思う。カメラによく似たデジタル機器だ。得られる結果も、「写真」ではなく、「写真」によく似た「デジタルな画像フォーマット」だ。そんなものを見せられた学生も困惑したと思うが、こんな話でよかったのだろうかと、帰り道、いろいろ考えた。それでも、求められたらどこにでも話をしにゆきたい。少しでもよろこんでもらえたらそれでいい。それが僕の仕事なんじゃないか。
■先週もいろいろ忙しかった。笠木が作・演出をした舞台(アデュー公演『125日間彷徨』)を見たのは火曜日(10日)。けっして気持ちのいい話ではないが、ドラマとしてよく書けており、オールツーと、アデューと、これまで笠木が主宰した舞台を三本観たが、そのなかではもっともよかった。そのひとつとして考えられるのは、俳優への演出がこれまでとは格段に丁寧になされていたことだ。ディテールの積み重ねがドラマに書かれた世界に深みを与えたと想像する。戯曲を読んでいないのでなんとも言えないが、作り出そうとするのではなく、書いているその「からだ」から出るなにものかによって言葉が生まれてくるのを感じ、それこそが、「作家」が登場するということではないか。技術的な瑕疵はいくつかあるだろう。気になることはあっても、それはまあ、たいしたことではなかった。あるいは、いま「演劇という表現を選択する」ということについてどう考えたらいいか、というのは、つまり演劇そのものにどう関わってゆくかになるが、それもべつに関係ないように思えた。本来ならもっとも「演劇の現在」を考えるべき部面としてそれはあるはずだが、べつに、そんなことにとらわれることもないかなと、その舞台の成果から感じたのも不思議だ。僕なんかが意志している演劇の文脈とはまったく異なるところにこの舞台があり、それは、どのような手つきで演劇を紡ぐかというちがいになる。技術的な問題点を指摘する以上に、ほんとうならそこを、つまり「手つき」を考えるべきだと思うものの、それを忘れさせてくれるものが舞台にあった。もちろん、田中や、山本君など、よく知っている俳優が出ていることなど、僕の見る目に客観性が欠けるのは仕方がないが、僕が舞台を観るにあたって「手つき」をあまり考えなかったのも珍しい。そのことの不思議について、舞台が終わってからしばらく考えていた。
■前回の「サブカルチャー論」の授業は、なにより話をしている自分にとって意味のあるものになり、それというのも、先週「都市の変遷」について語ったからで、するとやはり、「二流の盛り場」として、いま「秋葉原」をどう捉えたらいいかという疑問が残る。その直後の先週の日曜日、あの「秋葉原での事件」が起こった。どうしても語らずにいられなかった。なによりも、「なぜ秋葉原だったのか?」だ。九十九年に起こった「池袋通り魔殺人事件」について考えるとき、それがなぜ池袋だったかを、犯人の造田の行動を調べて感じるのは、圧倒的な「無根拠さ」だ。造田の部屋に残されていたのは、社会を憎悪する言葉を書いた壁に貼られた数枚の紙と、中上健次の『十九歳の地図』の文庫本だった。『十九歳の地図』の主人公は、当時の国鉄に脅迫電話をかけ、そこでこんなふうに語っている。
「爆破なんて甘っちょろいよ、ふっとばしてやるって言ってるんだ、ふっとばしてやるんだよ」「なんでもいいんだよ。だけど、玄海ってことになったんだ、しょうがないじゃないか。任意の一点だよ、いいか、おれがノートにでたらめな点々をつくるだろ、一線とほかの線が交錯する部分、それを一つでも二つでも白いノートにつくったことといっしょだよ、その点をけしごむでけすんだ、それがわからなきゃ、けしごむのかすでもなめてろ」「うすらばか、とんま、なぜもへちまもあるかよ。点がな、猫だったら猫を殺す。点がみかんだったらみかんをつぶす」
つまり、造田の行動は、『十九歳の地図』の主人公がそうだったように、「任意の一点」に向かっていた。どこでもよかったのだ。無根拠に池袋が選択された。けれど、秋葉原の事件の犯人の加藤は、「秋葉原」でなければならなかった。その日の加藤の行動を調べると、レンタカーを借りて裾野インターから東名に乗って東京を目指すものの、なぜか横浜青葉のインターで降りる。その後、国道246号を都心へ進むが、途中、渋谷で渋滞に巻き込まれ、そのことを、「渋谷ひどい」と、携帯電話から掲示板に書き込んでいる。だったら、渋谷でもよかったはずではないか。そこに歩行者天国はなかったかもしれないが、駅前のスクランブル交差点にトラックごと突っ込むことも考えられたはずだ。だが、そうはしなかったし、加藤の社会に対する怨嗟は、なぜか「秋葉原のあの交差点」に向けられた。
その後、学生たちと話したりしながら、その意味を考えていたが、まだわからないことはある。べつに「加藤」という二十五歳の男(酒鬼薔薇と同年齢!)がどんな人物だったかなどべつに興味はないが、しかし、「都市の変遷」という視点から考えれば、「なぜ秋葉原か?」によっていまがわかるように思えた。それというのも、加藤の生い立ちはともかく、非正規雇用者だったという加藤の社会的な位置と、社会に対する怨みが秋葉原に向けられた行動が、異なる軸にあるとは考えられないからだ。同軸においてそれをとらえたとき見えてくる現在があり、それは「なぜ渋谷ではなかったのか?」になるのだし、あるいは、付属池田小事件のことも視界に入れれば、「なぜ銀座ではなかったのか?」にもなる。
■そんなことでまた忙しい一週間だったけれど、クルマが動かなくなったこともかなり衝撃を受けた。ところが、いつもメンテをしてくれるTCロサリーのTさんのおかげで無事に動くようになった。めでたし、めでたし、ってこともないけれど、月曜日(9日)には「新潮」のM君とKさんに会って、少しだけ進んだ小説を渡したのだった。少しずつ小説も書いている。
(14:36 Jun. 15 2008)
Jun. 6 fri. 「サブカルチャー再考」
■あれからさらに、「サブカルチャー」について考えていた。D・ヘブディジの『サブカルチャー』(未来社)の翻訳が出版されたのは一九八六年だが、原書は七九年に刊行されている。そこで取り上げられ分析されているのは、当然、七九年以前のことになり、するとパンクの出現とそのスタイルの分析がかなりの分量を占める。当時にあってはきわめて現在的だったと想像する。ただ、よくわからない叙述で本書は締め括られ、なんだったんでしょう、という気にさせられるが、むしろパンクの登場という衝撃がこれを著者に書かせたのではないか。というか、「サブカルチャー」を全面的にあきらかにしてくれるというより、パンクミュージックの、あるいは(具体的には)、セックスピストルズが出現した意味を社会学的な見地から解くために「サブカルチャー」という視座を使ったというか。それで、「サブカルチャー」のスタイルを読むために、さかのぼって、出現し存在した、「レゲエ」や「モッズ」、あるいは「テッズ」について分析されるものの、むしろ、「サブカルチャー」という言葉の多義性が強調されるようにその分析はある。
レゲエは、パンクロック同様、「真面目な」人びとから、ナンセンスとして、現代の英国生活の主要問題からの的はずれな気晴らしとして追いはらわれるであろう。他の場合には、レゲエとパンク・ロックは、堕落者と宣告されるか、あるいは、「善良で清潔な面白い人たち」に成り下がるのである。しかし、これまで述べてきたように、両者の一致はさらに深い。レゲエとパンク・ロックはともに、特定の歴史的な条件に反応して生み出されたサブカルチャーを背景にして創成された。この反応は拒絶を表現する。そして拒絶はコンセンサスからの分離運動で始まる(西欧民主主義の国ぐにでは、コンセンサスは神聖である)。この反応は差別を暴露するので、誰もそれを喜ばない。それはサブカルチャーのメンバーに、敵意とあざけり、「まっ青になって口もきけないほどの怒り」を与える。 ──『サブカルチャー』(D・ヘブディジ著 山口淑子訳 未来社)より──
ここで読むべきは、「レゲエとパンク・ロックはともに、特定の歴史的な条件に反応して生み出されたサブカルチャーを背景にして創成された」という部分だと思う。まず考えるべきなのは、「特定の歴史的な条件」の、「条件」に含まれる大きな要素は、本書にあっては「英国」だ(だからここでの「レゲエ」は、イギリスに移民した中南米人によってもたらされた「レゲエ」になる)。さらにわかるのは、「サブカルチャー」は、ある事柄への「反応」によって生み出されるものらしいことだ。そして、「反応は拒絶を表現する」とある。「この反応は差別を暴露するので、誰もそれを喜ばない」とあって(この翻訳された日本語の、子どものような言いぐさが気になるものの)、ここで解かれる「サブカルチャー」は、あらかじめスタイルや文化様式としてあったのではなく、「反応」によって、つまり、ある種の「やむにやまれぬ動機」によって社会が生み出した現象になる。そうした現象が背景にあってはじめて、「レゲエとパンク・ロック」は生まれた。しかもそれは、「まっ青になって口もきけないほどの怒り」のなかでだ(なぜこの言葉はカッコで括られているのだろう。ことによったら、なにか有名なフレーズなのかもしれない。たとえば、パンクの歌詞とか。あるいは、シェイクスピアか、マルクスっぽくもある)。つまり、「レゲエ」や「パンクロック」は表象(=意味するもの)だから、読むべき中心は、「反応」によって出現した、本質(=意味されるもの)となるべき「サブカルチャー」そのものだ。
いま「サブカルチャー」を考えるとき、ここで具体的に示された、七〇年代の半ばのイギリスにおける「二分法」(「権力側の人びと」と、「従属地位や二級市民の地位しか与えられていない人びと」)はいま有効だろうか。だが、それを差し引いて考えても、やはり、なんらかの「緊迫状態」を生み出さないとしたら、文化的な衝突、そこに文化同士が接触することで出現する、ぎりぎりと擦り合わされるような軋みが生み出す音は現れない。そのノイズこそが文化ではないか。したがって、サブカルチャーは表現力に富む形態である。しかし、サブカルチャーが表現するのは、結局、権力側の人びと、従属地位や二級市民の地位しか与えられていない人びとの間の、本質的な緊迫状態である。
二〇〇一年以降、「南北の格差」、あるいは「グローバリズム」と呼ばれる、いわば〈帝国〉としての世界の再構築と均衡化のなか、「非対称性」は経済の領域にあってしばしば異議を語られることはあった。では「文化」はどうだったか。音楽産業、映画産業のグローバル化において、文化もまた圧倒的な資本の力に世界が塗り潰されたとき、「非対称性」はここでも鮮明になる。だから、「権力側の文化」は、「圧倒的資本に支えられた文化」としてあらためて抑圧の対象になるのなら、「サブカルチャー」はそれに「反応」し、またべつの姿で現れてもおかしくはない。ただ、「高度に進んだ資本主義」はきわめて巧妙にできている。先日、早稲田の「メディア論」でデリダを専門にしている藤本さんがおっしゃっていたが、「資本主義は自分を批判するもの、否定するものもまた、自分の内側に取り込む」という性格を持ったよくできたシステムだ。では、どのようにしたら「緊迫状態」は生まれるのか。「緊迫状態」によって「資本」の裏をかくことはできるのか。
きのう書いたことにさらに補足するなら、「サブカルチャー」は消滅したのではないか、というのが僕の推論だ。というのも、「二流の街」が生み出すだろう、「二流」だからこその「官能」すら、渋谷でどん詰まりになりどこにも存在しないと考えるからだ。
いま、「サブカル」と呼ばれている表象は、ある層が享受している「ポップカルチャー」が並列した総体としての光景だ。「緊迫状態」を生み出すように、なにかに「反応」して出現する「サブカルチャー」ではない。歴史の切断点で、「サブカルチャー」は、「パンク・ロック」のような姿をして突発的に、あるいは歴史の必然として出現するのだとしたら、圧倒的な資本や、ネオリベ化する社会によって支配された文化のなかで、その萌芽すら見えてこないように思える。だが、待ってはいられない。「サブカル」の表象や、現象をあと追いしたり、解釈している場合ではない。だから、「能動的なオルタナティブ」は、その名の通り、進んでシステムの裏をかくことでその姿を明確にする。ニルバーナと、グランジは、そういった意味で、九〇年代におけるオルタナティブになりえたのだろう。そこには「緊迫状態」があった。いま現在、「緊迫状態」はどのように生み出されるか。「サブカルチャー」は再び、なにかに「反応」してその姿を現すだろうか。だが、「機は熟している。革命は近い」といったことにはけっしてならない。それは空虚に語られ現実を無視したロマンティックな過去のスローガンだ。
(8:34 Jun. 8 2008)
Jun. 5 thurs. 「きょうは早稲田へ」
■わたしはそのとき眠っていたのである。むしろ、最近では珍しくよく眠ってしまい、電話で目が覚めてはじめて、たいへんなことを忘れていたのに気がついた。失敗した。完全にきょうの予定を忘れていた。それで早稲田の岡室さんに迷惑をかけた。夕方、ようやく早稲田に行く。「戯曲を読む」という授業で、シェイクスピアの『オセロー』を読み、さらに「サブカルチャー論」。「サブカルチャー論」では「都市の変容」といったテーマで、「80年代地下文化論」と同様の内容を、さまざまな写真や映像を見せながら話をしたが、話しているうちにサブカルチャーについてあることに気がついた。
■小林信彦さんの『うらなり』は、題名が示すように『坊ちゃん』の登場人物である「うらなり」が主人公で、「うらなり」の視点から『坊ちゃん』を書き直した小説だ。その冒頭、「うらなり」は「山嵐」に銀座で会う。『坊っちゃん』から三十年後という設定だ。食事ののち、「これから、どうなさいます」と「山嵐」は「うらなり」に質問する。
「新宿というところに行ってみようと思ってます。なんでも新しい盛り場だとか」
「震災後に、ぐんと伸びた盛り場です。その前は、神楽坂だったのですがねえ。新宿は武蔵野館という映画館、ライスカレーの中村屋、この二つが目玉です。外国映画は神戸でも観られるでしょうから、殿堂のような武蔵野館の建物を眺めて、ライスカレーを食う手があります。中村屋ではライスカレーではなく、カリーと言います。英語で正確に読むと、そうなるのでしょうか」
「さあ。でも、向うがそう主張するのなら、正しいのではないですか」
「まあ、若者というか、学生の街です。当てもなく素通りされるのも一興かも知れません」
堀田は手帖を破いて、新宿の簡単な地図を描いてくれた。武蔵野館とならんで、ムーラン・ルージュという劇場もあった。
「二流の盛り場の雰囲気を味わうのも、想い出になるかと思います」
「これはどうも」
私は地図を二つ折りにして、ワイシャツの胸ポケットにおさめた。
ここで都市(=東京)について考えるとき重要なのは、「二流の盛り場」という言葉であり、二人が再会する場所を「銀座」にしたのも恣意的ではなく、おそらく「一流の盛り場」としての銀座を置くことで都市における土地の布置のようなものを小説の冒頭で示そうとしたからだと想像する。だからこそ、その時代の(おそらく一九三六年ごろの)「東京」の空気のようなものが小説の冒頭に漂っているのを読むことができ、二人のやりとりに目をやる限り、東京の「二流の盛り場」は、「浅草」「神楽坂」「新宿」といったように変遷していったと考えることができる。とりわけ、戦後「浅草」は見る影もなく衰退したが、しかし「若者というか、学生の街です」という言葉があるように、「銀座」という一流の街区とは異なる性格で「新宿」を表現するとき、「街」が生み出す文化圏域にあるなにものかが示されるなら、それこそが「サブカルチャー的なるもの」だろう。つまり「二流」という言葉が意味するもの。ただ、「二流」は、どの視点に立ったときに見えてくる「二流」か。「銀座」という「一流の街」がある。それを「一流」たらしめている文化があり、それとは異なる圏域にある事象はここでは、おしなべて「二流」になる。その言葉は「30年後の山嵐」が口にする。彼はすでに、『坊ちゃん』に登場する、あの「山嵐」ではなかった。小林信彦の描く「30年後の山嵐」は、どこか通俗的な匂いのするうさんくささをたたえた人物だ。そこに「一流」に対する小林信彦の視線が反映していると読める。
「80年代地下文化論」では、「八〇年代的なるもの」や、「オタク」という切り口で街について考えていたが、「サブカルチャー」という視点からあらためて同様に話をしているうち、六〇年代から七〇年代にかけて「新宿」にあった文化が、明治通りに沿って、「原宿」「渋谷」に移動していったことから現在を考えると、「二流のなにか」が、「渋谷」あたりでどん詰まった感がある。つまり、東京における「サブカルチャー」がそこで行き止ったようにも見え、それが「現在」ではないか。『新・都市論TOKYO』(集英社新書)において建築家の隈研吾さんは、「成熟期」という言葉で現在を語っている。つまり、「高度成長期」が終わり、いまこの国は「成熟期」にあるという視座から都市を考える。それを参照したとき「サブカルチャー」は、これまでとは異なる文脈でそれを理解しないと、たとえば「六〇年代の新宿」を懐かしむような懐古的なものでしかなくなる。むしろ、「渋谷」すらも、懐古的な現象でしかなくなるだろう。
「新宿」について授業で話ながら、そんなことを考えていた。
では、「サブカルチャー」はいま、どこにあるだろう。もはや「街」ではないのかもしれない。「秋葉原」はまたべつの活気を呈した「二流の街」だが、いま書いているような文脈とはまったく種類が異なると思えてならない。たしかに、『趣都の誕生 萌える都市アキハバラ 』(森川 嘉一郎 幻冬舎)で描かれた特別な街としての「秋葉原」はあるだろうが、かつての「新宿」「原宿」「渋谷」が、「二流」であるがゆえに、時代が軋むような音をたてて発していた「サブカルチャー」という魅力的な力をそこには感じない。もっというなら、「二流の持つ官能」のようなものが「秋葉原」には欠けている。
だから考える。授業をしながら考えている。
■授業が終わったあと、TA(授業のアシスタントをしてくれる学生)のT君と、打ち合せに来た白夜書房の女性編集者の二人、それから写真部のM君という学生と五人で食事に行った。いろいろ話ができた。そのあいだもずっと、授業で話ながら考えていたことを反芻していたのだが。
(9:32 Jun. 6 2008)
Jun. 4 wed. 「また授業をした」
■水曜日は多摩美の上野毛校舎で「戯曲」「シナリオ」を教える講座を非常勤でやっている。夕方の六時からはじめ、終わったら、夜の十時になっていた。働いたなあ。熱心に教えてしまった。この授業は二コマ連続であるので、通常は九時十分までだが、今日中にやらなくてはいけないことがあって出席した学生が提出した課題について一人ずつ検討してゆく。終わらないんだよ。ぜんぜん終わらない。途中、休み時間があるがそれも無視して授業をぶっ通しで続ける(この授業は毎回休憩なしだ)。まあ、芝居の稽古をしていることを思えば、べつにたいへんではないのだった。教えながら自分でも学ぶことが多い。というか、話をしながら、戯曲の書き方をこちらが学んでいるような気分になる。書き方を教える方法がもっとあるんじゃないかと考えつつ。それはしいていは、自分が楽しめるかということだし、むしろそのことを通じて学びたいということ。
■その後も、相馬から、WindowsのIE7だと、不具合があるからCSSファイルを書き換えたといった指示のメールがいくつか来る。忙しくてそこまで僕も確認できなかった。うちのWindowsマシンもここんとこすっかり起動していないけれど、Windowsの映像関連のフリーソフトで使いたいものがいくつかあって試そうとしているものの、さすがに時間がない。学生が授業に持ちこむコンピュータがたいていWindowsのラップトップなので、学生が使い方に困っているときなど、ひょいひょいと手助けできるのも、Windowsが使えるからだ。あと、関係ないけどiPhoneがソフトバンクから出るというニュースに愕然とした。
■多摩美の授業を終えて家に戻ったのは、夜の11時ぐらいになっていた。食事をしたらすっかり眠くなる。いったん眠ってから、「考える人」の連載原稿を書く。それから、トマス・ピンチョンの文庫本『スローラーナー』の解説のゲラが届いていたのでそれもチェックをすます。あとはあしたの授業の準備。だいたい、毎週、火曜日ぐらいから大学の準備をしているので、まあ、一週間、ほとんど仕事をしているわけだし、授業のある日は、コンピュータや資料を抱えて教室を移動するのがけっこう大変だ。で、木曜日の「サブカルチャー論」の授業が終わったあと、TAをしてくれているK君やT君とのんびり話をするのがなにより気持ちが落ちつく。先週は、それに、写真部の学生が二人加わり、話をするのがとても楽しかった。写真部で、まだ二年生だという学生が、いろいろ考えていてなんとも頼もしい。で、その写真部でこんどゼミのようなことをすることになった。テーマは「写真とサブカルチャー」。それも楽しみだ。
■時間があれば授業のための読書。このところ「創作物」というか、小説を読んだり映画を観ることより、バルトを読んだりとかそういった類のものばかり読んでどうもいけない。小説を読まなくてはな。青山監督が、最近は思想書など読まないと言っていたが、創作者としてはなによりもそれが大事なはずだ。だけど、授業のための読書もけっこう面白いから困る。ところで、この左に各ページに飛ぶメニューが並んでいるけれどもう10年近く前に作ったもので、なかにはなんのことだかわからなくなっているものもある。たとえば、「Qvism」というページがあるけれど、これははじめて手にした、「QV10A」というおもちゃみたいなデジカメで撮った写真を並べるページだ。で、「キュービズム」とひっかけて、「Qvism」というタイトルを思いついたという、ただ、その思いつきだけだったんだよ。中身がなんにもない。しかも、その「QV10A」はいまではもう手元にないのだ。どこにいってしまったんだろう。少しずつ、サイトを更新し、新しくしてゆこうと思うのだった。
(10:18 Jun. 5 2008)
Jun. 3 tue. 「新しい六月」
■日曜日(6月1日)に相馬が家に来て、このノートのページなど、サイトのリニューアルに際し、新しくデザインしてもらったページのデータを受け取ったり(もちろんデータは手渡しするようなものではなく、無線LANを通じて相馬のコンピュータから僕のコンピュータにあっというまにコピーされたわけだが)、いくつか技術的なことを教えてもらった。それでいろいろなことがわかった。こういう仕組みで新しいスタイルのウェブは動いているのか、と。きわめて論理的に構築されている。これは便利だとつくづく。相馬にはとても助けられた。
■そんな作業をしつつ、また大学の授業のために予習をしたり、準備のための作業をし、肝心なサイトの更新作業はというと、このノートが書けなくてちっても進まなかったわけである。「メンバーのページ」は更新したけれど(とはいっても、「ただいま準備中」がかなり多い)、トップページにあたる「PAPERS」はもうデザインはできているが僕が文章を書かないばかりに更新できないままだ。更新していないあいだ、「考える人」(新潮社)のN君から原稿の催促があったが、このノートが更新されていないのを見て、どこかに行っているのかと問い合わせのメールをもらった。申し訳ない。以上のような理由でノートが更新できずにいたのである。しかも、原稿も書けない。小説のほうも、それ以来、ちっとも進まない。ただ大学はだいぶ落ちついた。落ちついて授業ができるようになってきた。まだ読むべき本は数多いが。
■月曜日は、東京芸術大学の教授をなさっているWさんをはじめ、「取出アートプロジェクト」の方たちにお会いした。その公募展の審査をやることになったからだ。公募で選ばれると、そのアーティストが、取出にある団地の一室を一ヶ月間借りることができ、そこで制作ができるという。それいいなあ。僕がやりたくなった。美術が中心なのだろうけど、パフォーマンス系の作品も公募している。演劇をやっている人も、やっていない人も、ダンスの人も、そうじゃない人も、とにかく応募したらいかがかと思った。話を聞いていたらとても興味がわいた。審査は夏。それが楽しみになってきた。やっぱり、夏だよな。夏、最高。その夜、鍼治療。腰が危なかったんだよ。爆発寸前だった。これで一安心だ。で、きょうはNHKのNさんに会って食事をしながらいろいろ話しをする。僕としては珍しく、毎日、人に会っているが、それぞれ刺激的だったのである。やっぱり、人だよな。人、最高。
■といったわけで、サイトのリニューアル進行中である。メンバーのページには、遊園地再生事業団の新しい連絡先も記されていますのでよろしくお願いします。というのも、今年の年賀状にその連絡先を記したにもかかわらず、いまだに旧住所への連絡が絶えないものですから、よろしくお願いしたい次第なのです。といったわけで、心機一転だ。やっぱり、心機一転だよな。心機一転、最高。それより原稿を書かなくてはいけない。なんかほかにも書きたいことがあったんだよな。そういうことだったのかよ、って発見が、なにかを読んでいてあったのだ。思い出したら、また書こう。メールをいろいろいただいております。ありがとうございます。返事ができなくて申し訳ない。
(4:13 Jun. 4 2008)
5←「二〇〇八年五月後半」はこちら