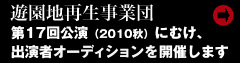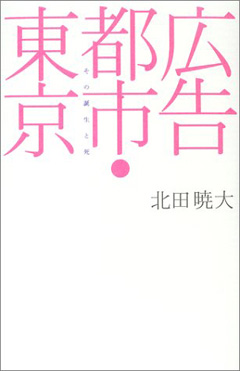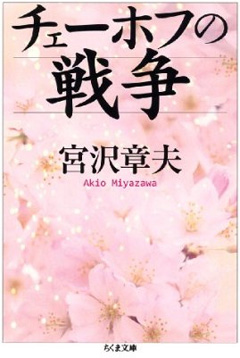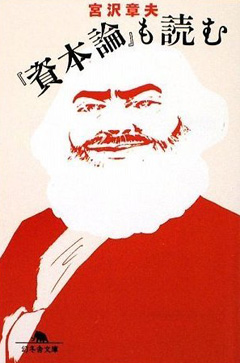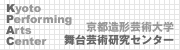Aug. 15 sat. 「ライジングサンに行ってくる」
■八月十五日。この国にとって特別な日。これから北海道に向かうのである。ライジングサンだ。眠い。こんなに早起きして、しかも、早起きした日はたいてい昼に眠るという生活習慣だから、夜まで大丈夫か心配だ。僕の出番は夜の10時なのである。だめだろう。だめにきまっている。とにかく北海道に着いたら、予定ではそのまま会場にバスで向かうことになっているがすぐにホテルで、仮眠をとろうと思う。仮眠を取って本番の「赤塚不二夫論」と「ライジングサン博士・しりあがかり寿」のステージに万全の体制でのぞみたい。
■東京に戻るのは17日の予定。少しだけでも北海道を満喫したい。というか、前日に北海道に行き、ライジングサンを楽しんでから次の日の本番を迎えるべきだったよ。当日入りって、俺、ほんとにだめなんだ。なにもできないのだ。眠いだけなんだ。それを忘れてスケジュールを先方に任せてしまった。だめだと、ほんとに本番中、ただぼーっとしている人がステージにいるだけになってしまうからな。しりあがりさんにも申し訳ないのだ。
■昨夜は「赤塚不二夫論」の素材を作り直していた。少し長い。まあ、時間が延びるかも知れないけれど、ぼーっとしている人が時間が伸びるのだから、これはもう、どういうことになるのかわからない。それにしてもライジングサンをもっと楽しみたかったのだがなあ。とにかく北海道についたらすぐにホテルに行き、寝るぞ、俺は。断固、寝る。誰がなんといおうと寝る。こうし書いていても眠い。
■というわけで、遅刻してはいけないので、もう家を出よう。では、また17日に。向こうで更新ができたら更新もしますが。
(8:10 Aug. 15 2009)
Aug. 13 thurs. 「夏はこれからが佳境だ、気分的に」
■明け方から、午後にかけて筑摩から新しく刊行予定の単行本の直しを完成させる。メールで原稿を送ったがなんの返事もない。お盆休みか。そういうことか。河出書房新社からは、引用部分などを直したまたべつのゲラを送ってくれたとのことだが、なぜか届かない。お盆休みだからか。そういうことだったのか。もう全国いたるところがお盆である。お盆気分である。
■わたしは北海道の「ライジングサン」に備え、夜、鍼治療に行きからだの調整をしたのである。もう万全だ。これでやるべきことはやりつくしたと思っていたが、肝心の「赤塚不二夫論」をまた新たに直そうと思ってそれを忘れていた。このあいだと同じことをやるのは自分が飽きるからいやなのだ。またちがうことをしたかったが時間がない。
■鍼治療の帰り。クルマで小さな事故。自転車の人に接触。申し訳ないことをしてしまった。相手がさほど怪我がなかったから幸いだったが、気をつけなくてはと、より運転に慎重になろうとあらためて決めた。とくに住宅街は危険だ。自分がしっかりしていることだ。自戒。
■その後も読書はしていた。というより読みたい本が次々に現れる。鶴見俊輔の『限界芸術論』は、いまさらいったいなんだと思われるでしょうが、僕が問題にしている「サブカルチャー」との接点はないかあらためて読もうと思ったしだい。文庫本版の解説で四方田犬彦氏は「限界芸術」について、「マージナル(marginal)」という言葉を使って語る。あ、ここだと、授業ではすでにロラン・バルトの話はしていたが、「限界芸術」「ロラン・バルト」からあらためてまたべつのことを考えようと、なにかひらめいた。それはべつに、多くの研究者による既出の研究成果とはまた異なる視点からの論考にしなくては、僕が考えることの意味がなく、それはつまり、「笑える」ということのはずだ。
■そうやって、つい本を読みこみ、夜が明けて外が青白くなってゆく夏の日々。気持ちがいい。ライジングサンのある日は15日の朝11時の飛行機で北海道に向かい、出番はたしか夜だ。こんな生活をしていて大丈夫なのか。眠くならないかそれが心配である。俺、ほんと眠いと、ぜんぜんだめだからな。
■夏はこれからがいよいよ佳境である。
(5:23 Aug. 14 2009)
Aug. 11 tue. 「落ちついて本が読める夏」
■もう今週末には北海道に行く。「ライジングサン」である。そのまえに、なんとしてでも二冊の新しい単行本の仕事、「座・高円寺」の講座のこと、秋からの大学の準備をある程度まとめて心おきなく出かけたかったが、あっというまに時間が過ぎてしまったことに唖然としている。
■北海道を心ゆくまで楽しみたかったのだがなあ。仕事のことがひっかかってなにか落ち着かない。何年前かのライジングサンは今回と同様、仕事だったとはいえ、なんだかわからないほど楽しかった。あのころは暇だったのだろうか。初めてのフェスに興奮していたのかもしれない。でも、今回はしりあがり寿さんと一緒なのが楽しみだ。あの人の、人を穏やかな気分にさせてくれる力はいったいなにごとなのだろう。不思議でならない。
■そんな2009年の夏である。いわゆる「ゼロ年代」ももう終わる。とはいえ、では「ゼロ年代」がいつはじまったか、その議論はいろいろだと思うし、いかにも「ゼロ年代」だと実感したのも人によって異なるだろう。だが、それを印象付ける「出来事」がこの何年かのなかにきっとあったはずだ。2005年の小泉政権下による自民の圧倒的な総選挙勝利もまたひとつの時代の区切りではあった。文化の領域ではなにかなかっただろうか。振り返るにはまだ早い。そんなとき、「STUDIO VOICE」の最終号が発売され、特集は「ゼロ年代総括」だ。それを手にしたとき、なにか既視感のようなものを抱いた。いつだったか同じようなことを経験した気がする。
■僕の個人的な感想では「ゼロ年代」はどうでもよかった。「STUDIO VOICE」の最終号が総括し一区切りがついてせいせいした。この「感じ」が、七〇年代が終わったときと似ている気がする。僕にとっての七〇年代は不遇だったし、ゼロ年代もあまりいいことがなく、総括され、片付けられる感じ、そのときの個人的な感触が似ていると思えてならない。それにしても、「STUDIO VOICE」は読みづらい。人を寄せ付けないかのようなデザインは意図されたものなのか。少し前の号で「ミニマルミュージック」の特集があったがどうしても落ちついて読めなかった。休刊になっても仕方がないのか。あるいは雑誌というものの役割が終わりつつある時代なのか。でも、雑誌好きとしては、まだまだ雑誌を読みたいと思っているが。
■地味に仕事。いっこうに終わらず。書いても書いても、終わらない。いやになる。学生からメールをもらった。去年は精神的に調子が悪くて後期を休学していたKという学生。今年の夏は元気そうでなによりだ。しかも、ものすごい勉強家で、いまは大学のほかに、ダブルスクールを受けており、ある大きな目標に向かい邁進している様子。すごいな。そんな忙しいあいまにメールをくれるのでなにか話してあげたいと思うが、僕のほうもあまり余裕がなくて、ばかな話でもして気分をリラックスさせてあげたいが、人間、余裕がないとばかな話もできないものだ。
■深夜、気晴らしだと思って数冊の本を持ってファミレスに行き軽い食事をとる。食事というより本を読むのが目的。近くの席にけたたましく笑う女のいる若者のグループがいて失敗した。本に集中できない。ところで、北田暁大の『広告都市・東京』は筑摩書房に文庫化してくださいと働きかけようかと思った。で、読んでいると「八〇年代」というもの、あるいはあの頃、よく読まれた「記号論」(をはじめとするニューアカデミズム)の本が、その時代における「都市」の(広告代理店的な、西武セゾングループ的な)意味化といかにシンクロしていたか、奇妙なこのシンクロこそが「八〇年代」であったと思いあたることが次々語られ、面白くてしょうがない。なるほど。
■いっぽう、小熊英二の『1968』はネット上でいろいろに批判されているけれど、批判の論点はあまり新鮮味がない。佐々木中『夜戦と永遠』(以文社)を読みはじめる。労作。ヤフーオークションで九〇年代半ばのCDを大量に買う。たいてい五〇〇円ぐらい。毎日のように、アマゾンか、ヤフーオークションで買ったものが家に届く。
■「ゼロ年代」のことを考えよう。まずは、「ゼロ年代」はいつはじまったのか、という問いから。まあ、表向き大学の授業のためだけど個人的な興味もあります。でも、そんな最近のことはともかく、あらためて世界史を勉強しておかなくてはね。それにしても、「座・高円寺」の戯曲の講座が憂鬱だ。
(12:20 Aug. 12 2009)
Aug. 10 mon. 「仕事をしている」
■携帯電話(iPhoneだけど)に「新潮」のKさんから留守電が入っているのにようやく気がついた。留守電を再生しないのでつい忘れてしまうのである。小説だ。小説だ。断固として小説なのである。そのためにすましておくべき仕事がある。
■それはそうと、すでに単行本として刊行された『資本論も読む』と『チェーホフの戦争』の文庫版(それぞれ、幻冬舎、筑摩書房)がもう店頭に並んでいるとのこと。まだ読んでいなかった方はこれを機会に手にとっていただきたい。これまでのエッセイとは異なるテイストですが、これも私であり、しかも渾身の著作である。単行本を買った方も「あとがき」など読みどころもあります。多少、手直した部分もあります。ぜひ買っていただけるとありがたい。
■文庫本で思い出したが、北田暁大の『広告都市・東京』はなぜ文庫にならないかだ。それ以前の北田暁大の著作『広告の誕生』は岩波の現代文庫に入っているのでもしかしたらまた岩波から出るかもしれない。あるいは『広告都市・東京』はかなりすぐれた論考だと感じるものの、絶版のままにしているのは著者が納得いかない部分があるからだろうか。あるいは時間的な変化に内容が耐えられない部分があるとか……うーん、そう感じない部分がないわけではないにしても、刺激的な本なんだからもっと多くの人に読んでもらうため……古書店を変にもうけさせないため……早く文庫化されることを願うばかりだ。「80年代地下文化論」を出したとき参照しておけばよかったといまごろになって思う。
■昼過ぎ、少し外へ出たが、それ以外はほとんど本を読んでいた。秋からの授業のための予習。あと、やらなくちゃいけないのは「座・高円寺」の戯曲レクチャーのための勉強だが、憂鬱だ。ものすごく憂鬱である。毎週二時間も授業をできるわけがないじゃないか。そのことをまず第一回目の授業で話そう。「俺は、あんまりしゃべらないから、むしろ、きみたちがしゃべれ」と宣言する。そして戯曲とは関係のない話をしよう。それでも演劇について、戯曲について話す努力はできるだけするつもりで(自分で言うのもなんだが、こういったときの私の律儀さ、まじめさはいったいなんでしょう)勉強はしておこう。そんな夏である。勉強ばかりの夏である。
■次に出る単行本のまとめ。少しずつ進行。あるいは秋からの「都市空間論演習」のために、次のフィールドワークの課題をどういった切り口にしようか考える。そのためには自分もそこに足を運ぼう。これまでも、各街区(高円寺、原宿、六本木ヒルズなど)はかなり回ったし、コンセプチャルなフィールドワークとして、「東京のたたりを探す」とか「自転車に乗る」「公園」「地下街」などいろいろやり、かなりやり尽くした感はあるので、同じことをするのは、つまり僕が飽きるから、新しいことを考えなければだめだ。学生と街を歩くという方法もあるか。
■それとはべつに、遊園地再生事業団の活動も本格化してゆかなくてはならず、秋に次回公演のオーディションがあるけれど、ほかにもラボ的な活動として、新しい外国の戯曲を読む会を開こうと思っていて、これは上村が積極的に動いている。上村はいまベルリンに向かっている。一方、田中夢はこの秋、川崎市アートセンターで阿部初美といういま注目されている若い演出家の舞台に出る。あちらから出演の依頼があった。それがとてもうれしかった。自分の舞台に出ている者が、なんらかのスタイルで認められるのはすごくいいことじゃないか。
■たしか、阿部さんという方は、太田省吾さんに師事し、このあいだ『更地』を演出したんじゃなかっただろうか。次の舞台にも期待がもてる。見たかったんだけどな、お知らせとかそういうものをまったくもらわなかったから見過ごしてしまったのだ。あとで人から教えられた。というか、いま遊園地再生事業団は、制作体制ががたがたで、住所の変更など、きちんと広くお知らせしていないのでむしろこちらがだめなのだ。
■時間はあっというまに過ぎて行く。本が出たらその印税でまた新しいコンピュータを買おう。大学の授業で使っているラップトップがさすがに処理速度が遅くてときどきもたつくのだ。あるいは素材を作るMacProの処理速度もいらつくことがときどきある。仕事道具としてのコンピュータと,資料となる本やDVDは必須。酒も飲まなければ、煙草も吸わない。ギャンブルもしない。遊ばない。ディズニーランドにも行かない。Wiiもしなけりゃ、ドラクエもしない。海にもいかず、山にもいかず、ひたすら勉強である。だったらいいじゃないか、それくらいのことに金を使ったって。夏なんだし。
(13:25 Aug. 11 2009)
Aug. 9 sun. 「夏を味わう」



■その後もノドの調子はもうひとつだった。で、ようやくきょうあたりから普通に声が出るようになった。そうこうしているうちに、一週間ぐらい経ってしまいいったいなにをしていたのか自分でも不思議で仕方がない。こつこつ仕事をしていたのである。ごく地味にこつこつだ。
■まず、佐々木敦さんが主宰する雑誌「エクス・ポ」に掲載される予定の岡田利規君、佐々木さんとの鼎談のゲラの直し。けっこう時間がかかった。さらに、筑摩書房のウェブで連載していた「テクの思想」のまとめ。連載が終わったらすぐに単行本にする予定だったが、いろいろ忙しいという理由でなにもしておらず、ぐずぐずこんな時期まで伸びてしまったのだ。ようやく直しをする。直していたら面白くなってきたものの、連載はたいていそうだがつまらない回がある。どうしたら面白くなるか思案中。あるいは、河出書房新社の『時間のかかる読書』の直し。ゲラに鉛筆で書き込みを入れたり、訂正したりで、ゲラがものすごく汚い状態になってしまった。わかりづらいところに手を入れ、面白くする最後のあがきのような作業。そういった仕事を連日。
■5日(水)は夕方、仕事を少し休み気晴らしにクルマを走らせ多摩ニュータウンにある巨大なブックオフへ。本の棚を見て回るが悲しくなるほどろくな本がない。ブックオフに期待するのがそもそもまちがってる。それでもCDを一枚。画集など(けっこういい画集が売れないせいだろうか、400円の値がついていた)。で、気がつくとiPhoneに桜井圭介君からメッセージが届いていた。六本木のスーパーデラックスで、山縣太一、大谷能生の二人のダンスがあるから見に来ないかとのことだったが、そのころ僕は、なぜか八王子にいたのだ。かき氷が食べたくて多摩ニュータウンあたりの、かき氷が食べられるファミレスを探していたら道に迷い八王子に着いていた。以前からその催しがあるのは知っていたが忘れていたのだ。
■その夜、来年の遊園地再生事業団のフライヤーのための写真を撮っていただきたいとお願いした写真家から連絡があったと、制作の黄木からメールが来ていた。快諾してくださるとのこと。うれしい。素直にうれしかった。鈴木理策さんである。今度、お会いすることになった。
■6日(木)。やはり家で仕事をしていたが、河出書房新社のTさんと、『時間のかかる読書』に付される「サブタイトル」についてメールで議論。僕は、むかしからそうですけど、いかにも、というか、あざとい笑いがどうも苦手で、そこになにか工夫が必要になる。あざとくならず、しかし、どこか面白い言葉がいい。新潮社の「考える人」の連載タイトルは「考えない」だ。最初の候補は、「考えない人」だったが、それだとどうも「狙い」が感じられる。あざとい。だからきわめてあたりまえの言葉「考えない」にした。その後、『時間のかかる読書』のサブタイトルのほうはいろいろ検討したがどうもうまくいかない。いい言葉が思い浮かばない。
■早稲田の学生からメール。学園祭の催しについて相談にのってほしいとのこと。演劇の催しらしい。短い芝居をいろいろな集団がオムニバスのように次々と上演するとのこと。どんな芝居をするつもりだ。あと、俺の芝居を観ているのだろうか。観ていないで声をかけてくるとですね、あの、僕の演劇の方向と彼らの演劇の方向がかなりちがうとしたら、アドヴァイスにならないと思う。たとえば、ミュージカルだったら、俺、お手上げである。
■鈴木理策さんにメールで感謝を伝える。こんど会うことになった。もちろん鈴木理策さんの写真はいくつか観させてもらっているが、以前、ある雑誌が、僕の舞台の取材に来たとき雑誌用の写真を撮ってくれたのが鈴木さんだった。その写真が、いままで自分が撮られた写真のなかでいちばんよかった。満面の笑みを浮かべていたわけですよ、わたしは。それがすごくいい。なんだったんだろう。撮影者によってこんなにもちがうのかと思った。
■7日(金)。早稲田の図書館で、北田暁大の『広告都市・東京』を借りる。というのも絶版になっており古書も三千円近くで、買うべきかどうかで悩んだ末、図書館にあるなら借りようと思った次第です。二〇〇二年に出た本だが図書館のそれはぼろぼろだ。そうとう読まれた形跡があるけれど、それにしたって本の扱いが雑すぎないか。しかもなにか変な匂いがする。もう少し大事に扱えと言いたくなった。まあ、本の外観はともあれふつうに読めるから問題はない。そんな数日、芸能界をにぎわすドラッグ関係のニュース。いろいろ背後にあるどす黒いものを予感し気分が悪くなるのと同時に、そこんとこどうなんだ、というひどく下世話な好奇心もある。
■あと、あれですね、ネットに流れる情報によれば酒井法子はテクノ好きで(トランスか?)、レイブにもよく行っていたとのこと。ドラッグをきめて踊りまくっていたというが、そこからどうしたって最近の私の興味であるところの「90年代サブカル」について考えざるをえない。現象としての「その時代」ではなく、いまなぜそんな「酒井法子」が取り沙汰されたか、というのも、単に夫が覚醒剤で捕まったというだけの偶然ではないと思うのだ。いまも響く「90年代サブカル」の残像が気になる。あるいは、またべつの芸能人が「MDMA」って「あの時代の渋谷」を象徴するようなドラッグで捕まったのも奇妙だ。なにかが終わることを示しているのだろうか。けっして、はじまりではないと思える。まあ、大げさに考えるのもばかばかしいほど、ばかやろうが跋扈しているという話だし、あと六本木ヒルズだよな、問題は、なにしろ人ひとり死んでるし。
■夕方、髪を切ってもらいに青山へ。気持ちがいいくらいの坊主頭になった。さっぱりだ。それにしても青山周辺が激変している。有名ブランドのショップが並び、さらに一本、奥の道を入ったかつては住宅街だった土地もいまでは、ショップが次々とできている。この変容の都市性に驚かされつつ、『広告都市・東京』における北田暁大の論考を思い起こす。
■8日(土)。ある打合せで新宿へ。土曜日の新宿は人でいっぱいだが、渋谷とはまた異なる。アルタの横にある喫茶店に入ったが店員がみんな外国人だった。打合せを終えて紀伊國屋書店へ。売り場にいるとそこにある本をぜんぶレジに持って行きたくなる衝動にかられる。小熊英二の『1968』の下巻のほか、何冊か買う。本日(9日)は散歩。初台の先、かなり歩いた場所にあるカフェに入って食事をした。カフェのソファですっかりくつろぐ女がいた。靴を脱ぎ長いソファで横になりながら雑誌を読んでいる。くつろぎすぎじゃないのか。散歩の帰りは雨に降られる。
■小熊英二の『1968』を読んでいる。六〇年代の半ばのいくつかの大学における闘争の記述はあまり面白くない。ただ、「自主講座運動」のはじまりと、その限界については興味がある。というのも、僕が大学に入ったころもまだ「自主講座運動」はかろうじて生きていたこともあって懐かしいのと、現在の大学を考えるうえでも意味があるからだ。
■いろいろなことができるような気持ちのいい季節である。なにしろ夏だからな。だからって、海へ、山へということはいっさいない。地味に本を読む。あとは考えること。
(16:12 Aug. 10 2009)
Aug. 4 tue. 「成績表を出してすっきりした八月」



■数日前からノドの調子がひどく悪かったのである。
■以前から少し疲れると声がかれることはよくあった。この一ヶ月それが顕著になり、声がかすれ、いよいよ話すのも大変になったのはこの数日。去年、入院していた東京共済病院に行った(その後、手術を受けるため五反田のNTT病院に転院したのである)。耳鼻咽喉科を受診するなんて子どものころ以来だ。鼻からファイバースコープを挿入された。医師の診断によればノドにポリープ状の炎症ができているとのこと。煙草を吸っていた者がよくなる症状だというが、煙草をやめてからもう一年以上になり、なんでいまごろそんな症状が出たか不思議である。
■いまでは誰もがやっていると思うが少し身体の調子が悪かったらネットで調べる。あらかじめわたしもネットにあたっていた。「声がかれる」という症状でもっとも深刻なのは「喉頭ガン」だ。まあ、そこまでひどくないようでほっとしたが、今年の四月からの授業でノドを酷使していたのかもしれないと思いあたるのは、まず、授業のとき、やけに早口になっていることだ。あるいはやけに熱弁するときがある。なにをそんなにムキになるのかと思うような話し方になる。しかも、俳優のように腹筋で声を出していないのだな。そういった訓練を受けてこなかったからノドに負担がかかる。
■薬をもらって帰宅。帰宅するまえに東中野へ。ちょっと食事だ。夏の暑さが気持ちいい。まあ、それには、学生のレポートを読み終わり、きのう(3日)成績簿を大学に出したという達成感があったのが大きい。
■読んだ、読んだ、不眠不休で読み続けた。うそだけど。学生のレポートである。「サブカルチャー論」はたしか受講者が285人くらいいて、未提出者が5人ぐらいだったから、数えていないがおおよそ280人分ぐらいは読んだのだと思う。それであらためてわかったのは学生たちが「サブカルチャー」をどう定義しているかだ。というか、一般的にどう「サブカルチャー」という言葉が受容されているかになるが、要するに「マジョリティ(=多数派)」に対する、「マイノリティ(=少数派)」であり、だからテレビで見られる「人」や「もの」、あるいは「文化」が、「メインカルチャー」で、そうでないものは「サブカルチャー」ということになるらしい。
■まちがってはいないけれど、それだけでは正しくない。というか、もっと大きな「文化の諸問題」はそうした一面的な解釈では理解できないだろう。「サブカルチャー」は日本語では基本、「下位文化」と訳される。だから、「サブカルチャー」の対義語は、「ハイカルチャー(=上位文化)」だ。「上位」に位置する「文化」が、「全体」を支配している状況が前提としてあり、それはつまりヨーロッパが中心だった世界地図だ。「下位文化」は中心から見た周縁に存在するとされてきたが、考えてみれば、それこそ中心からの視点だったので、たとえば、中南米で音楽を楽しむ者らは自分たちが「周縁」であるとは考えてもいなかったし「下位文化」という概念がそもそもない。つまり「サブカルチャー」における「受動性」など本来的に存在しなかった。つまり、勝手になにを言われたって関係ない人たちがいたということだ。
■「サブカルチャー」の萌芽を一九五〇年代と考えて授業で話したのは、アレンギンズバーグが自身がゲイであることを語るとき、当時のアメリカ社会の「マッチョ中心主義」に対して「能動的な外部」として存在することを意志したと読めるからだ。あるいは「白人至上主義」に対する黒人の文化もまた「能動的な外部」、あるいは「周辺」として存在しようとした(背景には公民権運動など政治性が強く反映していただろう)。こうした「周辺(ギンズバーグは「マージナル」という言葉を使っていた)」の文化が「能動化」した背景には一九五〇年代のアメリカ社会が世界でもっとも経済的に豊かだったことと無縁ではない(これはもう少し読解が必要だろうけれど、ただ、日本における「サブカルチャー的な現象」もまた六〇年代の高度経済成長以降に顕著になったとするなら、考えるに価する「前提」になると思う)。
■ともあれ「サブカルチャー」とは「下位」からの「能動性」のことだ。しかも問われるのは「能動性」の内容だ。学生の多くが定義するような「サブ」に対する「メイン」は、「メジャー(と呼ばれるような)」な「ポップカルチャー」だ。たしかに、そこにもまたべつの「能動性」はあるだろう。けれど、「ポップカルチャー」とも性格が異なるからこそ、「サブカルチャー」は、まさしく、「サブカルチャー」としてべつの色合いで確固たる「能動的」な存在を示すことになった。
■だとするなら、「異なる能動性」や、「べつの色合いによる存在」を正しく理解し、現象と本質を解くために必要な学術的な方法や領域はなにか。もちろん、「サブカルチャー」という言葉自体、そもそも社会学の研究のなかで出現したが、もう少し幅広く考える必要があると思える。なにしろ「カルチャー」のことだし。あるいは、「サブカルチャー」が内包する政治性も見逃せない。それらをさらに読むのが次の課題だと、前期の授業を終えてそう感想を抱いたが、というかそれを考えることが愉楽になっており、小熊英二の『1968』の「第2章」が面白いのも、そこに手がかりがあると感じたからだ。
■一方、「都市空間論演習」では、忘れていたことを思い出させてくれる学生のレポートがあった。『東京から考える』(東浩紀、北田暁大)のなかの、北田の発言が引用されていたからだ。
いまや来訪者は渋谷に意味や物語を求めてやってきているわけではない。そうではなくて、いろいろなモノやコトやヒトが、つまりは情報が集積している相対的に大きな情報アーカイブのようなものとして渋谷という都市を捉えているのではないか。(中略)……「渋谷よりも地元を好む若者が多い」というのも、渋谷が意味の供給源ではなく、情報アーカイブになっていることを示しているのではないか。情報アーカイブだからこそ、ドン・キホーテができたって構わないわけです。都市に意味や物語を求めるひとだけが、それに違和感を持つ。広告都市としての渋谷は完全に綻びてしまったと言っていいでしょう。(『東京から考える』P117-118)
これを読むと「都市」における「八〇年代」が完全に終わったと解釈もできる。つまり、「西武セゾングループ」的な文化の牽引力が力を失ったということだ(「おいしい生活」という広告コピーもいまはむかし)。僕はそれを、六本木の「WAVE」が閉店したとき強く感じた。ただ、「ドン・キホーテができたって構わない」「都市に意味や物語を求めるひとだけが、それに違和感を持つ」は、「下北沢がどんなふうに再開発されたって構わない」「都市に意味や物語を求めるひとだけが、それに違和感を持つ」という言葉にも変換でき、「再開発」に異議を申し立てることが「ノスタルジー」のような「物語性」へと単純に収斂されてしまうとしたら、それはあまりに紋切り型すぎる。「再開発」への反発には決まって「再開発する側」からそう応答されてきたのだから。
だから、「ドン・キホーテができたって構わない」ではなく、むしろ「積極的にドン・キホーテができたことを歓迎する層」が渋谷を変えたと考えるべきではないか。となると、「積極的に歓迎する層」にとっての「ドン・キホーテ」は「意味」であり「物語」だ。夏の早朝、海水浴に行くのだろうヤンキーファミリーがドン・キホーテで買い物をする。意外に早起きだな、彼らも。渋谷という街区の変化は、そんなヤンキーファミリーの夏の思い出として、彼らのなかに「意味/物語」を生成する。そうした変化が渋谷に出現したとすれば、都市だけで解ける問題ではなく、またべつの意味で「文化」についての問いが生まれるのではないか。
■といったことを考えていた。やっぱり愉楽として。あるいは、遊園地再生事業団のミーティングも開いたさ。あいまに少しずつ『時間のかかる読書(仮題)』のゲラチェックもした。気持ちのいい夏である。ようやく時間に余裕ができた。やりたいことがいくつもある。小説を書くぞ。とにかく書き上げよう、この夏のあいだに。
(0:29 Aug. 5 2009)
7←「二〇〇九年七月後半」はこちら