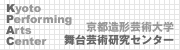Apr. 14 mon. 「神保町に行ったり、岸田戯曲賞の授賞式があったり」

■一番上の写真は神保町とまったく関係のない、このあいだボブ・ディランを観に行ったとき、会場近くにあったビル。なんのビルか知らなかったが夕陽のなかできれいだった。どこか黄昏を感じる建物だった。いつか廃墟になるのではないか。埋め立て地という土地、この建物、すべてが廃墟化する日がやってくるという遠くない未来の小説を書こうと思い、写真を残しておこうというか、資料のために撮った一枚だ。それにしても妙なデザインでなんの建物なのだろうと疑問に思っていたのだった。
■先週は、「1964年のサミュエル・ベケット」の原稿を書き上げ、ボブ・ディランとバート・バカラックのライブへと出かけ、途中、やついにも会ったしで、いろいろ疲れた。いや、やついは好きですけどね。週末は休もうと思っていたら、WOWOWで映画をたて続けに見、なかでも『華麗なるギャツビー』は目が疲れたよ。あの、俳優、トビー・マグワイアのアップになって困惑する表情を見ると、いつスパイダーマンに変身するのか気が気ではなかった。ところでハリウッドの女優は、あまり売れていない人のほうがすごい美人だなと思うが、売れている人たちはなぜああもクセがあるのかと思う。あと、もう一本、日本に輸入もされていないどうでもいい映画を観たが、どうでもいい話もハリウッドにかかると軽々と映画にしてみせるから不思議だ。技術的なうまさはあたりまえ。だけど、ほんとどうでもいい映画だった。
■それと、長編小説を映画にする場合、よほど注意しないと陳腐なお話になり浅薄になってしまうのだと『華麗なるギャツビー』を観ていた。まあ、派手だったけど。目の楽しみはあったものの。その目が疲れたが。


■そして、受賞作『ブルーシート』の一部(といってもかなりの長さだったが)を「福島県立いわき総合高等学校」の、当時、その上演をしもう卒業してしまった男女9人によって演じられた。とてもいい作品だった。僕はもちろん、戯曲しか読んでいなかったけれど、これはやはり奇跡が起こったのだと思った。あと、上演中、飴屋さんが、いちいち椅子を動かしたり(椅子は最終的にガレキのように積み上げられた)、背後にあるカーテンを動かしたりと忙しく、その姿がすでにパフォーマティブだった。飴屋さんは、飴屋さん自身が表現者なのだとつくづく。なにせ、かつてグランギニョール時代は嶋田久作らと舞台に立っていた人なのだから。そして、作品の外側にいて演出している様は、『死の教室』のカントールのようだった。面白かったなあ。金屏風を取り去って会場の係の人に怒られたり、つり下げられていた岸田戯曲賞授賞式の看板を天井から取り外し、積み上げられた椅子のなかに投げ出す。やりたい放題。そして最後は、七尾旅人さんの歌で会は終了(二次会もあったが僕は欠席)。
■ほんとうに近来、稀にみる授賞式。そして『ブルーシート』の作品的な価値にあらためて心を動かされた。もっとたくさんの人に見てもらえたらと思う。それは奇跡だったのかもしれない。それを演じた高校生は卒業し進学した者もいれば、すでに就職した者もいる。これから演劇にどんなふうに関わるのか僕はまったく知らない。でも、ある瞬間、俳優であること、表現者であることによって、彼らが生む作品があってもいいと考える者としては、まさにその典型を観た思いがする。ほんとによかった。この場にいられたことが幸福だった。
■遡って13日、神保町のレコード屋めぐりの成果はそれほどなかった。ただ、もっと時間と根気があれば、なにか見つけられたかもしれない。とにかく疲れた。レコードを棚から、こう、持ち上げ、ジャケットを確かめる。気になるレコードがあったら細かいデータを見るなど、その一連の、かつてはあたりまえにやっていたことがひどく疲れる。ずっと立っていると腰が痛くなるし。4月いっぱいで閉店するという中古レコード屋さんに行き、何枚か買う。950円。お得。
■そういえば、岸田戯曲賞授賞式の会場で、九龍ジョー君から声をかけられたのだが、たとえば渋谷のシアターDでやった「笑いについての講義」みたいなものを本にまとめないかという話。面白そうだな。それで家に帰ってからゆっくり考えたのだが、それはつまり、小林信彦さんの『日本の喜劇人』以降の、「喜劇論」、ただしもう世界には「喜劇」は存在しないかもしれないが。たとえば、小林さんが書かなかった部分の持つ笑いについて、「三木鶏郎と日曜娯楽版グループ」のこと(この資料がヤフーオークションに出ていたが買いそびれた)、そして、「モンティ・パイソン」が日本に与えた影響、80年代以降、高度情報化社会がもたらした笑いについてなど、語るべきことはいくつかある。それを本にまとめるのが僕にとって、なんになるかわからないものの、ほかに書ける人がいないので、俺が書くしかないかあと思っているのだが。いい出版社から出したい。岩波とか。いやべつに権威主義じゃなく、それも冗談のような気がして。
■そして、その本のなかに、先日書いた「1964年のサミュエル・ベケット」も入れたい。というのも、ベケットのことを中心に書いたつもりだが、読んでみると、バスター・キートンへのオマージュのように思えたのだ。僕はやっぱり、チャップリンより(もちろんその芸の見事さには感服するのだが)、キートンが好きだ。素晴らしい喜劇人だ。そのキートンにベケットが1964年に会いに行ったんだよ。初めて、そして生涯で最後のアメリカ行きによって。その年、ビートルズが全米デビュー。アメリカンポップスの世界は大きく変わった。山下達郎さんと、大滝詠一さんの「新春放談」のたしか、2004年の回だったかで、62年、63年のロックンロールリバイバルの背景にあるのは、ケネディイズムではないかと大瀧さんは発言している(1963年、ケネディは暗殺されている)。
■1964年はなぜ出現したか。ビートルズはどこからやってきたか。そしてベケットは同じ年になぜアメリカに渡ったか。このあたり、60年代の社会の煮詰まった空気と無縁ではないと思う。その背景にはベトナム戦争もあるのだし。モンティ・パイソンが誕生したのは1969年。なぜそれは出現したか。なぜイギリスだったのか。時代と併走する笑いとしてのモンティ・パイソンは知識人たちによって作られた。その意味とは? 考えることはいくらでもある。
■小説を書く切実さはどのようにして生まれるだろう。いまそのことがいちば悩むところだが。遊園地再生事業団の未来はどうなっているのか。またメンバーを集めてミーティングだ。演劇、文学、批評を平行してうまくやるほど器用ではないけれど、それぞれ、集中して取り組もうと思っているが。
(12:08 Apr. 15 2014)
Apr. 11 fri. 「町へ」


■木曜日(10日)のことから。
■午前中、病院へ。エコー検査のあと、24時間、心電図を計測する装置を胸につける。胸に貼り付けているうち、だんだんうっとおしくなってくる。
■その後、いったん家に帰り、バスで渋谷へ。神保町にあるレコード屋が今月いっぱいで閉店する。それでセールをやっているのを知ってそちらに行こうか迷ったが渋谷へ(東急ハンズで買い物)。というのも渋谷を歩いてみようと思ったからだ。このところあまり歩かずついクルマ(タクシーではなく自分で運転して。逆にタクシーには乗らなくなった)で移動してしまう。火曜日、ボブ・ディランのライブを観にお台場に行くのは新宿からりんかい線に乗った。電車はやはり面白いと再確認。新宿から、東京テレポートという聞き慣れない駅までが20数分で着いたのには驚いた。
■もちろん、他者からしたら「私も見られる対象」だが、勝手ながら人を見ることの興味深さはない。演劇をやっていると、たとえばワークショップやオーディションなど、いろいろな場所でたくさんの人に会う。かなりの人に会っていると思うが、男女を問わず、町には魅力的な人がとても多い。いままで会ったことのないような魅力を湛えている人に会う。それはべつに、美人とか、かっこいいとか、そういうのともべつだし、変な人というわけでもなく(もちろん変な人も好きですけどね)、怖い人ともちがう。得も言われぬ魅力だ。舞台にすぐ出したい気持ちにさせられる。というか、そんな人にもっとたくさん会いたい。舞台をする楽しみとはそのことのような気がしている。たしかに演劇は「稽古の時間が長い」ので、ずっと一緒にいなくちゃならない。そのあいだ誰もが耐えられるとも思えない。だからって映像だからいいというわけでもない。なにしろ、誰かと会って、あらためてその人の、ぱっと見たときの魅力(それに気づく自分の勘のよさには自信がある)をよりいいものとして磨き提出する時間がほしいからだ。人を発見する自信は子どものころからの蓄積のように感じる。よく映画や舞台など、さまざまなものを見てきたからだし、仕事で、さまざまな俳優や芸人に会ってきたからだ。
■で、本日(11日)は心電図の器具を外しに午前中病院。夕方、歯科医。で、夜、六本木のミッドタウンにある、「Billboard LIVE Tokyo」でバート・バカラックのライブを観る。一週間に2回も(9日にボブ・ディランを観た)ライブで外に出るなんてことはもう十数年なかった。バカラック、とてもよかった。これもSのおかげだ。大瀧詠一さんが亡くなられてから、彼とたびたび会うようになったのは、大瀧さんについて質問したいことがいくつもあるからで、というのもSが親族だからだ。いまは音楽関係の仕事をしている。詳しいことをあまり聞いていないが。
■だけど、人見知りなので、ライブには、湯山玲子さんや、野宮真貴さんと旦那さんがいらしたが、ずっと気詰まりだったわけだ、知らない人ばかりで。ライブが終わったらさーっと逃げるように会場をあとにした。でも、映画でも、演劇でも、音楽でも、終わったあとは、一人でものを考えたいのだ。そういえば、始まる前に、ミッドタウンの入口のところで、やついにあったのだな。なんかほっとしたな。やついの顔を見たら。
■家に帰ったとき、もう深夜の12時近くになっていたのは、バカラックのライブが始まったのが午後9時30分だったからで、この感じも久しぶりだ。大人の夜遊びだ。だいたい、ライブの料金が25000円だったからなあ。大人だ。ただ、「Billboard LIVE Tokyo」はいい店だった。ライブの前はバックのカーテンが開けられそこから六本木の夜景が見える。映画『ロスト・イン・トランスレーション』にも出てきた新宿パークハイアットの高層階にあるバーを思いだす。僕が見たのは白人の女性シンガーが歌っている姿だった。行ったことはないが。その奥にあるレストランで食事をしたことはある。パークハイアットに一日ぐらいは泊まってみたいな。といっても、家がわりと近いからな。歩いて行けるし。でも、金を貯めて、泊まるなら、いいホテルを選んだほうがいい。シーズンの京都はたいしたホテルでもないのに宿泊料を高くするから避けよう。大阪か、琵琶湖周辺に泊まるといい。同じ値段でもぜったいにいい。京都に近いし。
■そうだ、そんなことはどうでもいいんだ。私は勉強家にならなければならないのだ。夕方、いとうせいこう君と、市川真人さんが、後藤明生さんについて語る公開対談があるとTwitter知った。行きたかったが、歯科医が思いのか時間がかかりだめだった。勉強家の道は遠い。
■勉強と、それを元にした創作だ。うーん、五月から、あらためて忙しくなる。いろいろに忙しくなる。ことによると去年の秋にやったテレビのようなことをまたするかもしれない。その勉強もあるしな。歌舞伎の台本もあるんじゃないだろうか。
(6:50 Apr. 12 2014)
Apr. 7 mon. 「春だったなあ」

■考えてみたら、このノートを再開したのに前回は大滝詠一さんのことしか書かず、終わったばかりの僕の舞台『ヒネミの商人』についてまったく触れなかった。忘れていた。なんてことだ。みんなに助けてもらったのに。ほんとうに感謝するしかない。特に、笠木だなあ。企画を立てた段階からいろいろ相談にのってくれた。提言もしてくれた。ほんとうに感謝している。
■舞台についてはおいおい書いてゆくことにしよう。いや、『ヒネミの商人』のことだけではなく、この十数年のこととか、今後の活動について。遊園地再生事業団のこと。あと、『ヒネミの商人』を再演することでわかったこともある。「再演」とはなにかとかね。音楽のレコードやCDにおけるデジタルリマスターとか、そういったものとも異なるわけだし、「再演」にはさまざまな意味があると思う。ま、興行という側面も当然あるだろう。「当り狂言」という古い言葉もありますしね。人気が高いからなんども繰り返し「再演」されたから、その作品は「古典」として残る。シェークスピア戯曲を上演するのはべつに再演とは言わないのはなぜなのか。演出家がちがうからだろか。なにが、「再演」と「レパートリー」という考え方をわかつのか。
■そんなことも考えます、あらためて。
■さて、また更新が滞ったのは週末ずっと原稿を書いていたからだ。
■すでにTwitterではしばしば呟いているが、早稲田大学演劇博物館で4月22日からはじまる、『サミュエル・ベケット展〜ドアはわからないくらいに開いている』の図録への寄稿だ。依頼されたときにすぐ「1964年のサミュエル・ベケット」というタイトルを思いつき、その時点ではなにもわかっていなかった。なぜそんなタイトルが先に出たかというと、やっぱり大瀧詠一さんがらみになる。大瀧さんがこの三月、NHK-FMで放送する予定だった「アメリカンポップス伝」(すでに五日連続の放送をこれまで四シーズン放送してきた)の第五シーズンは、おそらくすでに大瀧さん自身が話していたように(あるラジオ番組で本人が口にした)、1963年12月31日までが語られ、そこで終わる予定だったのだろう。その翌年、つまり1964年の2月、ビートルズがテレビ番組「エド・サリバン・ショウ」に出演して全米に旋風を巻き起こす。おそらくビートルズの存在の意味、なにがビートルズを生んだか、どこからビートルズはやってきたかを大瀧さんは、「アメリカンポップス伝」という番組を通じて検証しようとしていたのだろう。聴きたかった。
■それで「1964年」がテーマになったわけですね、ベケットについて書くにあたっても。タイトルが最初にあったけれど、あとはなにも考えていなかった。『ヒネミの商人』の稽古は佳境に入りなかなかその原稿が書けなかったものの、稽古から帰って資料を読むと、1964年、ベケットが初めて、その年の夏、アメリカに行っていることがわかった。バスター・キートンが主演する『FILMS』(当然ベケットがシナリオを書いている)という映画の撮影に立ち合ったというのだ。なぜこんな偶然が起ったのか。ビートルズの全米デビュー(もちろんすでに何曲かはヒットチャートの上位に入っていたが)と、ベケットの初渡米が同じ年だったんですよ。いくつかの資料を引用してそのことの意味を問い、あるいは、『FILMS』を分析しつつ、せっせと書いていたのです。何度も書き直した。はじめに依頼があった字数よりずいぶん長くなったので削り、さらに繰り返し推敲しているうちに締め切りから破滅的に遅れたのだった。申し訳ないことをしました。なんとか許してもらいましたが。

■あるドキュメンタリーがテレビで放映されたのを録画したDVDを知人から受け取って観た。『書くことの重さ~作家 佐藤泰志』だ。正直、作品の全体が「文学」の情緒に流れているのではないかと少し疑問に感じつつ(いわば文学主義)、「書くことの重さ」についてあらためて考える。芥川賞の候補に五回、三島賞にも一回候補になったが、いずれも受賞に至らなかった。そして佐藤は、四十一歳で自ら命を絶った。
■べつに作家は賞を取るために小説を書くのではないだろうが、ある「成果」としての「賞」はある。あるいは励ましとしての「賞」があり、だからこそ、次の作品に臨むことが可能かもしれない。僕はそうだった。岸田戯曲賞を受賞したから、舞台をやらなくてはと思ったのは、がんばれと背中を押され続けてきたからだと思う。だから、劇作家だし、演出家だ。ではなぜ、小説を書くのか。
■『書くことの重さ~作家 佐藤泰志』を観て、佐藤泰志のことも、死について、佐藤の作品、文学のこと、そのドキュメンタリー内の再現ドラマに登場する芥川賞選考委員の描かれ方も、あまり考えず、やはり自分にとって書くとはなにかを問わざるを得ない。「重さ」として一面化していいのかということになる。「愉楽」ではいけなかったのか。佐藤にとって書くことは、重さであり、苦しみだったかもしれない……とはいえ、苦しくても誰にも同情してもらえない。なぜなら、普通の仕事をして生きている者のほうがずっと多いのだから。芥川賞が今年で何回目になるのかよく知らないが、そのたびに、かなりの人数が落選している。僕もその一人だ。候補に残らない者もかなりいる。それでも小説を書き続ける者もいるし、その後、まったく書かなくなった人たちもいる。「書くことの重さ」という言葉を多くの人は、「文学ってそんなにえらいのか」という感情で受け止めるのではないか。
■だけど、それでもなお、書こうとする。とても苦しい。水を張った洗面器に顔をつけてどこまで我慢できるかというあれに似ている。重く、苦しいことでしか、自分を表現できないとき、はじめて「書くこと」が生まれるが、そこまで切実さがない者にとって書くとはなんだろう。僕にはそれほど切実さがないよ。むしろそのことが重さになる。ただ、どうしてもいい作品だとは思えない小説に出会うと、またべつの切実さが生まれる。なんだこりゃという感じの、腹立たしさといってもいいが、うまいとか、へたとか、面白いとかつまらないとかじゃなくてさ、安易に俗情に寄りかかるというか、そんなふうな小説のくだらなさは、なんでもそうなんだけど、音楽でも、舞台でも、笑いでも、とにかくそのとき、なんとかしなくちゃという感情が生まれるわけだ。この切実さ。佐藤泰志が書くことに抱いた苦しさ、切実さ、重さとは異なるだろうが、どうしたって許せないものはあり、それはおそらく、佐藤の「創作の態度」への擁護になる。
■そんなふうにして、今年も春がやってきた。仕事をします。だんだんあったかくなったので散歩もしようと思います。レコード屋と古本屋をめぐろうと考えていますが。
(2:08 Apr. 8 2014)
Apr. 3 thurs. 「富士日記2.1再開」



■久しぶりの「富士日記2.1」です。ごぶさたしていました。これからは思うところあって小まめに書いてゆこうと思います。ぜひ読んでください。
■これからは書くと宣言してから、もう一年近くになってしまった。前回は沖縄に行ったという興奮のせいで気分が高揚していたから、「富士日記2.1」も続けて書くことができると考えていたのだ。だが、だめだった。やっぱり続かなかった。いまは原稿を書いているあいまになにを思ったか、あたまを休めるためにこれを書いている。というか、書きたいこともかなりあったという意味でもある。たとえば、昨年の12月になくなられた、大滝詠一さんについて書きたいことが山ほどある。もういまでは、ファンはみんな中年になってしまったのではないかという気がしないでもないけれど、それでもなお、大瀧さんの偉大さにいまさらながら畏怖するのだ。そのことをもっと伝えるべきだと思った。すごいんだよ、その仕事ぶりが。
■そして、その仕事と「勉強家」としての態度に学ぶことがたくさんあるとあらためて思い知らされ、私も「勉強家」になるためにこのノートを再開しようと考えた。これは考えるためのノートだからな。僕は書きながら考えがまとまってゆく。いま、書いている「1964年のサミュエル・ベケット」も大瀧さんのことを考えていなかったらそんなタイトルを思いつかなかったと思う。2014年3月31日の朝日新聞「ニュースの扉」の欄に、ナイアガラトライアングルで大瀧さん、山下達郎さんとも共演した伊藤銀次さんが、1970年代、大瀧さんが東京都瑞穂町(米軍横田基地のすぐそば、青梅線福生駅の近く)に作った「福生45スタジオ」でのエピソードなどを語っている。ほかにも興味深い記事は多いが、その記事の一部を紹介したい。
■伊藤さんは語っている。
ある物事や現象それ単体で楽しむのではなく、時間舳や場所舳などの様々な視点を駆使して、立体的、多面的に分析することの面白さでした。
それは例えば、ビートルズのレコードをただ聴いて『いい曲だなあ』で終わらず、彼らが最初にカバーしていた曲の原曲を探す。ポール・マッカートニーはリトル・リチャードを、ジョン・レノンはラリー・ウィリアムの曲を歌っていますよね。それらの原曲をたどっていくと、リトルもラリーも所属レーベルは、米国のスペシャルティー・レコードだと気づく。
「ボールとジョンは、あの時代、米国の黒人音楽専門のあのレーベルに目をつけ、アーティストごとに歌い分けをしていたのかなあ」という考えに至る。ビートルズが立体的に見える感覚です。
そんなことを、毎晩大瀧さんの家で、大瀧さん自身がレコードをかけて解説してくれる。「君は何もわかっちゃいない」なんて言いながら。当然、一からは教えてくれませんよ。断片的にレコードをかけながらヒントを出す。あとは自分え考えなさいよ、と。でもそれが楽しい」。
あー、その学校に行ってみたかった。経験したかった。
■べつの雑誌では、萩原健太さんが、大瀧さんがこうした分析を始めたのが中学3年生のときだったというエピソードを紹介している。僕も中学2年生のときに洋楽のレコードを買い始めかなりの量を所有していたが、後年、母親にすべて捨てられてしまうわけだが、しかし、自分の好きな曲の作曲家に共通点があり、さらに、イタリア系のシンガーだと気がつくことから分析を深めるなんてことを、中学生時代にやった記憶はないよ。せめて、CSN&Yのギターの音がおかしいので、いろいろ工夫したり、参照資料で確認したら、「Dチューニング」というものだったことに気がついたくらいだ。あとはぼんやり聞いていた。遡ることはしたが。ツェッペリンを聴けば、その前に、ヤードバーズがあるとか、この歌い手の前には、ライトニン・ホプキンスというカントリーブルースのシンガーがいてそのギターがかっこよすぎるのでコピーしたりなど。
■昨夜、大雨のなかコンビニまで行って買った「週刊文春」の小林信彦さんの連載を読む。大滝詠一さんへの追悼の言葉だった。70年代に僕はこの二人にかなり影響を受けていた。じつは大瀧さんに関していうと、『ロングバケーション』以降はあまり聴いていなかった(あまり好みではなかった)。今回、あらためて聴いたくらいだ。たとえば、「多羅尾伴内楽団」などすごくいいし、最初のソロ『大滝詠一』もいい。『ナイアガラムーン』がまたいい。「音頭」もよかった。というか、70年代、大瀧さんは徹底的に実験をしている時期だったのだと思う。それが『ロングバケーション』へと引き継がれ、あの大ヒットを生んだのだろう。そして実験のあいだの「研究」のすごさだ。音楽だけではなく、笑いや映画などへの熱中はただごとではない。クレージーキャッツへのリスペクトはすごいじゃないか。ほんとうに大瀧さんからさまざまな音源を紹介してもらった幸福を感じる。
■近年は、ラジオにおける「日本ポップス伝」と「アメリカポップス伝」だ。これはすごかった。ほんとうに面白い。その仕事の総体と、研究や仕事に対する態度や姿勢には頭が下がる。映画のロケ地探訪もすごいんだよな。公開されていないけれど、ある場所にあったものを少しだけ見せてもらったが、なぜこれ単行本にしないのかと思う。だけど、そんなつもりはさらさらないところがまた、すごいよ、大瀧師匠は。
■去年のシティボーイズ・ライブを観に来てくれた。楽屋を訪ねてくださり、声をかけてくれた。声をかけてくれたことに興奮し、緊張し、なにも話せなかった。もっと話をすべきだった。そのあと、近いうちに会いましょうと身近な人から伝言を受けていたのだ。会えるときに、会っておかなければだめなんだ。そのことの後悔はすごく大きい。
■そして、僕もまた、仕事を同じようにしてゆこうと思う。きちんと記録し、きちんと調べること、それは演劇だけではなく、音楽も、それから文学も同じだ。若いときには、喜劇と笑いについて徹底的に学んだと思う。それから三十代になるころ演劇について学んだ。そういうのが財産になる。いや、もっとやるべきことがある。というかもっと深く踏み入っていくことができるはずだ。僕の仕事はいまのところ主に演劇だから、そこをもっと深く考えることが必要で、大瀧さんが「日本ポップス伝」や「分母分子論」を語るときにしばしば例に出す、明治初年、この国が近代化するにあたり、日本の音楽がどのように成り立ったかという「日本歌謡史」の構造はまったく演劇と同じだ。そういう国だったのだなあ。
■といったことを考えながら、いまは、早稲田の演劇博物館で公開される『サミュエル・ベケット展 ──ドアはわからないくらいに開いている』(2014年4月22日(火)~8月3日(日)詳しくはこちら)のために、「1964年のサミュエル・ベケット」という文章を書いている。いい文章にしたいんだ。ぜったいに面白くしたいんだ。
(13:15 Apr. 4 2014)
7←「2013年7月前半」はこちら