|
|
 |
 |
| Sep.29 thurs. 「もう授業がはじまってしまう」 |
■忙しいので簡潔に。阪神優勝おめでとう。よろこんでいる関西人の、なにかでバカになってしまった状況はいつ見ても面白い。今年は野球のことをほとんど書かなかったけれど、たまには見ていたし、ヤクルト青木の打率トップは気にかけていたのだ。球場には足を運んでいない。巨人の凋落は面白いほどだ。大学の授業の準備。「現代能楽集」の勉強。午後、岩崎書店のHさんに会う。絵本の相談。少しまとまる。外に出たら意外に寒い。軽い風邪をひく。風邪をひくとすごく腹立たしい。国書刊行会から、テリー・サザーンの短編集が出ていると知ってすぐに注文。後期の文芸専修の授業にむけ、好きな作家で、しかし、あまり人が取り上げないだろう作家を取り上げたい。そのためにも、これまで読んできて好きだと思った作家の小説をもっと細密に読もうと思う。もう授業がはじまってしまう。あ、「キャンペーン問題」についてMさんという方からメールをもらったがそれはまた後日。
(9:26 sep.30 2005)
| Sep.28 wed. 「もう授業がはじまってしまう」 |
■こそこそする「研究会」の参加希望者からどっとメールをもらって困惑しているのが正直なところです。まだなにも具体的なことは決まっていないし、事態は流動的なので、どう返事をしていいか困った。参加を希望される方がいるだけでも嬉しいですが、ひとまず保留でお願いします。メールはほんとうにうれしかったです。
■少し焦ったのは、岡田君のワークショップに行ったとき会った早稲田の学生に、30日から授業がはじまると聞いたからだ。知らなかった。意外と早いじゃないか。東大は11日からだというので早稲田もそんなものだろうと考えていたのだ。しかも、なぜ30日の金曜日という中途半端な日からはじまるのだろう。やっぱり、なにごとも月曜日からはじめるべきじゃないか。といったことを考えていた水曜日である。
■小説の直しなどしていたら、Power Bookのハードディスクから異音がする。まずい。以前、これと似たようなことが起こって、iBookのハードディスクがいかれてしまったことがある。あわてて外付けのハードディスクにどうしても必要なファイル類をバックアップした。その後、復調。しかし、油断はならないな。デスクトップだったらハードディスク交換は簡単だが、ノートだとそうはいかない。iBookをばらそうと思って挑戦したが、かなりむつかしかった。Power Bookはどうだろう。そんなことはまあ、どうだっていいか。あんまりそういうことにも情熱をもてなくなってきた。
■このあいだから、書こう書こうと思って忘れていたのは、このところ覚醒剤や大麻で逮捕される事件がやけに頻発していることだ。民主党の元議員が逮捕されたと思ったら、医大の大学院生が逮捕されたり、自衛隊関係者が大量に逮捕されるなど、かなり話題性の高い事件が報道されるのが気になっているのだ。しばしば、「キャンペーン」というものはありますね。ある情報を連続的に流すことによって、なんらかの効果を生み出そうとする方法としてのキャンペーン。これらの事件は偶然、同じ時期に発覚したのだろうか。議員、医大生、自衛隊員と、やけによくできた並びだ。見せしめとしてはかなり高い効果が期待できる。私はドラッグ関係についてべつに積極的に肯定するわけではないが、それにしたって、こうしたキャンペーンから受けるのは、なにやら息苦しい市民社会の圧力だ。単純にその図を考えれば、べつにドラッグをやっていようがいまいが、その匂いがするというだけで市民社会がそれをはじき出すような排他主義が、少しずつ、身近に迫っているのを感じる。それは息苦しさです。
■「現代能楽集」のための勉強をしている。いろいろできそうな可能性と、むつかしさを同時に感じている。
(14:07 sep.29 2005)
| Sep.27 tue. 「ポツドールとニブロールとチェルフィッチュ」 |
■タイトルは語呂がいいという理由だけで決めました。
■私としては、まれに見る行動的な一日を過ごしてしまった。昼間、駒場のアゴラ劇場でポツドールの『ニセS高原』を観、夜は横浜に行ってチェルフィッチュの岡田君がやっているワークショップの見学に行ったのだった。ポツドールははじめて観た。とても面白かったが、噂に聞いていた話から想像していた舞台とはかなりちがったので、おやっと思いもし、こういうものはやはり自分の目で確かめないとだめだな。とても丁寧な演出だと思った。動線、人の交錯する視線や言葉、それらのやりとりがとても精緻に演出されている。端正である。平田君の演出に似ている部分もあるが、けれど、平田君の戯曲や演出では、突然、激高する人はいないし、背景に流れる人間観のようなものはまるで異なる。で、そうした「人間観」を持った作品を、最近、しばしば観ることがあるが、これはなんの影響か。いや、むしろ、「なにに影響されなかったのか」を考えたほうが正しいのではないか。というのも、その世界では、どこかに「悪意」を持った「いやなやつ」たちが登場するが、それはむしろ、しばしばよく見る風景だ。日常的に私たちは接している。それは肯定せざるをえない。だが、それを表面に登場させず、背景に漂うメカニズムとしてきっぱり表現したのが別役実だとしたら、ここには、別役実的なメカニズムの劇からは遠くにあり、いわば長いあいだ現代演劇を支配していた「不条理劇」の、「仕組み」や「構造」ではなく、「不条理劇」が「不条理劇」であるからこそ表出していた、人物像、人間観から逃れているのを知ることができるだろう。それはじつのところ、10年以上前、松尾スズキの劇をはじめて観たときから感じていたことだが、それが潮流になって影響を受けたのではなく、先にも書いたようにむしろ別役実に影響を受けなかったと感じさせるところに、現在性があるのを見る。なにしろ、圧倒的だったからさ、別役さんは。
■夜、横浜のBank Art NYKで、岡田君のワークショップを見学。このあいだ「吾妻橋ダンスクロッシング」で会ったとき岡田君が、見学に来てくださいと言うので、見に行ったわけではなく、前々から見学したかったのだがその時間がとれなかったのだ。その最終回にようやく間に合った。いろいろ書いてゆくときりがないが、なにより印象に残ったのは、講師を務める岡田君が座っている位置だった。それは変則的な「対面授業」だったのである。しばしば、芝居の稽古は、演技空間があり、その手前に演出家用の机がある。演出家の背後に稽古を待っている俳優たちがいる。ワークショップもたいていこれに準ずるのではないか。僕はそうだ。こういった位置関係で進行するものだが、岡田君は、たとえば学校の教室を思い浮かべてもらえればいいが、その教壇のようなところにいる。ただ、その教壇が生徒の側から見て左に寄っているのが「対面授業」とやや異なるところだ。教壇の右に空間があると想像してください。そこで、受講者の一人が話をはじめる。横から岡田君は見ている。そして、話者と、受講者(教室で言えば生徒のような存在)の両者に向かって、いまの話者の言葉とからだの動きについて解説をはじめる。このレイアウトが面白かったなあ。これはワークショップであると同時に、講義である。なにしろほとんどの受講者はただ講師である岡田君の話を聞いているだけなのだ。僕だったら、ワークショップに来た者には全員、その日のうちになにかさせないといられない(からだを動かすことを強要する)が、このワークショップでは、それはあまり重要ではない。同時に、岡田君と受講者は、話者が語る姿を見ている。おそらくこのワークショップで重要なのはこの部分だろうと思われる。それが興味深い。なにもしていない受講者は、なにもしていないのではなく、見ている。もちろん、芝居の稽古にしろ、ワークショップにしろ、待機している者らは「見ている」が、それをかなり強く、意識的に、深く、精緻にそうさせる。僕も見ることを要求するワークショップのプログラムをしばしばやるが、二ヶ月間それだけをやるというのはめったにないことだ。というか、まず最初に俺が飽きるよ。
■ニブロールの矢内原さんからメールをもらい、10月、東京写真美術館であるニブロールの「ワークインプログレス」などの誘いがあったのは少し前の話だ。美術館のような空間で、芝居とか、パフォーマンスをするのは、私にとって、ひとつの理想である。できたらいいが、そういった機会がなかなかない。
■といったわけで、まれにみる行動的な一日だったので疲れた。
(12:38 sep.28 2005)
■書こうと構想していたモンティ・パイソンの原稿は、どう考えても、しっかり書こうとすれば二週間後になる(なにしろ、そのための資料、ジョン・ラッセル・テイラー著『怒りの演劇 イギリス演劇の新しい波』喜志哲雄 中野里皓史 柴田稔彦・訳は古本屋に注文してもまだ届いていないし)だろうということで編集をしているE君とも相談し、今回は、推薦文のようなものにした。しっかり考えた解説はまたなにかの機会に書くことにする。アドヴァイスしてくれたTさん、Tさんの授業のノートのコピーをわざわざスキャンしてメールで送ってくれたUさんには申し訳ないことをしたのだった。
■日曜日はずっとその仕事だ。後期からはじまる東大駒場の授業の概要を書いて、内野儀さんに送る。プリントアウトして掲示板に貼り出すとのこと。「八〇年代アンダーグラウンド文化論」というタイトルの授業だ。ここでそれを先行して発表してしまおう。いけないのだろうか。でも、もし学生が読んでいたら、参考にしてくれると思えるのだ。「アンダーグラウンド」といういかにも古めかしい言葉を使ったのは、いまはなき日本で初のクラブカルチャーを発信していた「ピテカントロプス・エレクトス」があったのが原宿の「地下」だったからだ。
八〇年代と呼ばれる時代があった。それはいま、「オタク」という切り口で、あるいは、「経済のバブル化」という現象で解釈され現在と接続しようと試みられることはしばしばある。けれど、また異なる視点から顧みるとき、現在をより奥行きのある方法で理解することになるのではないか。たとえばそれは、「オシャレ」という言葉が奇妙な響きを持って出現した時代だ。その軽薄さは、「バブル」という言葉によって単純化される傾向は強いが、あらためてその本質を見つめ直すべきではないか。単に、「オタク」だけの時代ではなかった。「バブル」だけで語ることも理解を浅くする。音楽、演劇、美術など、様々な見地から「トーキョー」の「八〇年代文化」を再検証し、それが現在のなにと結びつき、新たに再生産されているか、いま目にする現象の背後にどんな可能性が潜んでいるかを探る試みだ。あえて、「アンダーグラウンド」という古めかしい言葉を選んだのには理由がある。かつて原宿の「地下」に、「ピテカントロプス・エレクトス」という、その時代の言葉でいうなら、きわめて「オシャレ」な「クラブ」があった。八〇年代の半ばだ。クラブカルチャーが大衆化する以前、そこには、ある特別な、密室性の高い文化があった。これはその地下から生成し、そして地上へと派生していった八〇年代の「裏文化史」である。
E君と話をまとめて授業計画を考えたが、それは次のようなものだ。
1・「ピテカントロプス・エレクトス」という場所があった
2・「YMO文化圏」と「ピテカン属性」
3・セゾングループの文化史ーー皿はなぜ買われ、
なぜ「こんな皿!」と割られる羽目になったのか
4・森ビルの時代と六本木WAVEの閉店(と音楽の話)
5・モンティ・パイソンとラジカル・ガジベリビンバ・システム
──表象文化論から見た「笑い」
6・80年代は勉強の時代=近代のやり直し(リプレイ)だった
7・その頃、「オタク」はどこで何を見ていたのか
8・「ピテカン」と「オタク」の距離:岡崎京子の位置
9・プロトコルとマニュアルを読み間違えること:明治の鹿鳴館
10・「ピテカン」はバブル時代の鹿鳴館
11・フィールドワーク:80年代の地図を持って現在の原宿を歩く
12・森ビルの都市計画と「趣都アキハバラ」
13・「80年代」は何を現在にもたらしたか
(控え)
1・講師を探せ!
8・「ロック」の衰退:「ロックは嫌い」から「ロックって何?」へ
(控え)
番外・蓮實重彦の「表層文化論」
と書いただけではぴんと来ない部分はあると思うが、先に書いた「ピテカントロプス・エレクトス」は八〇年代の「鹿鳴館」じゃなかったかとE君と話しているうちになったのだった。あるいは、「ロックは嫌い」というのは八〇年代に漂っていたムードだった。なにしろ汗くさいでしょ。八〇年代は汗くさいのを極端に嫌悪していた時代でもあったのだ。若い者が路上に腰をおろすのが消滅したのは八〇年代だったが、それが復活したのは九〇年代になってからだ。コンビニの前でよく観る風景は八〇年代にはまったくなかった。
■この授業は、火曜日の14時40分から(10月11日開始)。東大駒場のどこかの教室である。部屋もわかったらここに書きます。もぐり大歓迎。詳しいことがわかったらお知らせします。これはきっと面白い授業になると思う。そしてこれをまとめて本にしようというのが編集者であるところのE君の野望である。来年の春には刊行できるのではないか。
■夜、ある用事で吉祥寺に行く(スターパインズカフェでチケット購入)。用事があったがちょっとした夜のドライブだった。原稿が終わったので少し余裕。それから「現代能楽集」のための勉強。むつかしい。小説の推敲もする。J-Waveのある番組を聞いていて、外国のいい音楽が流れていたのネットで調べ、「iTunes」で調べたがなかった。アメリカの「iTunes」にはあるんだよ。日本の「iTunes」はなにからなにまで腹が立つ。たとえば、サンプル音源を聞くとアメリカのそれは丁寧にイントロを省略して歌からはじまるが、日本のそれは、イントロからはじまり肝心の歌がなかったりする。手間をかけろよ。しまいに怒るぞ、俺は。ぜんぜん買う気になれない。だって欲しいと思った音楽がないのだ。
■原稿がひとつ書けて少し油断した。のんびり過ごしてしまった。
■『トーキョー/不在/ハムレット』の演出助手をしていた相馬から、こそこそやる「研究会」のネーミング案が送られてきた。
「ひみつクラブ〈演劇〉」(こそこそする方向で)
「オルタナティブーズ」
(Alternativeというかっこいい概念を台無しにしてみました)
「a play without a country」
(故郷のない演劇。深い意味はなし。カート・ヴォネガットの新刊のもじり)
「火曜会」
(火曜にだけ集まる。「木曜会」より語呂が悪い。知らずに耳にした人には「歌謡界」だと思われる)
「くもり会」
(曇りの日にだけ集まる。もしくは集まるとなぜか曇る)
なるほど。こっちのほうも早いうちに具体化しなければ。何人かの人から参加したい旨のメールをもらっている。でも基本はこそこそなので、なにもあきらかにされることはないだろう。
■今年から来年にかけて、僕としては珍しく新刊本が何冊か出る予定だ。ご期待いただきたい。小説も発表する予定。それにしてもようやく秋になってきた。サンマがうまい季節です。
(8:50 sep.27 2005)
■寝屋川に住むYさんのブログを読んで(9月24日の「巨人ゆえにでかい」の日)笑ったなあ。それを思いついた城田君のくだらないことへのセンスと情熱に感動すらする。その面白さを伝えるYさんがまたうまいと思う。面白いことって微妙だな。
■以前、ある本の書評を頼まれた。架空の職業の本だったのだが、きれいな写真があり、架空の仕事を紹介する端正な文章があり、本の装丁はとてもきれいだ。全体を通じてきわめて趣味がいい。たしかに、「架空のなになに」というある種類の冗談には、スタニスワフ・レムや別役実さんなど、先人が数多くいるものの、本としてはとてもよくできていると思った。ただ残念なことに、ちょうどそのころ、べつの方にいただいた本に比べると見劣りしたのだった。それは様々な種類の公務員さんたちの集合写真の本だった。ごくふつうの人たちが、ただ職場で、その職域がよくわかる場所で、働いているときの姿のまま単に写真におさめられていた。ごくあたりまえの集合写真だが、それがきわめて面白い。このちがいはなんだったろう。「架空のなになに」という冗談がすでに過去のものだったかもしれないが、後者のごくあたりまえの集合写真の魅力は、虚構より現実が面白いということではけっしてない。というのも、そうして撮影されたそれらの写真も、やはり撮影したカメラマンの意図が存在するはずのものだからだ。実際、そうやって律儀にフレームに収まっている方々は大まじめなんだけど、でもなあ、冗談にしか思えないんだよ、これが。
■微妙なことだな。と、そんなことを考えつつ、この二日、原稿のことが頭から離れぬまま、23日は松倉のライブを聴きにゆき、24日は桜井君がプロデュースしている「吾妻橋ダンスクロッシング」を観た。二日とも、体調が悪いというか、なにか調子が出なくて(原稿のことがあったからか)、どちらも楽しみたかったがもうひとつ私のほうの調子が上がらなかった。受け入れの問題なのだろう。チェルフィッチュはやっぱり面白かった。もっと観ていたかったな。ただ、「吾妻橋ダンスクロッシング」の全体が興味深いのは、会場の空気がほかのダンスとはまた異なるところだ。観客論みたいな問題ではなく(なにしろ僕も一観客だから、ほかの観客については書けないしね)、なにか雰囲気がいい。このあいだ、クラブキングが出している雑誌「DICTIONARY」から「ライジングサン」の感想を書くように要請があり、とにかく「フェス」はすごいということを書いたのだった。「フェスの力」というようなものがあってですね、そうじゃなきゃ私はあの日、北海道で夜中まで音楽を聴くようなことをしなかったと思う。それに似たなにかを、「吾妻橋ダンスクロッシング」の会場で感じていたのだ。この催しも様々なダンサーたちが次々と現れ「フェス」と言えなくもない。「フェス」はすごいよ。今後、このシリーズはもっと盛り上がるんじゃないかな。
■一方、松倉は、歌が終わってから、「ありがとうございます」というまでの間が短かかった。あと五秒がまんしろよと、やってる途中でダメを出しそうになった。歌の余韻というものがぜんぜんないのだ。吉岡君のギターにずいぶん助けられていたな。でも、こうやってライブを開くことができたんだから少しだけ進歩した。そのライブには京都の大学で教えていたころの学生で、卒業し、いま東京にいる者が何人か来ていた。その一人に、「困ったら、連絡してこい」とアドヴァイスしたところ、いますでに困っていると言う。早いなあ。さらに「崖っぷちです」と言うのだが、だからって、俺にできることがなにかあるだろうか。ないとしたら、連絡してこいというのも無責任な話だ。ごはんをおごることぐらいはできると思う。むしろ、「腹が減ったら連絡してこい」というほうが正しいだろうか。ただ、相談には乗ることはできるし、メールでやはり、かつて教えていた学生から相談されることもある。なんかの偶然で出会ったのだから、なにかしてやりたいと思うが、私にできることなんてたかが知れている。申し訳ないほどたかが知れているのだ。
(9:10 sep.24 2005)
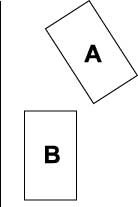 ■松倉のライブはいよいよあした(23日)だ。とても楽しみである。
■松倉のライブはいよいよあした(23日)だ。とても楽しみである。
■で、きょうもちょっとした楽しいことがあった。新宿で用事をすませたあと、家に戻る途中、それは新宿中央公園のわきあたりだが、路肩にクルマを止めて、携帯電話で連絡しようと思ったときのことだ(なにしろ運転中の携帯電話は違反だからな)。ふと気がつくとバックミラーになにやら点滅する赤いランプが見え、おやっと思ったのだが、思った通りのパトカーだった。そしてゆっくり接近してからパトカーは停車した。右の図が、そのときの状態である。これを見ると、なるほどなあと思ったのだ。Aがパトカー、Bが私のクルマだ。縦の線が歩道の位置を示す。
■こうやって前に止められたらどうにも発進はできない。逃げようとしたって逃げられない。さすがにプロのやることは効率的である。しかも、停車したと思った途端、さっと警察官が、出てくる出てくる。五人ほど。フォーメーションが決められているのかそれぞれの位置について私のクルマを取り囲む。ドア越しに声を掛けてきたのは初老の警察官だった。とても丁寧な対応だ。まあ、私に逃げる理由はなにもなかったので、携帯電話をかけようとしたと正直に話すと、「じゃあ、すいませんが、調べさせてもらいます」と言う。なんで? 免許証を確認させられる。なぜ? で、あとになって考えてみると、いろいろなテクニックが学べてたいへんためになった。まず、ドアを開けたのは私である。警察官はなにもしていない。というか一切、クルマには触れないのである。そしていったん、私が許可すると、あとはやりたい放題だ。クルマの内部を丹念に探る。ごそごそやっている。そのときカバンを助手席に置いてあったがそれも調べたかはよく見えなかった。というか、そのときべつの警官に話しかけられ、「どこに住んでるの?」と質問されれば、うっかり、住所を話して、視線がその警察官にいってしまうではないか。クルマのなかの警察官から目を離してしまった。すると次に、クルマの背後でべつの警察官が、「これは、どうやって、開けるのかな」と、わざとらしい芝居をしている。うしろのトランクが気になるらしい。開けようとして、しかし、クルマに触れようとしない。開けるような仕草はするが、「これ、いい?」とかなんか言っており、それでうっかり私も、こうやって開けるんですよと自慢気に開けてしまったのだった。知らないわけがないな、この人たちが、トランクの開け方を。つまり、すべては私の意志でクルマを開放させるのである。しかもそのとき、警察官がクルマのなかでなにをしているか見えない位置に立ってしまった。さすがだなあ、警察の人たちは。ものすごいプロフェッショナルな仕事ぶりだ。結局、なにも出てこなかった。あたりまえである。こういうときのために、小さなビニール袋に小麦粉とか入れて持ち歩いていたほうが喜ばれるのだろうか。あと、こう、ふつうの煙草をねじって銀紙に包んでおくとかね。あるいは、カーステレオから「犬のおまわりさん」を流し、「犬のおまわりさん、困ってしまってわんわんわわん、わんわんわわん」と聞こえるとか、警察の方に喜ばれるようなことをいろいろしたいと思ったのだった。楽しかったなあ。いろいろなことを経験するのはじつに新鮮である。
■さて、きのう書いた「モンティ・パイソン」の原稿のことで、さらにTさんからアドヴァイスのメールをいただき、かなり六〇年代のイギリスの演劇について学んだ。そして、じつはTさんは早稲田で演劇の講義もしているが、その授業を受けていた学生からメールをもらい、そのメールに講義のノートをスキャンしたものが添付されていたのだ。ありがたい。その最初のところには、こうあった。
「一九五六年の革命」
これがもう、唸らせる。なにしろ私の生まれた年である。この年、イギリスの演劇界にジョン・オズボーンが出現し、『怒りを込めて振り返れ』という戯曲を発表しているのだった。この登場はかなり劇的なものだったと想像される。その12年後の一九六八年にイギリスのBBCで『モンティ・パイソン・フライングサーカス』というプログラムが開始され、モンティ・パイソンの歴史はここにはじまるが、同時にその六八年、ピーター・ブルックが『なにもない空間』という演劇論を発表している。そして言わずとしれた、「六八年革命」の年でもあり、いやがうえにもこの時代を書くこと、そうした時代のなかに存在した「モンティ・パイソン」を書くことは、つまり「カウンターカルチャー」について触れ、もっと煎じ詰めれば「カウンター」について考えることになるのだと思った。だから、一九五六年から、六八年にいたる「12年間」が問題なのだと思える(ちなみに、日本において一九五六年は、ニューレフトが出現した年でもあるっていうか、民主化にわくハンガリーにソ連軍の戦車が侵攻した、有名なハンガリー事件の年なのだな)。少しずつ構想が固まってきた。いまピーター・ブルックを読み直しているところだ。さらに、資料を探さなければと思う。あとづけますよ。「モンティ・パイソン」がどこからどうやってきて、そして「モンティ・パイソン」になったのか。彼らの精神が、彼らの笑いが、なにを背景にして生まれ、そしてなにをして人を惹きつけたか。あるいは、なぜあれほど破壊的で革新的な笑いになったかは、その時代に負うところが多いと想像する。この原稿はいやがうえにも力が入る。でも、締め切りなんだよ。締め切りはとうに過ぎている。以前、坪内逍遙について書いたときは、こういった状態で、半年ぐらいかかってしまったわけだが、今回はそういうわけにはいかない。困った。だけど、面白い仕事は丁寧にやらないと気がすまないのだ。ジョン・ラッセル・テイラー著『怒りの演劇 イギリス演劇の新しい波』(喜志哲雄 中野里皓史 柴田稔彦・訳)も読まなければ。これ、少なく見積もってもあと二週間はかかるのじゃなかろうか。E君には申し訳ないが、勉強しないではいられないのだった。そうやっていつもみんなに迷惑をかけているのは、E君もよく知っているじゃないか。それを知ってて依頼してきたと私は勝手に解釈しているのである。
■ただ、この原稿の主眼は、「笑い」である。「モンティ・パイソンの笑い」だ。だが、それをしっかり見極めるためにこそ、歴史や背景、演劇との関わりを明確にするべきだと思う。それはけっして回顧ではないのだ。いってみれば、「いま」がどこからやってきたかを明確にすることでもある。
■だいぶ秋になってきた。やらなきゃいけないことが山積だ。打越さんからポツドールがいまやっている舞台がいいとメールがあったのでチケットを予約した。それも楽しみだけど、「現代能楽集」と「小説」のこともあって焦っている。
(5:17 sep.23 2005)
| Sep.21 wed. 「こそこそする」ver.2 |
■「下北沢スタジアム」のO君からきのう書いたネーミングのことでメールをもらった。「演劇ラボラトリー」「演劇発明室」「演劇発明所」といった名前で、それぞれなるほどと思ったのだが、「発明」というのはなんだかいい感じがする。メールをもらってとてもうれしかった。そういえばむかし、ワークショップをはじめてやったころ、「ワールドテクニック」とか「サマースクール」という名前でプログラムを組んだのを思い出した。こんどやろうと思うのはワークショップではなく、経験者たちによるトレーニングと研究の場だ。こっそりやっていきたい。つねにこそこそしていたい。どこで、なにをしているかなど、すべては秘密である。なんだかわからないが、とにかく、こそこそしたいと思ったのだ。
■ある学生が、「演出助手というのはどういうことをするのですか?」と質問をしてきたのは、まだ夏になる前だったか。その質問を、僕の舞台の演出助手をしたいと解釈したのは、いま考えると勘違いだったのかもしれないが、そうであろうと勝手に決めていた。やはり誤解だった。というのも、永井に紹介し、来年の公演スケジュールを伝えたところ、就職活動があるので演出助手をするのはむつかしいとのことだ。それはもっともだ。早く言ってくれてよかった。人の人生を台無しにするところだった。それで思い出したのは、僕が学生のころの話だ。当時から竹中直人とは友人だったが、竹中と同じように面白い男が多摩美にいて、なにか三人でやろう、舞台でもやらないかと、その男に持ちかけたことがあった。しかし彼は就職するからと言ってそれをきっぱり断った。そのときは、ひどく失望したが、いまになってみれば当然のことだと思う。僕と竹中は、その後、やくざな世界に足をつっこんでしまったが、彼はきちんと電通に就職し、いまはCMを作っている。どっちがいいって話じゃないと思う。それぞれの生き方だ。
■学生からいろいろ質問を受けるが、演劇のことはともかく、就職とか、進路とか、そういったことについてはまったく無能な教員である。ぜんぜんわからないし(僕に経験がないので)、へたなことを言って、その人の生き方を誤らせたくない。僕の話なんかぜんぜんあてにならないでしょう。「人生はギャンブルだ」とか、わけのわからないことを言ってみたい気持ちにもなるが、あんまりギャンブルはしないほうがいいと思うのだ。
■白夜書房からこんど出る「モンティ・パイソン」の本に関する原稿を書いている。とてもむつかしい。というのも、どの切り口で、いま、「モンティ・パイソン」を書いたら、これまでの解説や解釈とは異なるものが書けるかがそもそもむつかしいのだ。で、考えているうち、彼らが学生劇団の出身であることに着目するなら、その当時(一九六〇年代初頭のころ)のイギリスの演劇界がどんなことになっていたか、その後「モンティ・パイソン」になる彼らが、演劇の潮流に影響されたのか、それとも影響されなかったのか、考えるのは面白いと思いつつも、その裏付けがうまくとれないからだ。しかし、「モンティ・パイソン」を見る限り、そこには不条理演劇の影響はどこかあると思われるし、オックスフォードとケンブリッジ出身の、いわばインテリだった彼らが、ベケットやピンターらを知らないわけがない。あるいは、ある時代の空気として、共時的に、「モンティ・パイソン」と「不条理演劇」が育っていった可能性もある。イギリスの六〇年代初頭の演劇シーンがどうなっていたかなど、いろいろ調べる必要はあり、そのあたりの論を展開しようと思うとこれは大変な作業になってしまった。でも、面白そうなんだよな。それは「モンティ・パイソン」の笑いの質を分析するには格好の切り口だと思うのだ。あるいは、彼らの、あの「笑い」に立ち向かう精神がどこから生まれてきたかを知るひとつの方法にもなると思える。むつかしいのだ。だから考える。なおも考える。
■と、これを書いてアップした直後、以前、僕が演出したスコットランドの戯曲『雌鳥の中のナイフ』を翻訳してくれたTさんから、六〇年代のイギリス社会についてアドヴァイスのメールをいただいた。ありがたい。なんと、一九六八年までイギリスでは戯曲の検閲があったという。驚いたなどうも。また詳しくは後日。原稿を書かねばならない。
(3:40 sep.22 2005)
■祝日だとは知らなかった。
■いま、ぴたっと来るキャッチーなネーミングを考えていたのだった。「演劇養成所」なんていうのは問題外だ。「演劇実験室」となると、寺山修司だ。「アクターズスタジオ」は冗談じゃない。「アクターズ」って言葉が腹立たしい。学生の発表公演を終え、演技というか、演技における俳優の表現になにかまた、べつの方法を考えるべきだとふいに思いたって、そうした「場」を作りたいと思ったのだ。思考するだけだったり、イメージするだけだったりではできないと思い、俳優を集めて試みをする場を、舞台作品を作るときだけではなく作れないかと考えたとき、思いたった。ネーミングは大事だな。やっているわれわれが、そのネーミングのもとに過去の演劇表現とは切れた位置から、演技のアプローチをしたいと思うのは、早稲田の発表公演を終えていろいろ反省したからだし、「演劇研究会」とか、「演技研究会」とかじゃなくて、なにか生まれることを目ざすにふさわしい名前があるはずのものだ。しいていうなら、その名前に目ざすべき表現の方向があると思える。
■そんなおり、私は恵比寿にある東京都写真美術館に行った。「 ブラッサイ──ポンピドゥーセンター・コレクション展」を観た。なにか考えるヒントや、刺激を受けると思ったからだ。少し考えることが生まれた。もちろんブラッサイの写真はすごくいいが、それと同時にべつのフロアで展示されていた、「 決定版! 写真の歴史展10周年記念特別コレクション展 写真はものの見方をどのように変えてきたか 第4部 混沌」を観た。こちらにも刺激されたのだ。
■そんなことを考え、一日が過ぎて行く。ほかのことに集中できない。いつから俺は演劇のことばかり考えるような人間になってしまったのだ。原稿もぜんぜん書けていないし。まだきっとべつの方法があるはずだ。それを発見することができたらこれ以上のことはない。まあ、基本的にはかっこいいことしか考えていないのだが。10月から動き出そうと思う。しかも、若い者だけではなく、大人で経験も豊富な人が仕事のあいまに、参加してくれたらいい。それがそのまま本公演の舞台に結びつくことはないと思うが、しかし、考えることによってべつの方法が発見できるかもしれない。純粋な研究室になるだろう。いま有効な演技はどこにあるのだろう。なんかいいネーミングはないだろうか。
(4:35 sep.21 2005)
■深夜、どうしても必要なものがあって環七沿いにある「ドン・キホーテ」に行ったのだった。つくづく後悔したのは、「ドン・キホーテ」に行くとすさんだ気持ちになるからだ。駐車場はやたら悪臭がする。深夜ということもあってかほとんどの客がヤンキーだった。たとえば、エレベーターを乗るに際し、その彼女がまず乗り、まわりの迷惑など顧みず「開」をボタンを押させといて、男は悠々とした態度で自動販売機でジュースを買っている。この無神経さがわからない。深夜に行ってしまったのだから、向こうから見れば、こちらも謎の人物に見えただろうが、それにしたって、こうしたことが頻発する「ドン・キホーテ」に、なにかこの国の闇を見る。単純にモラルがないとか書く気はさらさらないが、こうしたこともまた、「ぼろ勝ち組とぼろ負け組」という構造が生んでいるのだろう。行かなきゃいいんだよ。「ドン・キホーテ」に行かなければすさんだ気持ちにならずにすむが、つい行ってしまった私がばかだ。そしてその一方で、取り澄ました六本木ヒルズのような世界はあり、そして一年に自殺者が三万人いるこの国は、なにか、たがが外れてしまったのを感じる。
■仕事にとりかかる。まずは小説の推敲。それから「現代能楽集」の予習。舞台のことを反省する気持ちを引きずりつつ、それにひとまず区切りをつけ、仕事はしなければならないのだな。特に小説を完成させようと力を入れる。読み返してみると、どうも気にくわないところが多々あり、読んでいるうちにいやな気持ちになった。「現代能楽集」は時間がないが大事な仕事だ。しかも、能の世界は広大だ。昼間、テレビで能の舞台をやっていたので観ていた。きれいだなあ。なんというきれいな所作や身体だろう。
■きょう、ふとしたことで、なにかべつの舞台表現について思いつきがひとつ生まれる。ただ、思いつきなので、それをどう舞台にするか、どう表現したら面白いかなど、これから考えるべきだろう。仕事をしようと思うが、つい演劇について考えている。四六時中、考えている。なにか生まれそうだ。そして小説。書き終えたとはいえ、まだ、これからしっかり推敲しいいものにしたい。あと三週間ぐらいで大学もはじまってしまう。それまでに、やることはいろいろあり、仕事を整理しておかなければな。もう九月も半ばを過ぎたが少しむし暑さを感じるのはなぜなのだろう。ここは亜熱帯なのか。亜熱帯になってしまったのか。
(5:44 sep.19 2005)
| Sep.17 sat. 「またひとつ舞台を終えて」 |
■早稲田の「演劇ワークショップ」の発表公演が終わって、それから長い夜は、朝まで打ち上げだった。
■16日の昼の回には、『トーキョー/不在/ハムレット』にも出ていた南波さん、鈴木将一郎、渕野、それからやはり早稲田で僕の授業を受けている何人かの学生が来てくれた。終演後、気がついたらその学生たちの姿が見えなくなっていたので、話ができなくて残念だった。それで公演をやっている36号棟にあるテラスのような場所で南波さんらと話しをしたが、それにしても、まあ、ふつうの公演だったら昼の回が終われば演出家としてはなにかやることがあると思うがなにも仕事がなくて、なにをしていいかわからぬままに時間が過ぎる。夜の回の直前、出演者たちに一声かけて開演を待つ。夜は、制作の永井をはじめ、白水社のW君、白夜書房のE君、青土社のMさん、Hさん、Yさんら、編集者たちがどっとやってきたのだった。都合で、観客は舞台を通って客席まで行く。すると遅れてきた観客はいままさに舞台で芝居をしているところを通って客席に行かねばならず、まあ、それが演出でもあったのだが、青土社のMさんが見事に遅れ、芝居中に舞台を歩いてくれたのがありがたかった。ずばり演出の意図が的中。あ、15日は、上村が遅れて来て舞台から出現したのだな。笑ったなあ、上村は。あと15日には打越さんも来ていた。編集者の方々に頭がさがる。
■といったわけで、9月5日からはじめたワークショップはきのうで終わり。公演を含めて12日間。公開ゲネプロ、公演の2日は稽古らしい稽古はしなかったから、すると10日。しかし直前に「場あたり」っていうか、「荒通し」っていうか、「テクニカルリハーサル」や「通し稽古」で2日とられ、8日。しかし稽古の休みが2日(一日は自主練習)あって、つまり、稽古したのは6日だよ。9月5日はチェーホフの『三人姉妹』の読み合わせと自己紹介で終わり、9月6日は、それを5分間でまとめて人に話すというのをやって台本を作る作業をしていたと考えれば、結局ですね、実質的な稽古は4日だ(自主練を含めると5日)。これはすごい。これはあくまでAクラスの話。Bクラス、Cクラスがどういう稽古をしていたかまったく知らない。似たような状況ではなかっただろうか。しかも、毎日稽古の開始が午後一時で、終わるのが四時半。その後、夜はスタッフワークの授業になる。おまけに僕は遅刻しがちだった。よくこれで形だけでもできたなあ。驚くしかないぞ。それには、スタッフワークの先生方やTAの人たちに負うところが大きかったように思う。舞台の作り方などほんとんど知らない学生たちがまがりなりにも照明を吊り、音を出し、舞台監督部は裏で進行し、制作は様々な事務的な作業をした。美術や衣装、小道具も先生たちに助けられながら作ることができた。京都の大学でも同じ経験をしてきたが、今回のように短期間になると、よりそのことを強く感じた。むしろこの授業の主眼はそこにあるのだろう。スタッフワークのための授業だと考えたほうがわかりやすい。それが最初からわかっていたら、全体の演出プランも変わっていたかもしれない。
■とはいうものの、俳優たちのための側面ももちろんある。最終的にはせりふをきちんと覚えたんだからよくやった。やればできるのだな。Aクラスのことしか僕にはわからないが、台本ができた時点で、単純に、これできるのか、覚えられるのだろうかと正直思ったのは、なにしろ、舞台経験のない、というか、二週間で八単位もらえるから履修した安易な考えの学生だっているような状況だったんだから、それでやろうっていうのがそもそも実験的じゃないか。寺山修司だってそんなことは考えなかったと思う。だが、人は成長するから不思議である。これまで私はワークショップによる「奇跡」というものを一切信じなかったというか、むしろ「奇跡」が起こることを否定してきたが、少しだけ発生してしまった。失敗したなあ、奇跡が起こっちゃったんだよ。この感じは、かつて静岡県袋井市でワークショップと発表公演をやったときに似ているが、袋井の時はもっと時間があった。だから不可解な気持ちにさせられた。
■あるいは、もっと稽古をしたかったのも正直なところだ。クオリティをより高めることはできた。というか、クオリティより学生たちともっと深く関わることで発見することがあったはずだ。それが薄かったのも残念だ。形になればいいってもんでもない。表面にあらわれないところで、この授業を通じて僕自身もまたなにか見つけられたかもしれない。あるいは、経験のある者も、もっと時間や余裕があれば、演劇そのもの、演技そのものについて考える時間が生まれたはずだ。ナターシャを演じたTやM、マーシャを演じたSらは経験があってある程度芝居ができたからその役を振ったが、それはいってみれば形を作るための役割だ。そうならざるえをえなかった。彼女、彼らが表現について考える機会にならなかったんじゃないかと悔いるのだ。もっと演出してあげるべきだったな。
■このワークショップの発表公演は、今年で七回目になるそうだ。去年までのことはほとんど知らない。あとで聞くと、これまではあまり、現代演劇のAクラス、古典芸能のBクラス、ダンスのCクラスが融合することはなかったそうだが、今年は多少あり、でも最後の舞台を観ながらもっとできたと思えてならなかった。ばらばらで演出していたが、ちょっとした演出の工夫で、つなぎの部分などより融合することができただろう。それは次の機会の課題。なにしろ、僕は総合演出ってことになっているからな。それに気がついたのは授業がはじまる三日ほど前だ。もっと早く気がつけって話である。終演後、去年までTAをやっていたという人と話しをすると、ほとんど音楽がなかったことを指摘されたが、特に僕の担当する現代演劇は意図的にそうした。今回の場合はどう考えてもいらない。そういえば、音響を担当している学生に客入れの音楽をどうするか質問されたのだが、それもやっぱり、いらないと答えたのだな。逆にもっと映像を使うべきだった。特に生中継。テクニカルな問題でうまく活用できなかった。生中継の練習をする時間がなかったので、いちばん安全策をとったというべきか。失敗してもいいからもうずっと生中継でも構わなかったな。舞台上に、なぜか、どうでもいいものを中継しているカメラマンがずっといるという状況でもよかったんじゃないか。といった自分の反省はいくつかあるが、学生たちはよくやった。それで彼ら、彼女らに、この授業を通じてなにか得るものがあったらそれにこしたことはないのだが。まだ書き足りない気がするが、それは思い出したらおいおい書くことにする。
■打ち上げは朝まで。いろいろな学生と話しができて楽しかった。特にBクラスの男たちと音楽の話などして面白いが、気がついたらまわりは男ばかりで、残念なことになっていたのだ。居酒屋の外に出るともう明るくなっていた。「じゃあ、もう二度と会うことはないと思うけれど」などと、照れくさいのでいつもの調子で話してみんなと別れ、クルマで家に戻る。眠ろうとするが舞台のことをいろいろ考えていた。
■で、朝刊を読むと、早稲田の学生とジャニーズが一緒に舞台を作るという記事があった。もちろん事前に知っていたのだが、それというのも、16日の昼の公演のある直前、控え室になっている教室にいたら、ジャニーズの岡本君がやってきたのだった。話しをしたら僕の舞台を観たことがあると言い、それも「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」時代の話だった。思わず、「きみ、いくつ?」と質問をしてしまった。
■眼が覚めたのは夕方。また舞台のことを考える。きょう一日は休み。またあしたから仕事だ。小説をまとめよう。原稿もある。それから「現代能楽集」のことも考える。来週は打ち合わせもある。いくつか悔いが残ったけれど、またひとつの舞台が終わった。
(4:59 sep.18 2005)
「富士日記2」二〇〇五年九月前半はこちら → 
|
|

